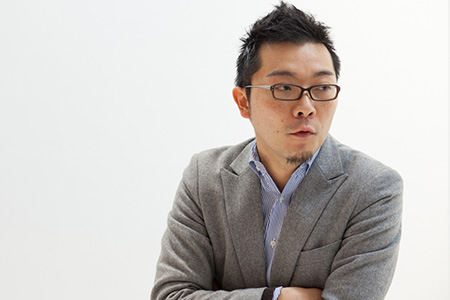ベンチャーキャピタルからクリエイティブ業界への転身
- 2013/02/07
- SERIES
- インタビュー・テキスト:小野田 弥恵
- 撮影:すがわらよしみ
Profile
重村 正彌
1979年生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、大和証券グループのベンチャーキャピタル「エヌ・アイ・エフベンチャーズ株式会社(現:大和企業投資株式会社)」に入社。5年間勤務したのちに退社し、「ガスアズインターフェイス株式会社」へ入社。現職では、企画営業をはじめ、総務、人事、経理などもこなす。
坂本龍馬になるより、彼を支える寺田屋お登勢になりたい
―重村さんは学生時代、クラスのなかでどんなポジションでしたか?
重村:小学生のころはわりと静かなタイプでしたね。教室のすみっこで、マイナーな雑誌をくすくす笑いながら読んでるヤツみたいな(笑)。小学校は受験校で成績絶対主義! みたいな校風だったから、そこそこ上手く立ち回ってはいたんですが、価値観を押し付けられるのがすごく嫌でして。でも一方で、ここの校訓が今でも自分の価値観にすごく影響しているんです。「人のお世話にならぬよう、人のお世話ができるよう」という教えなんですけれど。
—迷惑をかけず自由にやるが、人のサポートをしよう、といいますか。
重村:中学からは慶應義塾大学の付属校で、SFCの一期生だったんです。そんな、先輩が誰もいないという状態からのスタートだったから、本当に自由でしたね。運動会の出し物は何をするかということから、自分たちで考えたりして。この頃から、みんなで何か考えたり、仕切ったりすることが好きでしたね。でも、僕は委員長や応援団長をやるタイプではなくて、その周りでヤジをとばして、トップを盛り立てるポジションだった。今の仕事観にも一貫しているのですが、僕は何かやりたいことがある人のサポートをするのが、一番面白いと感じるんです。飽きっぽくて、自分で1つのことをずっとやろうとしても続かないから、っていうのもあるんですけれどね(笑)。
―そんなサポートしたいモチベーションが、新卒で入社したベンチャーキャピタルを志望するきっかけにつながったのは?
重村:大学で中小企業論を専攻していたのですが、たまたまアメリカのベンチャーキャピタルの人が講演する機会があって、当時アメリカでベンチャーキャピタルが盛んだってことを知ったんです。経営コンサルと違って、ベンチャーキャピタルはロジックを使うだけでなく、実際に投資をすることでリスクを背負いながら企業にコミットしていく。何かを実現したい人や企業に対して自分自身もより突っ込んでいける。そこに魅力を感じたんです。
―それで就活は上手くいったんですか?
重村:新卒の採用をしているベンチャーキャピタルは当時、国内にも5社あるかないかくらいだったので、すべて受けました。面接では、面接官のおじさまたちの前で幕末の例え話をして、「僕は坂本龍馬になるより、彼を支える寺田屋お登勢になりたいんです!」なんて口説いたらわりとウケるかな、なんて考えたりして(笑)。結果、エヌ・アイ・エフベンチャーズ株式会社(現:大和企業投資株式会社)に入社しました。
もっと現場に! と転職を決意
―確信犯ですね……(笑)。そこでは実際にどのような仕事をしていたんですか?
重村:新人のころからすでに、出資先の会社を探して、例えば、一億円投資するためのプレゼンを10人くらいの役員の前でしていましたね。いわゆる年功序列みたいなものは全くなくて、どの会社に出資するのかを決めるのも自分。だから「これをやれ」と指示されることがない分、自分がやりたいことに向かって邁進できる環境が肌に合っていたみたいで。
―金額の規模も凄いですね……(笑)。具体的に、どんな企業に投資を行っていたんですか?
重村:当時、すでにITバブルは弾けていましたが、それでも周りではインターネットやテクノロジー系の会社に投資しようとする風潮がありました。でも僕は、コンテンツに投資したかったんです。例えばケータイゲーム、オンラインゲーム、音楽、アニメや映画などですね。
―なぜコンテンツに興味が?
重村:テクノロジーには特許など、対外的に誰かが認めた証明書みたいなものがあるから、誰にでも価値が分かりやすいと思っています。一方でコンテンツは嗜好性が強いから、価値判断の指標がつけにくいじゃないですか。今でこそ「CAMPFIRE」のようなクラウドファンディングも認識されてきていますが、当時はコンテンツに価値付けをする人があまりいなかったんです。だからこそ、この分野は面白いんじゃないかなって。そのころは映画に興味があったので、映画プロデューサーの養成講座を自腹で受けて、アメリカの映画づくりを学んだり、海外の映画を日本に持ち込んでいる会社を探して出資したり、色々していましたね。
―徐々に、今の業界へと繋がっていくように感じます。それで転職しようと思ったきっかけは?
重村:ある程度、仕事も経験させてもらって、今度はもっと現場に深くコミットしたいと思うようになったんです。投資先の役員会などで、社長さんに「なんでこんなに数字が悪いんですか?」とか「こうしましょう!」などと口を挟むこともあって。もちろんそれも仕事なのだけど、内心「自分がやったこともないのになんでこんなことが言えるんだろうか……」っていう矛盾した思いも強くなってきて。もともとの飽きっぽさも重なって、そのときの仕事にも満足してきた自分もいたんでしょうね。だからもっと実務的で、かつ、いろんな業種を横断できる仕事がしたいと思っていたときに、当時の上司の紹介でいまの会社に出会ったんです。
- Next Page
- ソリューションとしてのクリエイティブ
ソリューションとしてのクリエイティブ
—もともとは、同社に投資をしようとしていたんですよね。そもそも、どんな会社なのですか?
重村:アーティストの表現をどこまで広げられるかをミッションに、主に商品開発の企画提案やプロデュース、アーティストのセレクトやマネジメントなどを双方向に行っている会社です。結構、業務が幅広いので、一言でいうのはなかなか難しいんですが(苦笑)。今はクライアントの約8割がアパレルメーカーで、つながりのあるアーティストとのコラボ商品の提案などを手掛けています。例えばUNIQLOさんの「UT」で企画開発・デザイン提供を行ったり、百貨店・セレクトショップ向けの商品を開発したりしています。あわせて、商品開発だけではなく、売り場やカタログの提案や制作の発注なども行っています。
クライアントとクリエイター、商品開発から販促までを横断して行う会社はなかなかないので、ここならもっと現場にコミットできる! と思ってはじめは興味を持ったんです。結局、投資はできなかったんですが、僕が入社することになったと(笑)。
—なんだか面白い流れです(笑)。今は具体的にどんな仕事をしているんですか?
重村:基本的にいまの会社は、取締役以外は肩書きが無いので、できることは何でもやるっていうスタンスです。最近では、表参道ヒルズで、弊社で取り扱っている“えをかくえほん”シリーズ「supereditions」を題材にしたインスタレーションの展示を行いました。絵本の中にはストーリーだけが書いてあって、子どもが自分で絵を描く仕組みになっています。これを広めるために、まずイラストレーターさんに、ストーリーのイメージを巨大な絵本型のインスタレーションで表現してもらって。アーティストが表現したいことと僕たちがやりたいことをうまく組み合わせて、両方がうまくいくような企画を心掛けています。
—なるほど。重村さんはもともと絵とかアートが好きだったんですか?
重村:いえいえ。むしろ絵を描くのが大の苦手で、美術の授業で作った作品を帰り道に駅で捨てて帰るような子どもでした(笑)。自分で作るものは本当にひどくて、人に見せるのも恥ずかしかったですね。それもコンプレックスだったからこそ、作り手に対しての憧れは今でもあるのかもしれませんね。今でこそクリエイティブな業界にいますが、僕はもともとアートに詳しいわけでもないですし、今でももっと勉強しないといけないなと思っています。
—そうなんですね。例えば、前職での経験が活きていると思うことは?
重村:強いて言えば、クリエイターが何を表現したいかを引き出すヒアリング力でしょうか。ベンチャーキャピタルでは、自分が投資先を絶対的に信用していなければ「ここに投資したい」と役員にプレゼンできません。今の仕事でも、制作物に関してはやっぱりアーティストを信用しきっているんです。あとはクリエイターが表現しようとしていることが、いかに筋が通っていることなのか、それをちゃんとクライアントに伝えること。これに関しては前職での経験が役に立っていますね。だから、僕にとってクリエイティブって問題解決、ソリューションとしてのものっていう感覚が近いと思ってます。
末っ子は末っ子の道をゆく
—アートへの知識不足を、コミュニケーション力で補うのが、今の重村さんの生きる術なワケだと。
重村:そもそも僕のなかで、「アート」だけがクリエイティブだ、という意識がないんです。以前、太陽光電池を作っている会社のWEBサイト制作をしたときに感じたのですが、クリエイティブやデザインって「伝えたいことをどう伝えられるか」ということにつきるなと。太陽光電池で何をしたいかをヒアリングして、このツールでユーザーとのコミュニケーションをやりましょうと提案することも、アパレルのデザインを企画するのとそんなに変わらないのかなと。
—伝えたいことを伝えるためのクリエイティブだということでしょうか。
重村:そう。だから例えば、商品を開発するまでに出したアイデアやコンセプトも、売り場の作り方も、全て含めてクリエイティブだと思っています。デザインやクリエイティブという概念をこういう広い意味でとらえているからこそ、僕は科学者も和菓子職人もクリエイターだと思って尊敬していて。絵を描いている人だけがクリエイターじゃないって思うんですよ。
—なるほど。重村さんならではのフラットな視点ですね。では、いわゆる大手企業からベンチャー企業へ転職した当時、周りの反応はどうでしたか?
重村:転職当時は28歳だったんですが、同時期に結婚をしたんですよ。奥さんは前職で同じ職場だった人で、当時25歳。あまり先のことを深く考えていなかったのか、応援してくれましたね。
—そうなんですね。お話を伺っていると、重村さんは自分がやりたいことを常に冷静に見極めて、素直に突き進んできた印象を受けます。「こうすべきだ」という決めつけがなくて、むしろ「やりたいようにやる」というような、末っ子みたいな自由さがあるというか。
重村:あ、僕まさに末っ子なんですよ(笑)。上に兄がいて、兄は商社に勤めて結婚して子どももいて、最近では海外勤務していたりと、まさに「王道」といった人生を歩んでいますね。ちなみに僕の奥さんも長女でしっかり者なので、頼らせてもらっています(笑)。彼らに比べて、末っ子として育った僕の場合は、わりとなんとかなると思っている部分があるかもしれない。自分は飽きちゃうし我慢ができないし、やりたくないことならやらなければいいって思っちゃう。悩んでいるより、行動したほうが早いですから。例えば会社を辞めるなら、そう思ったときに辞める算段をとってしまえばいいっていう考えなんです。
—感覚的に動いているようで、進むときは論理的にことを運ぶんですね。まさに「人のお世話にならぬよう、人のお世話ができるよう」を体現していると言いますか……(笑)
重村:あっ、それかもしれませんね(笑)。
—小学生のときから一貫した精神(笑)。では最後に、今後の目標などはありますか?
重村:今、奥さんの実家が山梨で、桃園をやっているんですよ。僕は稲刈りもやったことがないんですが、30代になって都会と田舎で暮らすということに興味が湧いてきたんですよね。最近は、人と会うときに桃の差し入れをしたりして。今33歳なので、35歳になるまでには、週の二日、できれば半分くらいは山梨で仕事ができればいいなと思っています。まずはそういう環境づくりからはじめようかなと。とにかく、やってみなくちゃわからないですね。
Favorite item

伊藤潤二『恐怖博物館』
Back number
私としごと

「好きなこと」を仕事に。異業種から「ポケモンカード」のゲームデザイナーへ

「アーツ千代田 3331」設立メンバーが語る、アートを生業にするという覚悟

「好き」に貪欲に。元コピーライターがIDEOでデザインリサーチャーになった理由

広告は未来へのプロトタイピング。気鋭のプランナーが考える、PRのこれから

『テラスハウス』は台本がないのになぜ面白い? 生みの親が見せたいリアリティー

その哲学に憧れていたミナ ペルホネンが、今では私の仕事場に
Profile

GAS AS I/Fは、クリエイターの表現の場を創り出すことを目的に、1996年に複合メディア『GASBOOK』を発行しました。
これまで、約15年間にわたって培った国内外のクリエイターとのネットワークを核に、様々な企業、個人に向けてサービスや商品の開発を行っています。
現在も様々なプロジェクトが進行しており、より多くの表現の場を生み出すことができる「プラットフォーム」を目指し、活動を続けています。