東日本大震災で実家が津波に流された経験を綴った『ナガサレール イエタテール』、認知症になった祖母の介護問題を専門家の解説を交えながら描いた『マンガ 認知症』など、エッセイ漫画で人気のニコ・ニコルソンさん。近年は『呪文よ世界を覆せ』を連載するなど、フィクション作品にも挑戦中だ。
そんなニコさんは、自身のこれまでの漫画家人生を「王道とは言いがたい」と語る。イラストレーターとして働きながら徐々に「漫画家」としての仕事の割合を増やしていくなかで、何を考え、どんな選択をしてきたのか?
SNSの台頭以降、多様化する漫画家の働き方。その大きな変化のど真ん中で、自分の関心事にとことんこだわりながら活動の幅を広げ続けているニコさんに、「これまで」と「これから」、そして創作における信念をうかがった。
- 取材・テキスト:辻本力
- 編集・撮影:吉田薫
Profile

ニコ・ニコルソン
漫画家。宮城県亘理郡出身。東京都在住。代表作に『ナガサレール イエタテール完全版』(太田出版)、『マンガ認知症』(ちくま新書 大阪大学教授・佐藤眞一との共著)、『古オタクの恋わずらい』(講談社)など。現在『呪文よ世界を覆せ』を「月マガ基地」にて連載中。
初めてハマったのは少年漫画。「オタクのど真ん中」が上京するまで
ニコさんの漫画好きは、母親ゆずりだったという。子どもの頃、実家にあった母親のコレクションを介して漫画と出会い、徐々に自分の好みを確立していった。
ニコ:家には萩尾望都先生や竹宮惠子先生ら、いわゆる「花の24年組」の作品や一条ゆかり先生の作品が並んでいて、いまから考えてもなかなかセンスのいいラインナップでした。加えて、叔父さんが少年漫画の文化を持ち込んでくれたので、そのミックスで成長した感じです。
一番最初にハマったのは、『ドラゴンボール』でした。当時は『少年ジャンプ』の黄金期だったこともあり、『SLAM DUNK』に『幽☆遊☆白書』と名作のオンパレード。そうした作品に触れていくなかで、自然と「自分も描きたい」という気持ちが芽生えていきました。
その後は少女漫画にもどっぷり浸かり、オタク街道ど真ん中な青春時代を送りました。ちなみに、『古オタクの恋わずらい』は、当時のことを思い出しながら描いた半自伝的な作品です。
![]()
その後、成長したニコさんは、地元の宮城から仙台にあるデザイン専門学校に2年間通い、卒業後、同地にあるデザイン事務所に入社する。しかし、その生活は長くは続かなかった。
ニコ:とにかく絵に関わる仕事ができれば、という思いで入ったんですけど、やりたいこととはだいぶかけ離れていて。で、たいへんお恥ずかしいのですが、試用期間中に辞めてしまいました。それから一念発起して、20歳の時に上京しました。
居候生活から出版社勤務へ
東京での生活を始めたニコさんだったが、勢いで出てきてしまったため、住む場所すら決まっておらず、当初は居候生活だったという。親の反対などはなかったのだろうか。
ニコ:その頃は叔母の家と、一足先に就職を決めて上京していた当時の彼氏の家を行ったり来たりするダメダメな生活でした。でも、母親は反対しませんでしたね。好きにしなさい。その代わり、困っても私は何もしないからね、というスタンスで。自由にさせてあげるけど、それには責任が伴うんだよ、というのを体験から学べという方針だったんです。
さすがにこの生活を続けるわけにもいかず、まずは何をさておき働く場所だろと、ひたすら履歴書を書く生活を送るようになりました。最終的に、バイトでもパートでもいいからと出版社に的を絞って就職活動をしたところ、映像や音楽やゲームなどを幅広く手がける大手企業の出版部門にDTPオペレーター的な立場でもぐり込むことができました。
さまざまなジャンルを扱う会社だったので、雑誌に書籍と作る印刷物もそれはそれは多岐にわたっていました。それに、とにかくすごい仕事量で。最初のうちは、何でも「できます」と引き受けていたんですが、イラストを20点描いて給料が一緒とかになると、さすがにな……と。それで意を決して「イラストのギャランティだけは別にしてほしい」とお願いしました。上司の方も考えてくれて条件を通してくれたので、ありがたかったですね。この時に、働く上での交渉の大事さを学びました。
ブログ / エッセイ漫画ブームの波に乗って
ニコさんが最初に注目されるきっかけとなったのは、当時流行していた「ブログ」だったという。ブログは、個人が発信する場として現在主流になっているSNSやnoteの前身的な存在だった。
ニコ:日々の出来事とか、旅行に行った時のことなどをイラストとテキストで綴っていて。いわゆる「エッセイ漫画」でしたね。
当時、タレントの真鍋かをりさんのブログが人気で、彼女は「ブログの女王」と呼ばれ、同名のテレビ番組を持っていたのですが、なんとそこで私のブログを紹介していただいたんですよ。2006年のことです。
小栗左多里さんの『ダーリンは外国人』シリーズをはじめ、エッセイ漫画が大流行していた時期でもあったので、そういう観点から注目していただいたんだと思います。
現在もブログにて日記や旅の記録を掲載している
この露出をきっかけに、他社からの仕事が増え始めた。仕事を受けていくなかで、ニコさんは「もっと自分の面白いと思っているモノ/コトについて発信する場がほしい」という願望を抱くようになっていった。
ニコ:会社で出していたDVDの雑誌で、好きな映画をイラストを交えてレビューする1ページコーナーをいただいたことで、その願望に拍車がかかりました。すごく面白くて、もっとこういうコラム的な仕事がしたい!って。
編集長に「もっとやらせてください!」と直談判をしたら、「どんなものを描きたいの?」と。私は「漫画を描きたいです!」とは言ったものの、漫画だけだと心もとないので、じゃあ漫画で漫画を紹介する連載にしようということになり、「ニコ・ニコルソンのオトナ☆漫画」が始まりました。
そして、この連載で日本橋ヨヲコ先生の人気漫画『少女ファイト』を取り上げたことが、思わぬ仕事に繋がります。同書の担当編集者さんから、『少女ファイト』の新刊に付録として付けるアンソロジーに漫画を描いてくれないかとオファーをいただいたんです。これが、私が出版社から「漫画の依頼」をいただいた最初の機会でした。
![]()
東日本大震災という転機。『ナガサレール イエタテール』を駆動した使命感
こうして、憧れだった漫画家としての第一歩を踏み出したニコさんは、2008年に自身の上京エピソードを綴ったエッセイ漫画『上京さん』を上梓、出版デビューを果たす。しかし、当時はまだ「漫画家」と名乗ることに気後れがあったという。
ニコ:ずっと「イラストレーター」という肩書きで仕事をしてきて、ようやく「漫画」と呼んでいい本を出せたものの、やっぱり自分は漫画家としては傍流だなという意識がなかなか抜けなかったんです。
いまでこそSNSで人気が出てデビューみたいな道もありますが、当時は漫画家といえば、雑誌の新人賞に投稿して賞を獲ってデビュー、というのが正規の道という認識で。その頃は自分が漫画で食べていく姿なんてまるでイメージできませんでした。
しかしニコさんは、この最初の本の出版を契機に、勤めていた出版社を辞めることを決意する。不安はなかったのだろうか?
ニコ:辞めたいと編集長に伝えたら、「二足の草鞋にしといたらええのに」と言われました。確かに、当時から会社員をやりながら描いている漫画家さんもけっこういましたし、そのほうが安全であることは間違いないですよね。私も一応、ちゃんと連載が決まった段階で辞めたんですけど、収入の面ではめちゃめちゃ不安でした。でも、そこは20代という若さゆえの勢いで、自分の可能性を信じて、えい!っと。
「漫画家」としての転機は、2011年の3月に訪れた。東日本大震災である。幸い、宮城に住むご家族は無事だったものの、この未曾有の天災によってニコさんの実家は津波に流されてしまう。しかし、絶望的な状況を前に、ニコさんはある決意を胸にしていた。「このことは、私が描かなくちゃならない」と。
ニコ:「いま、自分が関心を持っているものを描いて残さなくては」という気持ちが大きかったです。当時、被災した母と祖母は仮設住宅に住んでいて、私も頻繁に帰省して一緒に過ごしていたんですが、この時に被災地の状況やそこでの経験を外に向けて発信することの必要性を強く実感しました。
あの頃って、楽しげなものは全部「不謹慎」と言われてしまい、自粛ムードが蔓延していたじゃないですか。いま思い返してみると、ギャグ要素の強い漫画を描いていた自分としてはやっぱり思うところがあったんでしょうね。被災地であっても人間が生きている以上、面白いことも起これば、日常的に笑いが生まれる瞬間というのはたくさんあります。もちろん、大変な状況であることは間違いありません。でも、それ「だけ」ではない、さまざまな営みがここにはある——このリアルは、まさに今現場にいる私が発信すべきことじゃないのか。そんなことを考えているうちに自然と描き始めていました。
『ナガサレール イエタテール 完全版』ニコ・ニコルソン著(太田出版)
執筆動機はいつも「すげえ!」「みんなに知ってもらいたい」
東日本大震災による避難生活と、失われた生家の再建に至るまでの過程をユーモラスに描いた『ナガサレール イエタテール』は、災害に遭遇した際に役立つ実用的な情報も盛り込まれたエッセイ漫画として大きな注目を集め、漫画家として躍進する大きな契機となった。
こうして「エッセイ漫画家」として確固たる地位を築いたニコさんは、現在でも祖母の介護問題などをテーマにした作品を精力的に発表し続けている。と同時に、近年は『月刊少年マガジン』のWEBコミック配信サイト「月マガ基地」にて連載中の『呪文よ世界を覆せ』ほか、フィクション作品にも果敢に挑戦中だ。
ニコ:エッセイ漫画の描き方しか知らなかったので、ストーリーものに挑戦し始めたばかりの頃は、日々「いったいどうすれば?」の連続でした。でも、ノンフィクションでもフィクションでも、「面白い!」「これは広く世に伝えるべきだ」という気持ちに突き動かされているという意味では、描くうえでの動機やモチベーションの部分はほとんど変わらないんです。
ニュートリノや素粒子物理学をモチーフにした恋愛漫画『アルキメデスのお風呂』は、物理学者の多田将先生の本を読んで「すごい!」と思った気持ちを読者にも伝えたくて描いた作品ですし、崖っぷち芸人が短歌にハマって負け人生を逆転させていく最新作『呪文よ世界を覆せ』も、元は『ネコは言っている、ここで死ぬ定めではないと』という、歌人の穂村弘さんと精神科医の春日武彦さんによる「死」をテーマにした対談本でイラストを担当した時に知った、ある歌をきっかけに描き始めました。それは〈手をのべてあなたとあなたに触れたきに息が足りないこの世の息が〉という河野裕子さんの辞世の歌なんですけど、「たった31文字で、こんなにも人の心を動かしてしまう短歌ってすげえ!」という感動を、やっぱり他の人にも知ってもらいたかったんですよね。
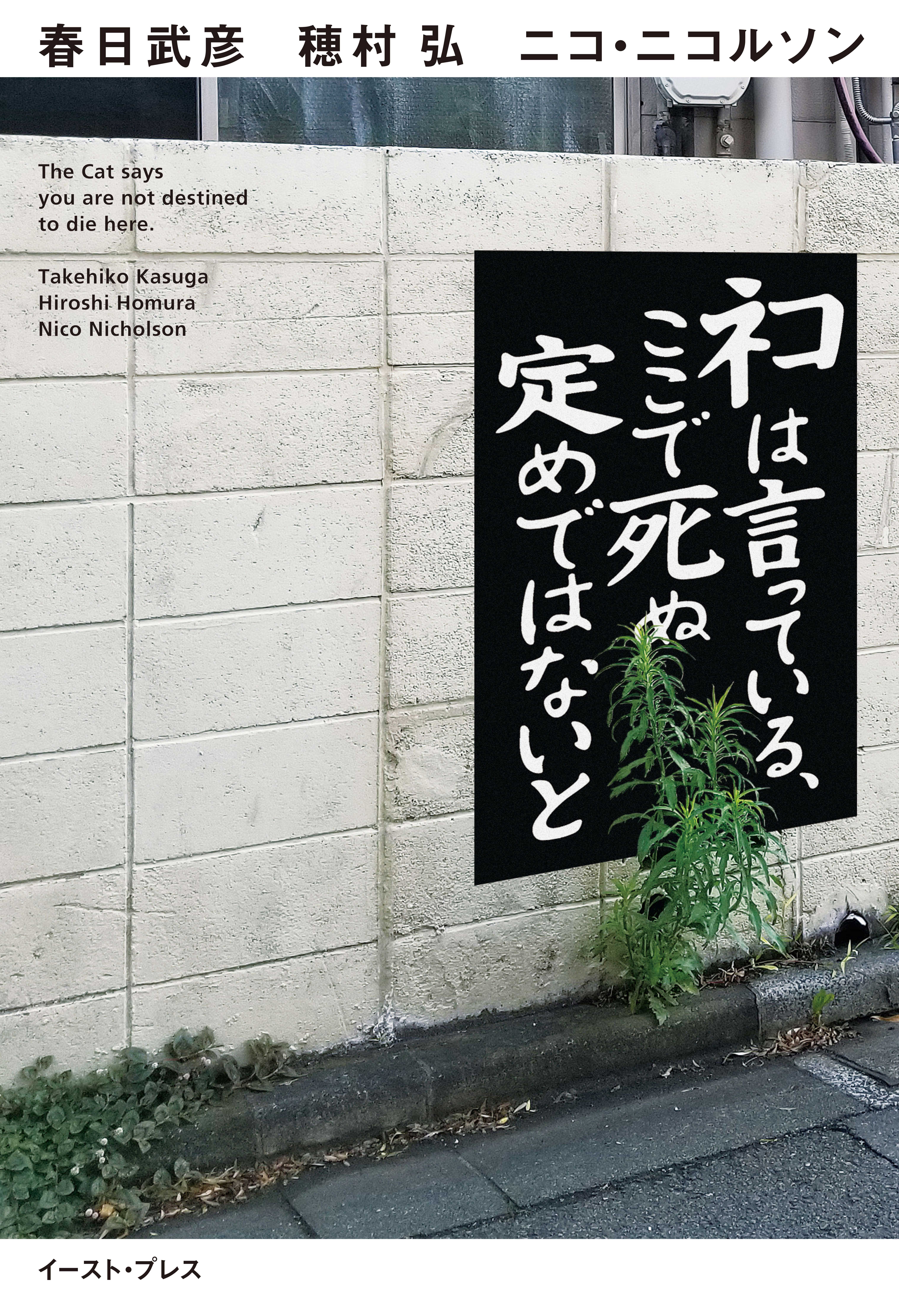
©️春日武彦 / 穂村弘 / ニコ・ニコルソン / イースト・プレス
「気持ち」だけはブレさせない。自分の持ち味を武器にするために
漫画家と一口に言っても、いまは雑誌や単行本をベースに活躍する作家もいれば、ネットやSNSを主戦場とする作家も、あるいは他に仕事を持ちつつマイペースに活動する作家もいる。こうしたスタイルの多様化は、漫画というジャンルへの参入のハードルを下げたという側面もあるが、一方で、苛烈な競争を生んでいることもまた事実。
加えてサブスクリプション、動画コンテンツなどとの競合もあり、ジャンルを横断して可処分時間の奪い合いが起こっている。こうしたコンテンツ過多の時代において、「好きな漫画」「描きたい漫画」にこだわり、創作を続けていくにはどうしたらいいのだろうか。
ニコ:私が強く意識しているのは、「自分が何を人に伝えたいのかを明確にしておく」ということです。自分はこういうものを面白いと思う。この経験はぜひ多くの人と共有したい。そうした創作の原動力となる「気持ち」だけはブレさせない。「伝えたいこと」を常にはっきりと自覚しておけば、迷いが生じても迷子にならず戻ってこられますし、描き続けていくなかで作品も良くなっていくように感じます。
とはいえ、いまはSNSを介して読者の声がダイレクトに飛んできたり、世の中の反応が常に可視化されている時代なので、やはり難しいなと感じることも多いです。例えば、コンプラを意識するあまり萎縮してしまったり、あるいは過度に「バズる」ことを求められてしまったりすることだってあるかもしれませんし。
一番大事なのは「嘘をつかないこと」。『3月のライオン』羽海野チカの教え
ニコ:コンプラについては、「気にしすぎて、描きたいものが描けなくならないようにしてください」と担当編集さんによく言われます。アウトかどうかという判断は編集側がしますので、まずは描きたいように描いてほしいと。
コンプラといえば、かつて認知症を患った祖母の介護生活を描いた『わたしのお婆ちゃん 認知症の祖母とのくらし』を描いていた時に抱いた葛藤を思い出します。この漫画は実話ベースではあるものの、エッセイ漫画という「エンタメ作品」として成立させるために、少なからずデフォルメをする必要がありました。作中、過酷な介護生活で極限状態になった私が、無意識のうちに祖母に手を振り上げてしまう場面が出てきます。振り下ろす直前に、自分のそのとんでもない挙動に気づいて恐れおののくのですが、このシーンは下手に描くと虐待と思われる心配もあり、入れるかどうかかなり悩みました。でも、取材をしたり、実際に自分で体験すると、介護でそこまで追い込まれてしまうことって現実にあるのがわかるんです。好きだから、愛しているからこそ、そこまでいってしまうことが。だから、私はこのシーンを描くという選択をしました。
バズ問題にしても、多くの人に作品を見てもらいたいと思うのは当たり前です。でも、そこから転じて「これだったらウケるんじゃないか」みたいなことばかり考えるようになってしまうと、自分という人間が何を面白がっていたのかがわからなくなってしまうと思うんです。つまり、自分という人間の定規がブレブレになる。それって、表現者としてすごく悲しいことじゃないかな、って。
ニコさんは最後に、かつて漫画家たちの創作の現場を取材した漫画『ニコ・ニコルソンのマンガ道場破り』を連載していた時、『3月のライオン』などの作品で知られる羽海野チカ氏に言われたある言葉を教えてくれた。
ニコ:羽海野先生は、漫画を描く上で一番大事なのは「嘘をつかないこと」だとおっしゃっていました。自分がそれを好きだという気持ちと、漫画にのせる感情に嘘がなければ、どんなテーマで描いても大丈夫ということですね。逆にいえば、そこに嘘があれば、それは読者にバレてしまう。この金言は、漫画を描き続ける上での大事な指針として、強く私の胸に刻みつけられています。
「短歌×お笑い」のコメディ漫画『呪文よ世界を覆せ』を「月マガ基地」にて連載中。©︎ニコ・ニコルソン/講談社






