
感覚と論理を行き来する。デザイン会社LIGHT THE WAYが築いた「なぜ」を問う文化
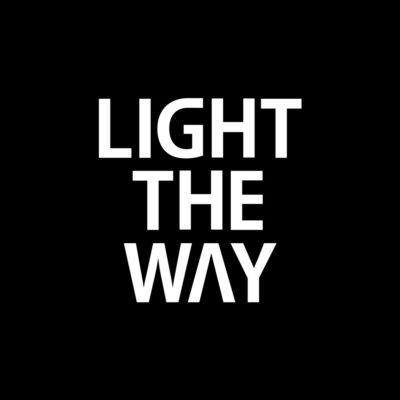
株式会社ライト・ザ・ウェイ(LIGHT THE WAY Inc.)
- 2025.10.20
- FEATURE
PR
映像を軸としたクリエイティブを手がけるデザイン会社LIGHT THE WAY。制作範囲は映像ディレクションをはじめ、アートディレクション、グラフィックデザイン、ウェブ・インターフェースデザイン、企業ブランディングなど多岐にわたる。
2026年で設立から10周年を迎える。LIGHT THE WAYは、社員一人ひとりの「感性」と「言語化できる論理的な思考力」を大切にし、「任せるけれど放任はしない」絶妙な距離感で、チーム全体の成長を丁寧に育んできた。
その成果を、社員たちはどのように感じているのだろうか。ディレクター / デザイナーの白木悠輔さん、山下さくらさん、関矢道大さん、黄珮庭さん、そして代表の西澤岳彦さんに、具体的な手法と成長の実感を聞いた。さらに、個々が目指すこと、LIGHT THE WAYとしての今後の展望も語られた。
- 取材・テキスト:宇治田エリ
- 編集:吉田薫
- 撮影:タケシタトモヒロ
「なんとなく」は通用しない。伝えるための設計思考
―LIGHT THE WAYでは、常に「どうしてこの表現 / 制作をするのか?」を考えることを徹底されているそうですね。感性を言語化することと論理性を特に重要視している理由をおうかがいできますか。
白木:僕たちの仕事は「伝えること」だと思っています。単に派手にすればいいとか、感動させればいいというものではない。例えば、クライアントに「自社の魅力を伝えたい」という課題があったとして、それを届ける最適な方法はなんだろう? と考えて設計し、その伝え方を提案していく。それが僕らの役割なんです。
だからこそ、「なぜその構成にするのか」「なぜこの配色にしたのか」といった問いに、すべて明確な理由を持たせる必要があるんですよね。好みの問題ではなく、あくまでクライアントの目的に対して整合性があるかどうかが重要なんです。

白木悠輔さん。ディレクター / デザイナー。兵庫県生まれ。近畿大学工学部建築学科卒業。2021年、LIGHT THE WAY Inc.入社。
白木:ですから、弊社でつくるものは「なんとなくでつくりました」というような、理由がない表現はNGです。もちろん大前提として、表現の美しさを担保するのは当然のこと。そこにちゃんとデータなり、自分たちの仮説なり、論理の裏付けがあったうえで、1本筋を通して初めてクライアントの課題を解決できる。そこにこそ課題解決の力が宿ると思っています。だからLIGHT THE WAYでは、感性に頼るだけではなく、論理も求められるんです。
―中途で入社された方はその姿勢について、率直にどう思いましたか?
関矢:論理性がここまで重視されるのか、という驚きもありましたが、でも同時に、その姿勢に真摯に応えたいなとも思いました。というのも、論理性を求められることが、自分にとって大きな学びになると感じたからです。
禅問答のように感じるほどではありませんが、常に「なぜそうしたのか?」と問われ続けるから、自分でも答えながら、思考を深めていくことができるんです。もちろん、前職でもレイアウトのことや色のことについてしっかり考えてきたつもりではあったけれど、最終的には感覚で決めていた部分が大きかったんだと入社してから気づかされましたね。

関矢道大さん。ディレクター / デザイナー。新潟県生まれ。TV制作、WEBメディア・広告制作、フリーランスを経て、2024年LIGHT THE WAY Inc.入社。
黄:私はもともと、感覚的に表現するタイプだったので、最初は少し戸惑いました。けれど、論理的に説明することができるようになるにつれ、トレンドに流されず、時間が経っても古びない表現に落とし込めるようになったと実感するようになりました。
これまでの自分の表現は、「そのときはカッコいい」と思っていても、あとから見返すとそうでもなかったり、芯が弱く感じることがあったり。時間が経つとコンセプトが語れなくなることも多くて。
私は5年経っても忘れられないような、長く通用する表現をつくりたくてLIGHT THE WAYに入ったので、まさにいま、その課題にちゃんと向き合えている実感があります。

黄珮庭さん。ディレクター / デザイナー。台湾生まれ。銘伝大学デジタルメディアデザイン学科卒業。台湾でフリーランスとして活動したのち来日し、BtoB映像制作会社を経て、2025年LIGHT THE WAY Inc.入社。
フィードバック文化が、論理的思考や目的意識を鍛える
―思考力を身に付けるために、フィードバックをしっかりすることを大切にされているそうですが、実際にどのように意見を交換しあっているのでしょうか?
白木:フィードバックはプロジェクトごとに、メンバーがリーダーに進捗を確認する形で行っています。頻度は、メンバーの経験値に応じて変えています。
たとえば、完成度100%をゴールとした時に、経験が浅いメンバーに対しては10%ごとに、中途入社のメンバーに対しては、30%ごとに進捗を確認するようにしています。
フィードバックの際は、「クライアントの求めることに合致しているか」「企画の最終的なゴールに向かっているか」「表現の軸がブレていないか」など、問いを投げかけながら確認し、もしズレがある場合は、その都度軌道修正の方向性を伝えるようにしていますね。
山下:入社1年目のとき、ディレクターとして担当した初案件で、あるIT企業の新サービスを紹介するモーショングラフィックスを手がけたのですが、企画からシナリオ構成、社外イラストレーターへの発注まで一貫して関わる中で、白木さんをはじめ、経験豊富なメンバーからたくさんのフィードバックをもらいました。
それこそ最初は、「60%くらいまで形にしてから見せないといけないのかな」と思っていたけれど、実際はもっとこまめに相談できて。進捗に応じて丁寧に見てもらえたことで、安心感がありましたし、自分からも積極的にフィードバックをもらいにいけるようになったと思います。

山下さくらさん。ディレクター / デザイナー。千葉県生まれ。東京工芸大学芸術学部デザイン学科卒業。2024年LIGHT THE WAY Inc.入社。
関矢:LIGHT THE WAYの良さは、フィードバックが一方的な指示やダメ出しではなく、「どうしてこうしたの?」と問われるところだと思います。常に会話の延長として思考を問われ、考える。その繰り返しがまさに「問答」なんですよね。
続けるうちに自然と筋道の通った考え方が身についていくし、言語化する力も育っていくのだなと思います。
山下:そうですね。デザインに対するフィードバックだけでなく、クライアントとのコミュニケーションにまでフィードバックがあるのも、ありがたいと思っています。
関矢:その最たる例が、入社して間もない頃に「メールの文面は必ずチェックしてもらう」という文化ですよね。相手に伝わりやすい順番や、要点をどう配置するかまで細かく見てもらえて、対外的にどんな印象を与えるかという意識も自然と身についていきました。
西澤:「クリエイティブに向かう道を切り拓く」というコーポレートスローガンを、個々のメンバーが体現していくためには、クライアントから「LIGHT THE WAYの◯◯さんにお仕事をお願いしたい」と言ってもらえるようになる必要があると考えていて。そういう意味で、その個々の個性を「見える化」し、社会とつなげるコミュニケーションを心がけています。

西澤岳彦さん。CEO / ディレクター / アートディレクター。埼玉県生まれ。多摩美術大学情報デザイン学科卒業。2016年LIGHT THE WAY Inc. 設立
―映像勉強会もLIGHT THE WAYで長年続いている文化です。そのような取り組みも、思考力を鍛えることにつながっているのでしょうか?
関矢:そうだと思います。月に1回、各自がいいと思う映像を持ち寄って、その理由を言語化しながら発表するんです。それもまた、日頃の仕事のアウトプットにもいい影響が出ているなと感じます。
西澤:映像勉強会では、1年に少なくとも100本のペースで映像を見ているんです。この会で大事にしているのは、「いま、世の中で良しとされている表現は何か?」「何が人の心を動かすのか?」という視点を持つこと。そこから社会的価値と表現的価値の両面を理解し、共通認識を持てるようになると思いますし、判断力も磨かれると考えています。
―フィードバック文化を通して、感じた成長はありますか?
関矢:一番感じるのは「俯瞰で見る癖がついた」ことですね。制作に集中していると、つい視野が狭くなりがちですが、フィードバックを受けることで客観的な視点がリセットされて、「これは本当に伝わるか?」「見る人にどう映るか?」と冷静に考え直せるようになりました。結果的に、同じ失敗を繰り返さなくなるし、次に活かす力が身についているなと実感します。

任せるけれど、放任しない距離感を大切に
―プロジェクトを進めるうえで、どのようなことを大切にしていますか?
西澤:仕事を自分ごととして考えてもらうために、積極的に裁量を与えて任せるようにしています。でも、決して放任はしません。その距離感が、メンバーが安心して仕事に向き合える環境につながると思っているので、このスタンスを大切にしています。
関矢:自由度が高いけれど、もし軌道からはずれそうになったらしっかり手綱を握り直して軌道修正してくれるんですよね。
黄:責任を持つからこそ、クライアントがどんな会社で、これまでにどういうものをつくってきたのか、しっかり調べて理解したうえで、企画を提案しようという意識になりました。

―いま、メンバーの大きな成長につながっていると感じるプロジェクトはありますか?
西澤:たとえばNHKで現在放送されているこども向けニュース番組『週刊情報チャージ!チルシル』は、特にチャレンジングな内容です。毎週生放送の番組内の特集コーナーをインフォグラフィックスでつくるというもので、全社員が一丸となって取り組んでいます。
白木:このプロジェクトは、毎週必ず納品するスピード感が求められるため、社外パートナーとも連携しながら、1話ごとに4~5名ほどのチームを編成して進行しています。
番組の世界観やブランディングの初期提案、情報を効果的に伝えるためのインフォグラフィックスのルールづくりといった基盤設計も、弊社が関わらせていただきました。グラフィックのトーン&マナーやモーションの動き、スライドのテンション感など、細かいレギュレーションを整えることで、外部パートナーとも足並みを揃えています。タイトな制作スケジュールの中でも、少しでも魅力的なコンテンツを届けられるよう日々チャレンジしているプロジェクトです。
未来を担うこどもたちに向けて、わかりやすく、見ていて楽しいインフォグラフィックスを届けられることに、大きなやりがいを感じています。
―実際の進行は、どのように行っているのでしょうか?
白木:番組内容の取材と構成はNHKさんが担当し、LIGHT THE WAY側のディレクターが「どういうインフォグラフィックスで、どのように情報を伝えるのが効果的か」を提案し、方向性を固めてから制作を進めていきます。発注から納品までは、概ね3週間程度のスケジュールです。
―インフォグラフィックスとモーショングラフィックス、両方のディレクションが求められるのですね。タイトなスケジュールの中でアイデアを考え形にしていくことに、どのような難しさ、面白さを感じていますか?
白木:難しさはもちろんありますが、「どうすればよりわかりやすくなるか」を考えるプロセスに、この仕事の面白さが詰まっていると感じます。
関矢:情報をわかりやすく伝えるには、本質を掴む力が必要で、日々の勉強も欠かせません。また、ぱっと見はシンプルに見える表現でも、グラフィックの配置ひとつとっても「どう並べたら見やすいか」を細部まで検討する必要があります。難しいですが、それがきちんと形にできたときの達成感は大きいです。
―この案件を通して、どんな力が身についたと思いますか?
白木:クライアントと同席して、その場で「今回はこう進めていきましょう」と方向性を即決する場面も多いので、即断即決力はかなり鍛えられました。さらに、限られたスケジュールの中でロスをなるべくなくそうとするとき、「作り始めてから気づく」のでは遅い。事前に伝えるべきことをしっかり言語化して、先に共有しておくことの重要性を実感しました。解像度の高い思考力や質問力も、確実に身についてきていると感じます。
黄:私は今回のプロジェクトを通して、フィードバックを受ける側から伝える側へと変わった感覚があります。これまでは指示をもらう立場でしたが、NHK案件では自分がデザイナーに指示を出す立場になる場面が増えています。そのときに実感したのが、「なんとなく」の指示では伝わらないということです。
たとえば「テキストのサイズを何%拡大してください」といった、具体的な数値で指示するよう心がけています。自分自身が指示を受ける立場だった頃の経験を思い返し、「こう言われたら動きやすいよな」という感覚をディレクションに活かせている気がします。まだまだ「わかりやすく伝える力」は発展途上ですが、その分ひとつひとつが大きな学びになっていますね。
LIGHT THE WAYでキャリアを重ね、どこでも通用する力を身につける
―LIGHT THE WAYで得てきた思考力は、ご自身のキャリアにどのように役立つと思いますか?
白木:「考える力」は、どんな職業でも役立つと思っていて。たとえば、相手の行動を先読みして提案したり、コミュニケーションを円滑に進めたりするときにも活かされる力です。そういう思考力がある人は、どんな案件でも、どんな環境でも重宝されるんじゃないかと思うんです。
特に弊社では、クライアントの課題を見つけるところから始まり、解決策を提案し、成果につなげるところまで一貫して担う必要があります。いろんな分野の人たちとやりとりをしながら、ひとつのストーリーを組み立てていく。その過程そのものが自分を成長させてくれるし、キャリアの後押しになっているのを実感します。

関矢:今の時代は、若いうちから映像編集や制作に触れている人が多くて、動画業界の裾野が広がっているのはいいことだと思っています。一方で、能力の差もどんどん広がっているように感じていて。なんとなくつくっていても、それなりに食べていけてしまう時代だからこそ、差別化のためには「しっかり考えてつくる」ことがとても大切だと思うんです。
そうして考え抜いてつくったものは、クライアントにも喜ばれるし、自分の自信にもつながる。これまで映像制作に携わってきた経験があるからこそ、LIGHT THE WAYなら今後AIが進化していく中でも、生き残るための根幹を養えると感じています。
山下:私はようやく2年目に入ったばかりなので、まだキャリアの重ね方までは考えられているわけではありません。ただ、最終的なアウトプットを良くするためには、やはり「考える力」を身につけることが一番重要だと思うので、そこを意識しながら、社内外の人たちとのコミュニケーションを積極的に深めていきたいですね。

―LIGHT THE WAYは、2026年に設立から10周年を迎えます。最後に、会社として今後チャレンジしていきたいことを教えてください。
西澤:この10年間、やっていることはずいぶん変わってきました。これからも、メンバーがやりたいと思う仕事をきちんと取り入れていけば、さらに進化していくと思います。その中でも、「映像を軸にしている」という点だけは変わらないでしょう。
会社として進化していくためには、単に「映像をつくる会社」ではなく、コミュニケーション全体の設計にまで関わっていくことが欠かせません。エモーションとロジック、アートとデザイン、戦略と実装。その間を行き来しながら、クライアントの目的に本質から向き合う。そして、どのメンバーもジェネラリストとして、「なぜLIGHT THE WAYなのか?」を胸を張って語れる組織でありたいと思っています。それこそが、他社にはない私たちの強みになるはずです。
今後は、自社発信のプロジェクトにももっと力を入れていきたいです。いま、社内でオリジナルのショートストーリー制作に挑戦しています。社員にとってそれが大きなスキルアップの機会にもなるし、自分たちの表現力を社会に向けて発信するきっかけにもなる。好きなこと・得意なことを起点にしつつも、最終的には仕事として還元されていくような取り組みをこれからも積み重ねていきたいと考えています。

Profile

LIGHT THE WAYは映像を軸としたクリエイティブのデザイン会社です。映像ディレクション、アートディレクション、グラフィックデザイン、WEBデザイン、インターフェースデザイン、CI・BI・VIなどクリエイティブによって新たな価値を社会に生み出し、事業の進むべき道筋を照らし出します。
「クリエイティブ」という曖昧な言葉が指し示すのは、必ずしもその「成果物」に限りません。あなたがどこに立ち、どこへ向かうのか。そこにある障壁はなにか。選択する最良の方法はなにであるべきか。制作者の視点から課題を探り当て、ゴールへと向かう指針を指し示すこと。LIGHT THE WAYはその一連のプロセスや現象をつくり出すことが「クリエイティブ」であると信じています。まだ見たことのない景色に向かって、新たな道をともに歩みましょう。
〈応募を検討されている方へ〉
1人で活躍できるプロフェッショナルが、1人では到達できない場所を目指して集まる。LIGHT THE WAYが目指すのは、そんな独立した制作者の集団です。
LIGHT THE WAYは小さな組織です。そのため、あなたの存在が大きな力になり、会社の今後をつくります。スキルがあれば業界での経験は必須ではありません。好奇心と向上心は必要です。興味をお持ちいただいた方は、まずはお気軽にご連絡ください。
LIGHT THE WAYでは定期的に「私たちの声」というコラムを発信しています。会社の雰囲気や働く様子、制作への姿勢など、コラムを通じて私たちをより深く知ることができますので、ぜひご覧ください。
私たちの声はこちら
https://light-the-way.jp/column
さらに制作実績をご覧になりたい方はこちら
https://light-the-way.jp/works

