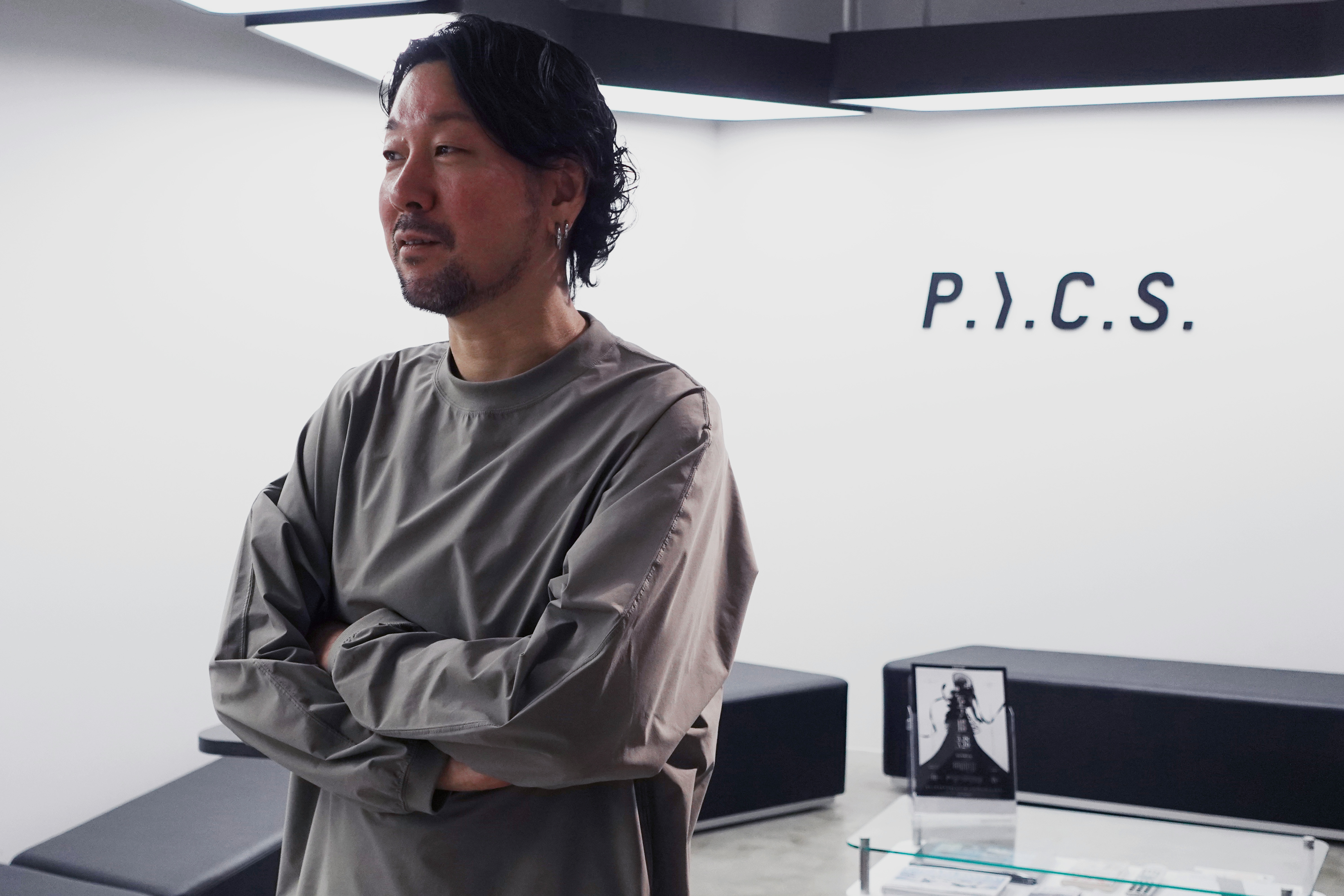King GnuやMILLENNIUM PARADEのミュージックビデオ、テレビアニメ『オッドタクシー』のオープニングなど、印象的な手描きアニメーションで注目を集めてきた山田遼志さん。現在は、立ち上げメンバーとして参加したクリエイティブハウスmimoidで、アニメーション作家のみならず映像ディレクターとしても活躍している。
そんな彼が、2025年7月24日から30日に原宿JOINT AROUND the CORNERで開催されている初個展『CITYNESS - LaLaLa, BROTHERS -』で、アニメーション以外の平面・立体作品を発表する。「アニメーションではできない、潔いものをつくりたかった」と語る山田さんは、作家性とキャリア、そして音楽やクラブカルチャーに親しんできた自身の背景を、どのように作品へと昇華させるのか。
連載「映像クリエイターファイル」vol.3では、個展会場で、山田さんのこれまでの軌跡をたどりながら、作家としての原点と未来について語ってもらった。
- 取材・テキスト:宇治田エリ
- 撮影:坂口愛弥(TABUN)
- 編集:吉田薫
「違和感」を表現する。学生時代に自覚したやりたいこと
―山田さんは多摩美術大学で修士課程まで学ばれていました。学生時代はどのような作品をつくっていましたか?
山田:初めは画家志望で、絵を描いていたんですよ。でもファインアート系の人たちの画力に圧倒されて、コンテンポラリーアートで勝負するのは難しいと感じて。絵と同時期に勉強していたアニメーションは、完成までの道のりが複雑で、ハードルが高い。でもむしろそこに魅力を感じて、アニメーション制作にのめり込むようになりました。
現在の手描きアニメーションのスタイルは、大学3、4年の頃にすでに確立されつつありましたね。作品でやりたいことも、その時点でかなり明確になっていて、作家として生きていこうと決意して大学院に進学しました。

山田遼志 アニメーション作家 / 映像ディレクター
1987年生まれ。東京在住。多摩美術大学大学院グラフィックデザイン専攻修了。株式会社ガレージフィルムでアニメーターとして勤務後、2017年にフリー。文化庁芸術家海外研修員としてドイツに留学。2020年にクリエイティブハウスmimoid立ち上げに参加。手描きアニメーションを中心にコマーシャルやミュージックビデオ、イラストレーションなどを手掛ける。現代社会の抱える不安や恐怖などをモチーフとし、狂気的で風刺的な作風が持ち味。自主作品は国内外でも高く評価されており、数多くの国際映画祭で受賞、上映歴がある。代表作にKingGnu「PrayerX」、Millenium Parade「Philip」、「Hunter」など
―「作品でやりたいこと」とは、どのようなことですか?
山田:「違和感」をどう表現するか、が軸としてありましたね。学校のルールなどに感じていた全体主義的なものへの反発心もありましたし、親がポーランドの歴史学者で、ホロコーストやナチスの話題に幼い頃から触れていたことも影響しています。
それをさらに掘り下げていくと、ソ連の社会主義統治や宗教弾圧といった東ヨーロッパの構造などが、自分が感じている「違和感」の根底にあると気づいて、それらを自分の作品に落とし込むようになりました。
「自分の絵だけでは食えない」CM制作現場で学んだこと
―大学院修了後、すぐに作家になるのではなく、映像制作会社に就職されています。
山田:社会に出たら作家活動を続けていこう思っていたけれど、大学院の1年目の終わりに「このままじゃ食っていけないな」と気づいて。まずいと思って就職活動を始めたんです。そんな時に拾ってくれたのが、ガレージフィルムでした。

個展『CITYNESS – LaLaLa, BROTHERS -』 7月24日から30日まで原宿のJOINT AROUND The CORNERで開催中
―そこではどのような仕事をされていましたか?
山田:主にCMアニメーションの制作を担当していましたね。就職する前は「アニメーションならなんでもできます」と自信満々だったけれど、実際に働き始めたら、我流でやってきた分、編集ソフトの使い方すらわからない。
しかも入社早々に手を骨折してしまって、本当に使いものにならなかったんです(笑) 。
―会社での経験は、その後の活動にどのような影響を与えましたか?
山田:良かったところは、どんなアニメーションでもつくれる力がついたことです。それこそ就職活動の面接などで、「君の絵ではお金にならない」と言われ、仕事を続けていくには、どんな絵でも描けるスキルや、他人の絵を使ってでも仕上げられる対応力が必要だと教えられて。そのうえで、ワークフローを構築する力や実務的なスキルも学ばせてもらいました。プロのアニメーターとして活動するための地力を培えたと思っています。
―入社当初から独立を見据えていたと思いますが、自主制作はされていましたか?
山田:当初はとにかく余裕がなくて、昼はがむしゃらに働き、夜はクラブイベントでVJをして憂さ晴らしする日々でした。でも、「自分の作品で勝負したい」という気持ちはずっとあったので、2017年に『Hunter』という短編に着手し、作品を完成させるために退職を決断しました。
作家として独立するために。留学と制作のチャンスを掴んだ
―その後、2018年には文化庁の研修制度でドイツへ留学されています。目的は?
山田:作家としてキャリアの土台を築くためにも、海外へ行きたいという気持ちが強かったんです。それが退職した理由のひとつでもありました。当時28歳でやるなら今しかないと思い、『Hunter』をさまざまな国際映画祭に出品したところ、『アヌシー国際アニメーション映画祭』への入選がきっかけとなり、ドイツのフィルムアカデミーに1年間留学することが決まりました。
―ドイツではどのような学びがありましたか?
山田:ドイツのアニメ界を代表するアンドレアス・ヒュカーデ(Andreas Hykade)氏に師事できたのは大きかったです。僕はエンタメよりも「わかりにくいもの」「考えさせるもの」をつくりたかったので、ようやく師匠と呼べる存在に出会えたという感覚でした。
彼の作品は、短い尺でもエモーショナルかつダイナミックに、カッコよくできるかということを考えたうえで仕上げられていて、そうした映画的な思考や演出技法がとても勉強になりました。しかも、第二言語で学ぶという環境が、自分の思考を根本から問い直すきっかけになったんです。
日本にいると、つい難解な言葉で考え込んでしまう癖があったのですが、ドイツでは中学生レベルの語彙で演出を伝えなければならない。その制限のなかで、自分のやりたいことが解体され、自分の演出の根本を見つめ直すことができました。

―留学と同時期に、King Gnuの“Prayer X”(2018)のミュージックビデオが発表されています。そちらも大きな転機となったのではないでしょうか?
山田:そうですね。ちょうどドイツへ行く直前に、もともと友人だったKing Gnuからオファーをもらって、ミュージックビデオを制作しました。
『BANANA FISH』というアニメのエンディング曲だったのですが、40年前の人気漫画、複雑で斬新な音楽、手描きアニメーションという3つの要素のいびつな掛け合わせが、逆に跳ねたんだと思います。それで彼らからも「帰ってきてくれよ」と声をかけてもらって。ドイツに残って作家活動をすることも考えていたけれど、日本のほうが面白そうだなと思って帰国しました。そこからPERIMETRONとのつながりも生まれていきました。
無意識をすくい上げ、中二病を超え、誰かに届く作品へと昇華させる
―2020年にはmimoidを設立され、現在は映像ディレクターとして活躍の幅を広げています。ご自身のアニメーション制作に変化や発見はありましたか?
山田:特にミュージックビデオをつくる時は、ドイツで学んだことを応用しながら、「どうやって複雑なストーリーを短い尺に収めるか」「観た人にモヤモヤや悪夢的な感覚をどう与えるか」を意識的に考えてつくるようになりました。
ボーカルが入っていない音源が届いた場合は、自分のアイデアストックから形になっていない企画を当てはめてみたりしながら打ち合わせを重ね、内容を固めていきます。楽曲を聴いて最初に感じたイメージは、散文詩のようなかたちで描き出し、無意識下で起きた反応を言語化・視覚化していきます。それから最初はバラバラな断片でしかなかったイメージを削ぎ落とし、100カットほどを試作。カットの順番を入れ替えたり、新しいカットを追加したりしながら、自分との対話を重ねて形にしていくんです。
だからこそ、制作終盤になって「自分はこの曲で何を伝えたかったのか」がようやく見えてくることもありますし、「この曲って、もしかしたらこういうことだったのかも」と気づかされることもあります。

―完成前に見えてくるものも多いということですね。
山田:そうですね。もちろん、仕事なのでメッセージやコンセプトは企画段階である程度固めますが、「この主人公は何を象徴しているのか」や「ストーリーの本質は何なのか」ということは、つくりながら徐々に発見していくことが多いです。
例えばMILLENNIUM PARADEの“Philip”(2020)や“Trepanation”(2021)はそういうつくり方で、発見も多い作品でした。“Trepanation”も、ギリギリまで完成イメージが固まりきっていなくて、結局これは誰なんだという議論をしていたら、制作チームが「こういうことなんじゃないですか」と解釈してくれて、ようやく腑に落ちたということもありました。
―上記のような作品には、常にひりつくような緊張感が漂っていて、それが自分の内にある違和感を掘り起こしていくような感覚があります。
山田:まさにそれを目指しています。「好き」で終わる作品よりも、観た人にモヤモヤしてほしい。そう簡単には消費されないものである必要があると思ってつくっています。ミヒャエル・エンデの作品なんかが典型的ですよね。児童向けのようでいて、大人になっても何度も読み返したくなる奥深さがある。そんな作品が理想です。
―作品が世の中に与えている影響について、どのように感じていますか?
山田:社会全体に影響を与えているとは言えないけれど、若い人と話したり、DMをもらったりする中で、思春期で苦しんでいる人たちが僕の映像に触れて少しでも楽になってくれているのかな、という印象はあります。
僕自身も、映像や音楽に救われた経験があります。「自分は自分でいい」と思えた瞬間があったからこそ、今度は自分がそんなきっかけを届けられたらいいな、という気持ちでつくっていますね。
―作品をつくり続ける中で、ご自身の中に変化の兆しはありますか?
山田:大学に入学した頃は「自分は天才だ」と本気で思っていたし、社会に出る時も「アニメーションなら何でもできる」と過信していました。その中二病的な感覚は今もどこかにあって、きっとこれからも完全には抜けない。でも、最近はだいぶその閉鎖的な考え方も薄れてきたというか。もう少し子どもでも見られるような、だけど一筋縄ではいかない、よくわからないけど後味が残る作品をつくりたいと思うようになっていますね。
潔さに向き合った展示『CITYNESS – LaLaLa, BROTHERS -』
―7月24日から初の個展が開催されます。どのようなコンセプトですか?
山田:タイトルの『CITYNESS』は「都市に生きるものの性質、またはその状態」という意味です。自分が影響を受けたロックやクラブカルチャー、ビートニクなどには、CITYNESSの様相があると思っています。そういったものたちには「潔さ」がある。
アニメーションは、制作過程が複雑で、自分的には潔くないワークフローを必要とした表現メディアだと思っているんですね。でも、完成したものは潔く見えるという不思議さがあって。その矛盾をイチから掘り起こしてみたいと思って、キャンバスやドローイング、立体作品に挑戦しました。

―映像と、絵画や立体の違いはどこにあると思いますか?
山田:たとえば、絵を描くときに一本の線を間違えて引いてしまったとします。でも、それを消すのではなく、その線を活かす方向で構成を決めていく。この意思決定の潔さが画面に定着していく感覚が絵画にはあって、それがすごく好きなんです。もちろんアニメーションでもそういうことは可能ですが、すでに多くの人がやってきた方法論でもあり、個人的にはキャンバスでやるほうがしっくりきます。
それから液晶タブレットなどの便利な道具が主流になった今こそ、あえて不便な支持体でやってみたいという思いもありました。制作環境がどんどん快適になると、考えなくてよいことが増えていく。それによって、考えることそのものが抜け落ちてしまう感じがあったんですよね。あまのじゃくかもしれないけれど、キャリアを重ねた今だからこそ、そうやって抜け落ちていく感覚を拾い直したいと思ったんです。
―絵画など大きな作品をつくるときは、身体性との関係も明確に見えてくると思います。制作しながら発見はありましたか?
山田:そうですね。大きい作品をつくっていると、体力的にも疲れるし、コマンドZ(やり直し)もできない。だけど、できないことが逆に「最高だな」と思える瞬間が多いですね。思い通りにならないことが、むしろ刺激になるんですよ。常に「今この瞬間どうするか」という意思決定を迫られている感じがあります。
―展示のサブタイトルにある「- LaLaLa, BROTHERS -」とは?
山田:作品の中で頻繁に使用しているキャラクターで、イマジナリーフレンド的な存在ですね。自分は昔から悩みがちなタイプで、そういう時に「別にいいじゃん、そのままでさ」と言ってくれるような、潔い存在なんです。
そんな彼らは、スーツに象徴されているように、社会の歯車にしっかりと噛み合える無個性を受け入れながら、昭和のサラリーマンのように満員電車で通勤して、家庭では疎まれながらも日々を過ごしている。その姿に対して僕は、否定ではなく「すごさ」を感じるんです。彼らは個性を消せる潔さも持ち合わせている。
また、自分はよく「人の不幸で飯を食う」ようなジャーナリストを題材にするのですが、そういう人たちにも潔さがあると思っています。人間がだんだん悪人になっていく様子を描くときにも、「それが良い・悪い」ではなく、一貫した潔さとして捉えているんですよね。

―善悪を決めない視点が独特で面白いです。
山田:善悪って、状況によって変わるものだと思うんです。もちろん、殺人や暴力はいけない。でも、それすらも一概に語れないケースがある。人はときに矛盾した行動をとるし、そのたびに悩む。その構造そのものにこそ、人の本質があるような気がしています。
もちろんそれがハンナ・アーレントのナチス研究のようにアイヒマンのような犯罪者を生んでしまうケースもあるので、常に受け入れながら、俯瞰した態度を取る必要があると思います。また映画のジョーカーのように、隣人を失うことが本人の理性をも失うことにもつながるので、その複雑な構造を理解した上で、我々の持ってるモヤモヤなどをお互いに言い合えるような世の中になってほしいなと思います。
―最後に、今後の展望についてお聞かせください。
山田:今はアニメーションの短編が完成しており、その発表の準備をしています。それから、今回の展示も実は3部作で考えていて、今回が第1章。第2章はアニメーションがメインのインスタレーション展示、そして第3章は1、2章を融合させたCITYNESSを乗り越えるような、アニメーションやインスタレーション、絵画の包括的な展示を考えています。
また、今回の展示にあわせてアパレルブランドの立ち上げも行いました。こちらも軌道に乗ってくれるとうれしいですね。ちょうど今、大学時代から20年近く温めてきたことを一気に放出しているような時期なので、これからもガツガツやっていきたいと思います。

山田:展示は、良い意味で展示っぽくないものになっているはずです。僕のアニメーションのアイデアの種みたいなものが見られる場になると思うので、7月30日のクロージングイベント含め、ぜひ気軽に遊びにきてください!