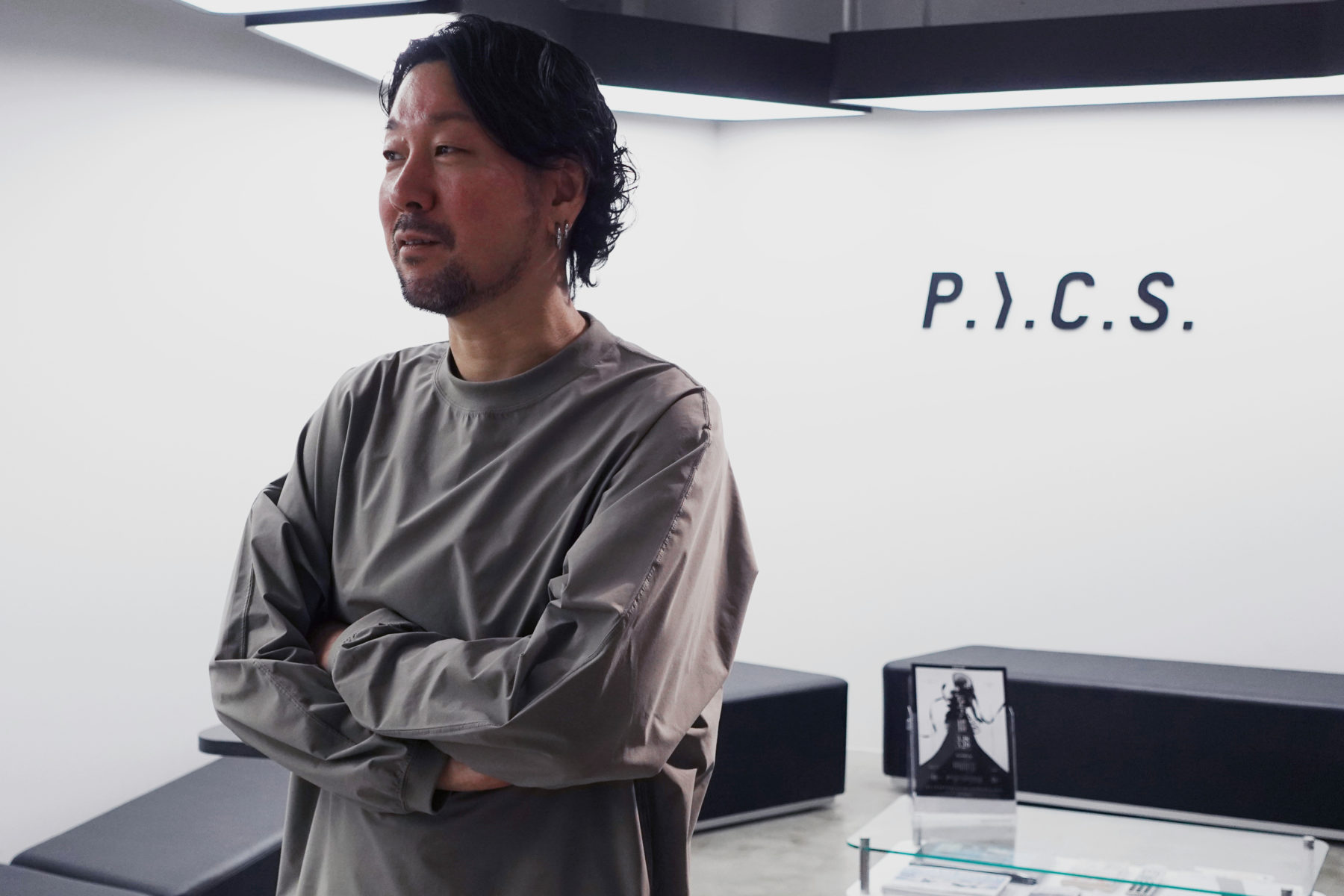
ビジュアルコミュニケーションの需要の増加とともに、映像表現もどんどん変化を続けている。新連載「映像クリエイターファイル」では、そんな変わりゆく映像表現の現場で活躍するクリエイターにインタビューを実施。クリエイターの表現の背景にある思いや考えからキャリアまで深ぼることで、映像表現の現在地を知るとともにクリエイターのキャリア形成の一助となることを目指す。
第一回に登場いただくのは、櫻坂46の“UDAGAWA GENERATION”や、自主制作作品『畏 - OSORE -』など多様な映像表現を手がける映像ディレクター・池田一真氏。広告からMV、そしてアニメから実写映画まで、ジャンルにも手法にもとらわれず作品を生み出す池田氏が、大切にしているのは「視聴者が喜ぶ映像を作ること」だという。
本インタビューでは、近作“UDAGAWA GENERATION”の制作背景や、コンセプトの生み出し方、これまでの歩みまでを語ってもらった。
※取材は2月に実施
- 取材・テキスト・編集:吉田薫
Profile
池田一真いけだ かずま
企画 / 演出。アイデアやユーモアに溢れた映像表現を得意とし、手法にとらわれない柔軟なディレクションで、TVCMから企業ブランディング映像、MV、アニメーションコンテンツやアトラクション用の空間映像まで、多岐に渡る媒体やジャンルを手がける。
https://www.pics.tokyo/member/kazuma-ikeda/
櫻坂の強みと新しさを見せたかった
—直近の作品は、“UDAGAWA GENERATION”が最新作になりますか?
池田:そうですね、直近で公開されたのは“UDAGAWA GENERATION”になります。
—本作は、遊び心あふれる内容になっていますね。ご自身としてもチャレンジングな作品だったとおっしゃっていましたが、コンセプトはどのように決めたのですか?
池田:最初にスタッフの方と打ち合わせをして、「今までの雰囲気とは違う、新しい櫻坂46を見せたい」という話がありました。欅坂の頃から関わっているので、「クールでシリアスなダンスチューン」という固定観念が私のなかにもありましたし、そういうものが求められているのではとも思ったのですが、今回は新しい見せ方をしようとアクセルを踏んだ感じです。
今回のMVでは、劇場やステージのような演出空間を作り、アイドルが観客に向けて全力でパフォーマンスをするも、空回りしてしまう――そんなストーリーにすることで、アイドルならではの努力や成長を描きたかったんです。
どんなことをしようかかなり迷いましたが、彼女たちの強みはダンスで魅せるパフォーマンスだと思っていたので、その軸はやっぱブレさせたくない。 そこでダンスを軸にしつつ、これまでとは違うテイスト――喜劇みたいだったり道化みたいだったりする動きを積極的に取り入れたいという話を(振付師の)TAKAHIROさんとしながら、作りこんでいきました。
新しさを見せつつ彼女たちらしさも表現したいと思っていたので、SNSのトレンドに「櫻坂らしさ」がランクインしていて嬉しかったですね。
—ファンにもしっかり伝わったのですね。本作はワンカットで撮られていると思うのですが、特に大変だったことは何ですか?
池田:ダンスの練習は個別でメンバーたちがやってるんですけど、カメラと仕掛けを合わせての全体的なリハーサルを別日で組むスケジュールはなかったので、撮影の日の半日使って綿密に計算をしながら、全員でどういうふうに動いたらどう撮れるかを話しあいながら作りました。それが少し大変でした。
今回は、ストーリーやコンセプトが「必死で練習をしている」というところにもあったので、ある程度のワンカットならではのほころびとかも込みで演出しました。
制作以上にコンセプトを大切にする理由
—そういったコンセプトをベースにした撮影方法はどうやって考え決めているのでしょうか?
池田:曲を聴きながらいろんな作品を見たり、画像を集めたり、リサーチしながら考えることが多いですね。曲を聞きながらさまざまな視覚的なインプットを重ねているうちに、「こういうコンセプトだと面白いかな」というアイデアが浮かぶのを待つんです。ただ、この時間が一番苦しいですね。全然楽しくないです(笑)。
私の場合は、自分で何をやりたいというのが、はっきり決まってないと映像を作れないんです。広告の場合は伝えたいメッセージが割とはっきりしているのでまた別ですが、MVの場合は自由度が高い分、何でもできてしまいますよね。だから、スタート地点の企画やコンセプトを自分の中でしっかり作ることが大事だと思っています。
演出が過剰になってしまったとしても、企画 / コンセプトが明快であれば「これはやりすぎだ」とか、反対に「もう少しやったほうがいい」というような判断がクリアにできるので。
—準備段階を何より大切にされているんですね。
池田:そうですね、準備はすごく大事です。逆に言うと、映像の制作方法にはこだわりがないですね。モーショングラフィックからCG、アニメ、実写まで何でもやります。「自分の技はこれだ」みたいなこだわりを持たないのが、ある意味こだわりかもしれないです。
人を美しく撮るため必要な距離感
—コレオグラファーのSeishiroさんと自主制作的に作られた『畏 – OSORE -』についてもおうかがいしたいです。受託の仕事とは制作過程が異なる部分が多かったそうですね。
池田:そうですね。この作品においてSeishiroさんとは、映像ディレクターと振付師というふうに役割を分けず、お互いにアイデアを出しあいながら作っています。彼は作品を作りながら答えを見つけていくタイプで、僕は最初に答えを決めてから肉付けしていくタイプ。『畏 – OSORE -』では、Seishiroさんの制作スタイルを軸に、最初から明確なストーリーを決めず、セッションのように作りあげていきました。
—ホラーのような恐ろしさと、人体の美しさが幻想的でした。
池田:ありがとうございます。ホラーと美しさ、そして生々しさを融合させることを目指していたので、嬉しいです。Seishiroさんと好きな要素をテーブルに並べながら、撮影の中で試行錯誤していきました。
—池田さんは「人」を美しく撮られますよね。人にフォーカスして撮るときに、特に意識されていることはあります?
池田:作品の目的や企画によりますが、MVではアーティスト自身が楽曲をアウトプットする存在なので、あまり細かい演技指導はしません。舞台としてのシチュエーションや世界観は固めますが、その中でどう表現するかはできるだけ本人たちに委ねるようにしています。だから、キャラクターや表情の細かい指示はほとんどしないですね。
—そういった撮影はアーティストに寄り添う感覚が必要になりそうですが、どうやって培われたのでしょう?
池田:じつはあまりパーソナルな部分は深掘りしないんです。例えば、櫻坂のメンバーについても、冠番組やSNS、ブログなどはあまりチェックしません。撮影の場に立てば、彼女たちの表現や空気感を直接感じ取ることができますし、それだけで十分だと思っています。
むしろ、事前に情報を入れすぎると先入観が生まれてしまい、フラットな視点で撮れなくなってしまうんですよね。
選り好みせずなんでもやる精神が、いまのキャリアをつくった
—池田さんのキャリアについてもおうかがいしたいです。池田さんが、映像ディレクターを志したきっかけを教えてください。
池田:映像を作りたいと思ったきっかけは、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』を見て面白そうだと思ったことですね。
—映画からの影響だったんですね。
池田:そうですね。中学生の頃だったと思いますが、漠然と映像を作りたいという気持ちが芽生えて、当時は何をすればそうなれるのかも全然わかっていませんでした。それで、CGの世界に興味を持ったんです。CGって、監督も美術も役者も、すべて自分でできるじゃないですか。これなら美味しいとこ取りだと思って、全部やりたくて、CGの勉強を始めました。
専門学校で簡単なPhotoshopとかAfter Effects、少しだけ3DCGを学んで。その後、19歳のときに最初の会社にバイトとして出入りし始めて、本格的に映像制作に携わるようになりました。
—その会社ではどのような仕事をされていたのでしょうか?
池田:最初の仕事は、音楽番組のオープニング映像やモーショングラフィックを作っていたましたね。スペースシャワーTVやM-ON! TV、CSの番組などの映像を作りました。あと、地上波のバラエティ番組のオープニング映像も手がけていました。
会社が大きくなかったので、コンテを書いたり、CGの制作を担当したり……基本的になんでもやりました。テレビ番組のディレクターと一緒に、企画やコンセプトに基づいて映像を作っていたので、かなり実践的な学びがあったと思います。
池田:年々やってるうちに、スペシャなどで音楽系の番組を作ったりMVを作ったりするディレクターと仕事をするようになって。その中で、電気グルーヴの“Cafe de 鬼(顔と科学)”という曲のMVにモーション制作として参加し、そのビデオが話題になったことが経験として大きくて。各スタッフがそれぞれのスキルを発揮してひとつの映像が出来上がっていく様子を目の当たりにするなかで、ディレクター業に興味を持つようになりました。
リアルで緻密なCGの制作が自分には合わなかったというのも理由の一つでもあります。抽象的な表現は得意なんですけど、例えば立体的な車を作るとかそういう繊細な作業に自分は向いていなかったんです。監督をメインでやるようになり、独立しました。
—なるほど。ちなみに初めての実写作品は?
池田:初めて撮った実写は、JPC bandの“ハイカラ行脚”という曲のMVです。グリーンバックで撮影し、背景はAfter Effectsで作ったグラフィックを合成して完成させました。
独立したての頃は、モーションデザインなどの仕事を請けながら、CMディレクターやプロデューサーと知り合い、徐々に監督の仕事を頂けるようになりました。運がよかったなと思います。
「どうしたら視聴者が面白がってくれるか」が何より大切
ー現在、池田さんは多様なジャンルの映像制作に携わられていますが、大切にされていることはなんですか?
池田: 映像ディレクターの中には、自分の作風がしっかりある人もいらっしゃいますよね。作風を好きになってもらって依頼がくるような、アーティストのような方です。でも私の場合は、「自分の作風はこれ」とは決めず、選り好みをせず、何でもやってみようというスタンスです。やったことがないジャンルやテイストであっても、挑戦してみる姿勢が自分の持ち味とも思うので、大切にしていきたいですね。
いわゆるアーティスト的なこだわりはないですが、「どうしたら視聴者が喜んでくれるか」「面白がってくれるか」を考えることが楽しいんです。なので完成したものをみんなで一緒に見る瞬間が一番好きですね。どうやって伝わったかが実感できるので。
今後、映像制作を取り巻く環境は、3DCGやAIが発展していく中でどんどん変わっていくと思いますが、どれだけ視聴者に響くかが一番大切ということは変わらないと思います。新しい技術やデバイスともうまく付き合いつつ、それがどのように物語やメッセージに生かされるかを考えながら、映像を作り続けたいです。


