
建築士の専門性は拡張できる。クリエイティブディレクター・松井一哲がNOT A HOTELで体現する新しいキャリア
- 2025.10.17
- REPORT
別荘を使いたい日数分だけオンラインで購入でき、資産として保有できる——そんな今までにないサービスを提供しているのが「NOT A HOTEL」だ。創業から5年、会社として急成長を続けており、社員数は350人以上になるという。
同社の成長を創業初期から支えてきたのが、クリエイティブディレクターの松井一哲さん。CINRAは、「建築士の存在や働き方が多様であることを体現したい」という想いを松井さんのnoteで読み、ぜひキャリアや仕事観についてお話を聞きたいと思い取材を申し込んだ。
建築士として大手設計事務所から外資系スタートアップ、そしてNOT A HOTELへと活動の場を移してきた松井さん。「用の美」への憧れから始まった建築への想い、そして今、建築を超えた体験デザインへと視野を広げるキャリアの軌跡を追った。
- 編集・インタビュー・リードテキスト:吉田薫
- テキスト:原里実
- 撮影:kazuo yoshida
大手設計事務所から外資系スタートアップへ。キャリア転換の理由とは
—松井さんは大学院の建築学専攻を修了後、大手建築設計事務所・日建設計からキャリアをスタートさせています。就職先として同社を選んだ理由からうかがってもよいですか。
松井:建築士としてのキャリアを始める場所って、じつはそれほど選択肢の幅が広くはないんです。メジャーな就職先としては、建築設計事務所かゼネコン、あるいはハウスメーカーなど。
日建設計は、人々の暮らしや街の風景に深く関わる建築を数多く手がけており、「人の記憶に残るような建築を設計したい」という自分の思いと重なりました。さらに、学生時代から尊敬していた建築家が在籍していたこともあり、ここでなら設計者として大きく成長できると感じ、入社を決意しました。
—そもそも、建築に興味をもったのはなぜだったのですか?
松井:もともとは建築に限らず、家具や食器、洋服など、いわゆる「用の美」というか、日常生活のなかで必要な機能を備えつつ、素朴な美しさを感じる「もの」にふれると、無性に心惹かれる感覚があって。なかでも建築は、人々の暮らしを包み込み、同時に街の風景を形づくる存在でもある。身近でありながら奥行きのある領域だと感じて、仕事にしたいと思うようになりました。

東北大学工学部卒、東京大学大学院建築学専攻修了。日建設計にて建築設計に従事後、WeWork Japanにて内装デザインを担当。2021年6月NOT A HOTEL参画。建築領域全体のクリエイティブディレクションに加え、KITAKARUIZAWA 「BASE」やNOT A HOTEL OFFICEでは企画・設計を担当。一級建築士 / 管理建築士
—建築そのものだけでなく、生活に関わるもの全般に興味があったのですね。日建設計を経てWeWork Japanに転職されていますが、これはどういった理由からだったのですか。
松井:日建設計では、忙しくもやりがいのあるプロジェクトが多く、尊敬する先輩方と共に働けたのは、とても恵まれた環境だったと思います。
一方で、まわりが優秀な人ばかりの中で働くうちに、特別な才能があるわけではない自分が、何を強みにして価値を発揮できるのかを考えるようになりました。組織の一員として成果を出すことはできても、自分らしい形でどう貢献できるのかを、まだ掴みきれていないように感じていました。
そんな思いから、もっと人とは違う経験を積みたい、自分の興味や強みにもう一度立ち返りたいと考えるようになりました。ちょうどそのタイミングで出会ったのが、WeWorkが立ち上げたデザインコンサルティング会社「Powered by We」でした。
設計事務所での仕事はどうしても「設計」というアウトプットに集約される面が強く、もっと広い視点でデザインに関わりたいという思いが、転職を決めるきっかけになりました。
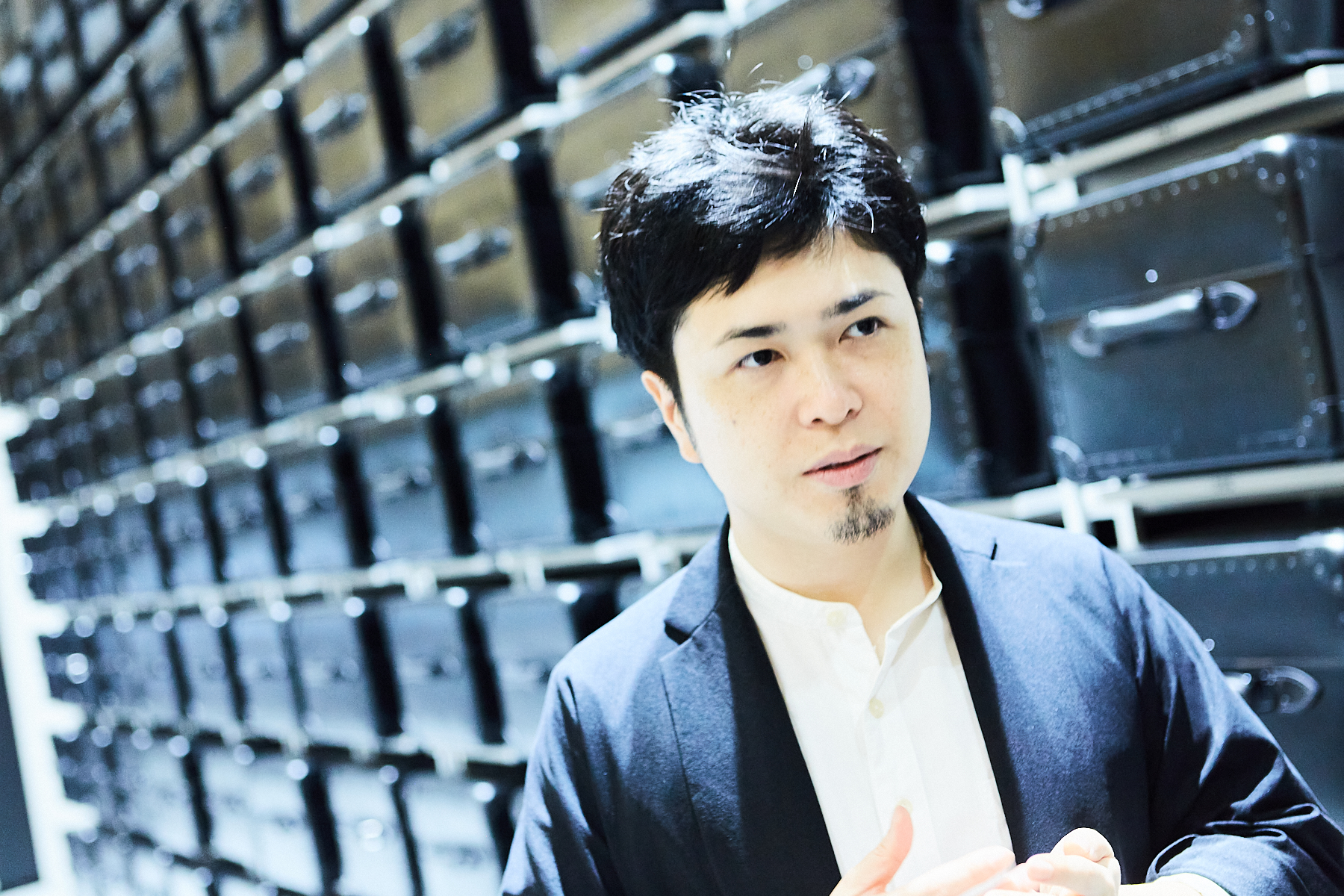
松井:Powered by Weでは、単にオフィスの内装を設計するだけでなく、母体であるWeWorkの運営ノウハウを背景に、オフィスを設けるエリアの選定から、コミュニティを中心に据えた運営方法まで、事業全体を踏まえた提案ができました。
建築を「建てたら終わり」ではなく、「そこからが始まり」と考える視点をもてたのは、自分にとって大きな転機でした。設計の枠を越え、人や組織の営みを含めて空間をデザインするという新しい可能性を学ばせてもらえたと思います。
—建築士として新しい視点を持つきっかけになったのですね。
松井:そうですね。一方で私が入社した当時は、スタートアップとはいえ、想像していたよりも各自の役割やデザインの進め方がすでに整っている段階でした。だからこそ、もし次に転職することがあるなら、もっと何もないところから組織や仕組みをつくり上げていく創業期に関わってみたいと強く思うようになりました。
NOT A HOTELへの参画の決め手は、代表の熱量と「建築 × テクノロジー」への挑戦
—その思いが、NOT A HOTELへの挑戦につながるわけですね。
松井:もともとは、NOT A HOTELで現在建築領域の執行役員をしている綿貫が、日建設計時代の同期だったんです。それで、一緒に建築チームを立ち上げないかと声をかけてくれて、代表の濵渦も交えて食事をして、その日のうちに転職の意思を固めました。
—すごい決断ですね。何が決め手になったのでしょう?
松井:当時はまだNOT A HOTELのECサイトもなく、建物も一棟も竣工していない段階でした。それでも、代表の語るビジョンや熱量に心を動かされたんです。これまでにない形で「暮らしの体験」をつくろうとする姿勢に、純粋にワクワクしました。
それに、建築を事業の軸に据えながらも、当時はまだ建築の専門家が社内に一人もいなかった。自分がその最初の一人として関われるのは今しかないと思いました。
そしてもうひとつ惹かれたのが、テクノロジーと建築を掛け合わせて新しい価値を生み出そうとしていた点です。
AppleやTeslaのように、ハードとソフトを高い次元で融合させることで、人々の体験そのものを変え、その体験がやがて「あたりまえの暮らし」として定着していく。そんなチャレンジを建築の領域で実現できたら、これ以上にエキサイティングなことはないと感じました。
—もともと「暮らし」にまつわるデザインに興味があったという、キャリアスタート時のモチベーションとも呼応したのですね。
松井:まさにそうですね。

NOT A HOTELらしさはどう生まれる? 大切にしている考え方
—建築部のクリエイティブディレクターとして、入社から現在まで、どういった役割を担っているのですか。
松井:入社当初は、ECサイトのキャッチコピーを書いたり、プロモーションビデオの絵コンテを描いて撮影に行ったり……建築の設計から離れたことまで、とにかくいろんな仕事を経験させてもらいましたね。
どれも初めての領域ばかりでしたが、建築設計で培ってきた経験が大いに生きたと感じています。たとえば、思い描いたことをスケッチで表現する力や、物事を順序立てて整理する力、そしてアイデアを魅力的に伝える力など。建築士の専門性は、空間設計にとどまらず、さまざまな領域で応用できる懐の深さがあると思いますね。
チームが成長して体制が整った今では、建築設計や内装設計が業務の中心になっています。もともとの自分の専門領域に立ち戻りながらも、海外の建築家やクリエイターとのやり取りをはじめ、プロジェクト初期の企画・構想やプロポーザル案件の取りまとめ、建築デザインチームとCGパース制作チームの橋渡しなど、事業と建築のあいだをつなぐ役割も担っています。
—NOT A HOTELの物件は、一目見て「NOT A HOTELだ」とわかる、強い世界観が特徴だと感じます。何を大切にして一棟一棟をつくり上げているのでしょうか?
松井:表立って掲げることはあまりありませんが、私たちの中では共通して大切にしている考え方がいくつかあります。
まずひとつは、「Make the Scene(フォトジェニックなシーンを切り取れる空間であること)」という考え方です。
現地を訪れなくても、CGパースや写真を見た瞬間に魅力が伝わるような空間であること。NOT A HOTELでは、建物が完成する前から販売を行うため、その建築の魅力を「絵として伝える」ことがとても重要になります。CGパースは単なる完成予想図ではなく、体験を想起させるための大切なコミュニケーションツールでもあるんです。
もうひとつは、「Sense of Materiality(五感に訴えかける質感の素材で仕上げること)」。無垢材に触れたときの温もりや、真鍮に手を触れたときのひんやりとした質感など、素材が持つリアルな感覚を重視しています。
スマートフォンの中で多くのことが完結してしまう今だからこそ、現実の場でしか味わえない「視覚以外の体験」も空間を通じて届けたいと思っています。

2025年7月に東京・晴海にオープンした複合型ワークスペース「NOT A HOTEL OFFICE」。松井さんもプロジェクトメンバーとして0から空間をつくりあげた。(「オフィスとは何か━━NOT A HOTELのひとつの答え」)
—ホテルにとっては場所も重要な要素ですよね。選定にも何か指針はありますか?
松井:私たちが場所を選ぶ際に大切にしているのは「Landscape First(その場所だからこそ成り立つデザインであること)」という考え方です。土地こそが空間づくりの主役であり、地形や風景、気候といったその土地にしかない魅力を建築を通じてより具体化していきます。
NOT A HOTELが必ずしも都心の一等地に存在しないのはそのためです。便利さだけではなく、その場所に身を置いたときにしか感じられない体験や風景を大切にしています。
建築を超えた体験デザインへの転換
—NOT A HOTELで働くようになって、ご自身にどんな変化が生まれていますか?
松井:NOT A HOTELで働くようになって、世界の見え方が大きく変わりました。以前は建築士として、どうしても関心の中心が「建築」そのものに偏っていたんですが、ファッションデザイナーやシェフなど、異なる分野の一流のクリエイターたちと協働するなかで、「衣・食・住」という枠のすべてがひとつにつながっていることを実感するようになって。
素材の選び方ひとつ、食卓のあり方ひとつにも、その人の生き方や価値観が表れる。そうした「暮らしそのもの」に対する解像度が上がるほど、日々の出来事をより豊かに感じられるようになりました。極端に聞こえるかもしれませんが、生きることそのものが前よりずっと楽しくなったんです。
たとえば、私が設計を担当した「NOT A HOTEL KITAKARUIZAWA BASE(以下、BASE)」では、ファッションブランド〈White Mountaineering〉のデザイナー・相澤陽介さんをクリエイティブディレクターに迎えました。
相澤さんは、家具に使うファブリックのテキスタイルを一からデザインするところから、室内に置くレコードや本のセレクトまで、空間を形づくるあらゆる要素に関わってくださいました。
その一つひとつの積み重ねによって、空間全体の完成度がどんどん高まっていく。「世界観は、細部の積層でできている」ということを、あのプロジェクトであらためて実感しました。

北軽井沢の「BASE L」 Photo:Kenta Hasegawa
松井:この経験を通して、いまは「空間をつくるうえで、建築はひとつの要素にすぎない」と考えるようになりました。
建築そのものは目的ではなく手段であり、大切なのはその場所での滞在をいかに豊かにできるか。そうした「体験のデザイン」こそが、NOT A HOTELの建築に求められる視点だと思っています。
—まさに、竣工がゴールではなくスタートである、事業会社ならではの考え方ですね。
松井:そうですね。BASEの竣工をきっかけに、初めて両親を自分の設計した建物に案内し、一緒に宿泊することができました。これまで建築士として手がけてきたのは研究所やオフィスなど、引き渡した後は自分でも立ち入ることのできない建物が多かったんです。
大学で建築を学び始めてから20年越しに、ようやく親に自分の建築を体験してもらうことができ、少しだけ親孝行ができた気がしました。
事業会社だからできる若手建築士の育成と業界への貢献。『NOT A HOTEL DESIGN COMPETITION』への想い
—今、挑戦していることを教えてください。
松井:2024年から、『NOT A HOTEL DESIGN COMPETITION』という建築コンペを開催しています。40歳未満の建築家・クリエイターなら誰でも応募でき、最優秀賞には賞金1,000万円+設計料が授与されます。さらに、受賞作品は実際にNOT A HOTELとして建設・販売まで行うという内容です。私自身、企画の立ち上げから関わり、現在も運営に携わっています。
現在は第2回の開催に向けて準備を進めている段階ですが、目指しているのは、このコンペを一過性のものに終わらせず、いずれは日本の建築文化の中に根づかせていくことです。
若い建築家やクリエイターが挑戦できる場をつくり、日本各地に新しい名建築が生まれるきっかけにできればと思っています。

2024年の最優秀賞『NATURE WITHIN』。現在、建築が進められている。『NOT A HOTEL DESIGN COMPETITION』詳細はこちら
—すばらしいプロジェクトですね。業界や若手建築士の育成に貢献したいという思いは、昔からあったのでしょうか?
松井:そうですね。建築という仕事は、知識と経験の積み重ねが大きくものを言う世界です。さらに、建設には多くの費用がかかるため、若い世代が自分の思い描いた建築を自由に形にできる機会は決して多くありません。私自身も設計者として駆け出しの頃、どれだけ良いアイデアがあっても、それを実際に建築として「建てる」チャンスがないことにもどかしさを感じていました。
だからこそ、私たちのコンペでは、発想力や情熱を持つ人たちがアイデアを形にできる環境を整えています。NOT A HOTELには、経験豊富な一級建築士が数多く在籍しており、基本設計から実施設計、現場監理まで一貫してサポートできる体制があります。私たち自身もこの挑戦に本気で伴走し、才能ある若い建築家たちのアイデアを、現実の建築として具現化していきます。
第2回となる2026年の舞台は屋久島です。世界遺産でもあるこの地で、NOT A HOTELだからこそできる新たな挑戦の機会をつくっていきたいと思っています。
「設計事務所こそが正義」を越えて──建築士の可能性を、もっと自由に
—これまでのキャリアを経て、今あらためて「建築」や「建築士」という仕事をどう捉えていますか?
松井:かつては、「設計事務所で働く建築士こそが正義」だと信じていました。けれど今は、その枠を越えて、建築の可能性をもっと自由に捉えたいと感じています。
建築士という仕事は、図面を描くだけでなく、空間を通して体験をデザインし、人々の暮らしを少しでも豊かにできる仕事だと思います。だからこそ、その関わり方や生かし方は、人の数だけあっていい。
建築をもっと身近に感じてもらえるように。そして、その面白さや奥深さを、ひとりでも多くの人に伝えられるように。
そんな思いで、これからも自分なりの形で建築と向き合っていきたいと思います。

