
契約書はどのようにつくり、どう読めばいい?映画人たちがフリーランス新法に期待する業界の変化
- 2025.03.19
- REPORT
映画業界を含む文化芸術分野では、長らく契約書を交わさない慣習が問題視されていました。ですが2024年11月からはフリーランス法が施行され、発注者側はフリーランスに仕事を発注後、直ちに業務内容・報酬額・支払期日などを明示することが義務付けられています。契約書があったとしても、健全な労働環境と正当な報酬を守るためには、それぞれがきちんと契約内容を理解し、自身で内容を精査することが必要です。
一般社団法人Japanese Film Project(以下、JFP)では文化庁主催事業として、文化庁が公表した「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン」に基づき、映画関係者に向けて契約に関する様々なコンテンツを作成。昨年は映画スタッフ向けに取り組みを行いましたが、今年は監督や俳優にも範囲を広げ、新たな講座や研修会を実施。1月から2月にかけて、「ゼロから始める、契約書の読み方講座」を複数回にわたり開催しました。
各講座では、フリーランス法や契約に詳しい弁護士が講師として参加し、日本映画業界で働く映画スタッフ、俳優、配給エージェントが聞き役として登壇。実際に契約書の作成を体験し、それぞれの契約事情や労働環境がどのようなものなのか、参加者との意見交換とともに語られました。本記事では開催された全講座の総括として要点をレポートしながら、映画業界における契約のあり方を考えます。
- テキスト・取材:ISO
- 編集:𠮷田薫
契約書作成を映画スタッフ、俳優、配給エージェントはどう見るか
各講座では、本事業で制作されたガイドブックと契約書ひな型例を基に、登壇者と参加者が契約書を作成。実際に自らの手で契約書を作成して感じた意見や、現在の労働と契約の状況などについて、様々な意見が交わされた。
山下久義(以下、山下):そもそも契約書を結ぶことに慣れていないことが多いので、その点を双方理解して進めることが重要だと思います。ひな型も便利で良いと思いつつ、作品によって結ぶべき内容も異なるので、そこは今後細かくなっていくんだろうなと。
特に新人だと報酬の交渉や相場など分からないことばかりだと思います。なので私の助監督チームはベテランから新入りまで、私がまとめて交渉します。「助監督という枠で報酬はこれくらい」と提示されるので、各々の状況次第では自分の報酬を減らして別の人に回すこともありますね。
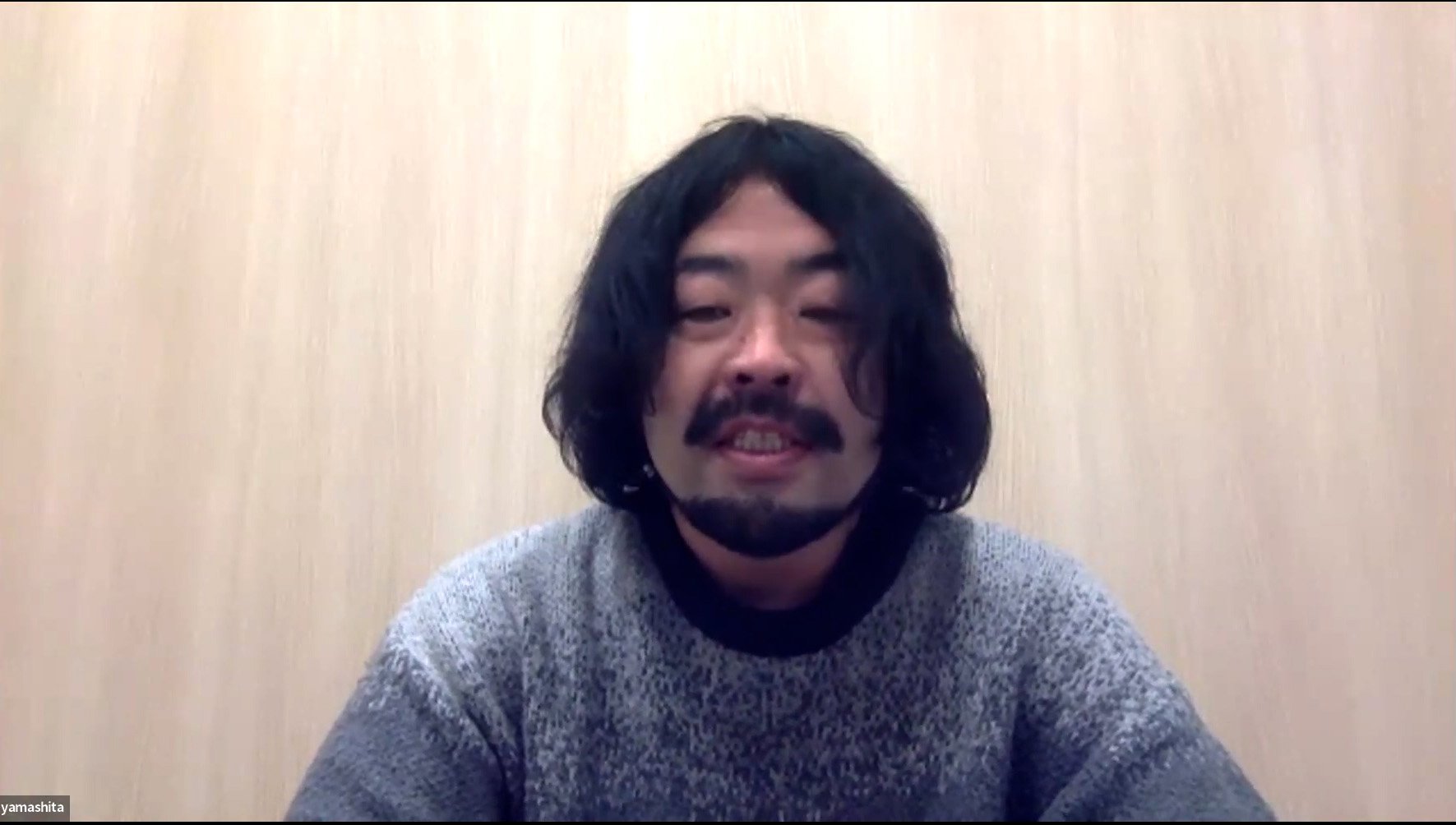
山下久義(助監督)。1980年生まれ。大阪府出身。助監督歴は20年以上。4年前から若手助監督育成の為の「助監督.com」を主宰。主な作品に『チワワちゃん』『そして、バトンは渡された』『夜明けのすべて』『赤羽骨子のボディガード』『ブルーピリオド』『傲慢と善良』など
赤塚佳仁:日本映画の製作現場では、映画スタッフが完璧な分業制になっていないのが大きな問題だと考えます。海外であれば仕事がはっきりと分担され、各自スケジュール表に仕事時間が記載されていますし、労働時間も明確なんです。
一方で日本は、たとえば掃除はどこの担当なのか線引きが非常に曖昧だったりします。だから皆で朝早く来て、最後まで一緒にやるということも。そのように仕事の線引きが明確でない傾向がある以上、今後は業務内容などを含むきっちりした契約書を成り立たせることが日本の映画界の課題かもしれません。私は契約書を作るうえでは報酬面の交渉を重視したほうがよいのかなと思います。

赤塚佳仁(映画美術監督)。米アカデミー協会執行委員。日本映画装飾協会専務理事。日本映画・テレビ美術監督協会理事。株式会社京映アーツ副社長取締役。数多くの日本映画、海外作品にプロダクションデザイナーやセットデコレター、装飾として関わっている
小野寺史穂理:今回いただいた契約書のひな型を見たときに、もしこれが昔からあればどれだけ守られてきたんだろうと思いました。事務所に所属していた時でさえ契約書がなかったこともあり、ある現場では撮影が長引いたのに報酬は変わらず、時給換算すると300円以下だったこともありました。でも契約書があったらそれも防げたのだろうなと。
現在、「文化・芸能業界のこころのサポートセンターMeBuKi」で相談を受ける50%以上がハラスメントに関するものです。契約書では「配慮」という項目で記載されていますが、今後より内容が具体化・明確化され、あらゆるハラスメントを事前に防止できるものになればいいなと期待しています。

小野寺史穂理(俳優・臨床心理士・公認心理師)俳優活動を経て、臨床心理士・公認心理師となる。2013年に野田地図『MIWA』(作・演出 野田秀樹)に出演したほか、ミス・インターナショナル2013日本大会ファイナリストに選出される。現在は、「本郷東大前こころのクリニック」と小・中学校にてカウンセラーとして勤務しながら、俳優活動も継続している。 2022年、業界内のさまざまな問題を受け「文化・芸能業界のこころのサポートセンターMeBuKi」を立ち上げた
工藤梨穂:自主制作の映画を上映・配給した際に、上映物のことでちょっとしたトラブルになったことがあったんです。その際にどのように対応していいかわからず、契約をもっと明確にしておけばよかったと今回改めて感じました。
また報酬の話は仕事のオファーを受けてからしばらく進んだあと、かつ契約書より口頭で交わされることが多いので、その点は今後是正されていってもらえればと思います。

工藤梨穂(映画監督)1995年生まれ。福岡県出身。京都造形芸術大学(現・京都芸術大学)映画学科卒業。同大学の卒業制作『オーファンズ・ブルース』が第40回ぴあフィルムフェスティバル「PFFアワード2018」においてグランプリなど2冠を受賞し、2020年にPFFスカラシップで『裸足で鳴らしてみせろ』を製作し商業デビュー。最新作『オーガスト・マイ・ヘヴン』が配信プラットフォームRoadsteadにて販売中
渡辺祐一:経験のあまりない製作者は配給と交渉をするための知見がなく、アンフェアな契約を結んでしまう可能性があります。仮に興行収入の50%が配給収入だとしましょう。それを製作者と配給とで、どう分配するか? 僕がフェアだと思うのは次のような考え方です。まず配給がある一定の割合を配給手数料としてもらいます。公開規模が広がれば、その分の費用と作業が増えるからです。そこから、製作者と配給がそれぞれが出資した製作費と配給宣伝費の比率を指針の一つとして分配率を決めていくというものです。
ただし、公的助成や特別協賛金、カンパの有無などによって事情は異なります。ですから個別具体的な事情を正直に話し合い、双方にとってよりフェアな落とし所を相談できるビジネスパートナーを見つけることが何より大切だと思います。

渡辺祐一(映画配給)。1978年生まれ。2009年、映画配給会社東風の立ち上げに参加。ドキュメンタリーを中心に映画の配給・宣伝を手がける。2014年より日本映画大学で非常勤講師として配給・興行システムを講じる。2024年12月に東風を退社し、映画配給会社アギィを設立。
浅田智穂:ひな型を見たところインティマシーコーディネーターに関わる項目で、「露出や性的表現に対する事前協議」というものがあります。我々は同意書でその同意を得ることを仕事としていますが、その旨が契約書に記載されているのは良いことだと思います。ただ、現状は同意書を交わす段階で俳優の皆さんは契約書を結んでいないことが多い。本来「出演契約書→同意書」の順番で交わすべきだと思いますが、なかなかその順番がうまくいっていないと感じているので、フリーランス新法によって変わっていけばいいなと思います。

浅田智穂(インティマシーコーディネーター)。1998年、ノースカロライナ州立芸術大学卒業。帰国後、エンターテインメント業界で通訳者として活動。2020年、アメリカのIntimacy Professionals Association (IPA)にてインティマシーコーディネーター養成プログラムを修了。Netflix映画『彼女』(2021)、映画『怪物』(2023)、NHKドラマ『大奥』(2022〜2023)、その他多数の作品に参加。後進育成やより安心安全な映像制作のために、2023年に株式会社Blanketを設立
弁護士からフリーランス新法の解説も実施された
永井靖人:そもそも契約とは当事者間の約束のこと。書面はもちろん口頭でも契約は成立し、契約をすると双方に法律的権利と義務が発生します。契約を破ると紛争が生じる可能性がありますが、適正な契約書があると双方の権利と義務が明確化され、紛争を防いだり裁判時に証拠になるなどの役割を果たします。また契約書を作成する過程で、相互の認識の擦り合わたり、仕事内容や報酬の交渉ができるといったメリットもあります。
一方で契約書がないと、条件や仕事内容に齟齬が生じたまま業務が進み、仕事内容を満たしていないとして報酬が貰えなかったり、損害賠償が生じる可能性も。それを防ぐためにも、仮に契約書が作られていない場合はメールやメッセージなどの証拠を残すことが重要です。
契約書を交わすときのコツは、契約の中心にあたる義務(自分が何をしなければいけないか=出演義務、報酬支払い義務など)と権利(自分は何をしてもらえるか=報酬額、相手の仕事)をしっかりと明確にし、こちらの希望を出していくこと。
現在はフリーランス法が施行されたことにより、フリーランスに発注する際には、発注者に契約書の義務が生じます。これは発注者とフリーランスの権力関係の平等を図ることが目的。
困ったときには弁護士や、文化庁の「文化芸術活動に関する法律相談窓口」、関係省庁が連携し運営されている「フリーランス・トラブル110番」に相談していただければと思います。

永井靖人(弁護士 波千鳥法律事務所 代表弁護士)。早稲田大学第一文学部卒業、早稲田大学法務研究科修了。2015年弁護士登録及び早稲田リーガルコモンズ法律事務所入所。2019年波千鳥法律事務所を開設、同代表。現在まで、顧問先を中心とした契約書作成や法律助言業務を行うほか、紛争や訴訟対応に取り組む。また、弁護士登録時から、芸術・文化・創造的な活動への支援プログラムを企画運営する非営利任意団体Arts&Lawに参加。知的財産権に関するセミナーや講演・講義、相談会を実施している
聞き手として登壇した映画監督・高野徹氏はフリーランス・トラブル110番に相談した経験があるという。
高野徹:映画の仕事をした際にトラブルが発生し、発注者側が報酬の減額を一方的に突きつけてきたことがあったんです。一向に話を聞いてくれない状況だったのでフリーランス・トラブル110番に連絡したところ、弁護士の方がオンラインで親身に相談に乗ってくれました。「こういうことを記載した書面を送るといい」といただいたアドバイス通りにしたところ、それまでの対応が嘘のように話を聞いてくれて満額報酬が支払われました。無料で解決できたので驚きました。

高野徹(監督・助監督)。1988年生まれ。横浜国立大学大学院都市イノベーション学府修了。 濱口竜介監督『ハッピーアワー』(2015年)、『偶然と想像』(2021年)などに助監督として参加し、2023年に監督作『マリの話』を発表
長澤哲也:フリーランス法のような法律があるのは、先進国で日本のみ。取引をしたあとに適正な対価を払うという大前提が機能していないことが理由です。特に大企業と中小企業、企業と個人のような取引上の格差がある場合、その格差によって後から条件が変わったりと弱い立場の者が不利益を被る可能性が高い。その格差を是正し、後出しジャンケンを禁止するためにできたのがフリーランス法です。
フリーランス法により、発注者は条件を明記した契約書の発行が義務付けられましたが、中身を決めるのは双方なので受け身ではいけません。フリーランス法上の義務には以下のようなものがあります。
・書面などによる取引条件の明示
・報酬支払日の設定、期限内の支払い
・禁止行為(報酬の減額や不当なやり直し等)
・募集情報の的確表示
・育児介護等と業務の両立に関する配慮
・ハラスメント対策に関する体制整備
・中途解約等の事前予告、理由開示
フリーランス新法で義務付けられている内容以外ですと、自身の身を守るために以下の項目を入れることを推奨します。
・業務期間が延長された場合の追加報酬
・業務時間とそれに伴う追加報酬
・完全休養日(撮休日とは異なる)とそれに伴う追加報酬
・休憩等とそれに伴う追加報酬
長澤:契約書とは、仕事の実態や業務内容を反映させた契約を文字にして定め、それに見合った報酬を求めるためのもの。制作会社と映画スタッフ双方で様々な要点を定めなければいけません。
「良い映画をつくる」という最終ゴールは共通しているはずなので、そのためにも双方間でしっかりと意思疎通して、自分の価値に見あった報酬を認めてもらい、認識に齟齬がないようにしていくことが大切です。

長澤哲也(弁護士・弁護士法人大江橋法律事務所 パートナー弁護士)。主著として、『優越的地位濫用規制と下請法の解説と分析〔第4版〕』(商事法務、2021 年〔初版2011 年〕)、『独禁法務の実践知』(有斐閣、2020 年)。文化庁 文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けた検討会議委員
参加者による意見交換も
映画スタッフや俳優などとして活動する参加者もグループワークを行い、様々な意見交換が行われた。
多くの参加者が語っていたのは、これまでほとんど契約書が交わされていなかったということ。業務内容や報酬が曖昧のまま仕事が進むことも多く、それでトラブルになることも。しかしひな型に沿った契約書があれば、あらゆるトラブルは未然に防げるのではないかと、契約書の作成を肯定的に見る参加者が多数を占めた。
日本では他国のように業種ごとの最低賃金は設定されていないので、報酬などの交渉をする際は同業種で情報を共有したり、集団性を持って契約書を作成するのが良い、などといった建設的な意見も交わされた。
さいごに
フリーランス法施行に伴う契約書の導入で、変化が訪れ始めた日本の映画業界。健全な労働環境で、適正な報酬を受け取るためにも、発注者だけでなく受注者側であるフリーランスが契約をよく理解し、能動的に交渉していかなければならないだろう。
JFPはその一助となるよう、映画スタッフ・俳優・配給エージェント向けに、契約書ひな型例とガイドブックを作成し、HPに掲載しているとのこと。弁護士による解説動画もあるので、それらを活用してぜひ契約書についての理解を深めて欲しい。
主催:文化庁(令和6年度「芸術家等実務研修会」)
事務局・企画・運営:一般社団法人Japanese Film Project
▼参考記事
映画文化を守る、フランスの法制度・契約事情。黒沢清が語った「映画が生き残っていく道」とは
契約書が普及し、変化した韓国映画業界。韓国在住の監督・俳優に聞く生の声
▼参考動画
映画関係者のための契約レッスン:紹介アニメ動画(文化庁委託事業)
