
映画文化を守る、フランスの法制度・契約事情。黒沢清が語った「映画が生き残っていく道」とは
- 2025.02.13
- REPORT
映画業界を含む文化芸術分野では、長らく契約書を交わさない慣習が問題視されていました。ですが2024年11月からはフリーランス・事業者間取引適正化等法(以下、フリーランス法)が施行され、発注者側はフリーランスに仕事を発注後、直ちに業務内容・報酬額・支払期日などを書面または電磁的方法で明示することが義務付けられています。契約書があったとしても、健全な労働環境と正当な報酬を守るためには、それぞれがきちんと契約内容を理解し、自身で内容を精査することが必要です。
一般社団法人Japanese Film Project(以下、JFP)では文化庁主催事業として「俳優のための契約レッスン」「配給・エージェントとの契約レッスン」と題し、文化庁が公表した「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン」に基づき、映画関係者に向けて契約に関する様々なコンテンツを作成しています。昨年は映画スタッフ向けに取り組みを行いましたが、今年は監督や俳優にも範囲を広げ、新たな講座や研修会を実施。1月25日には、フランスから契約事情を学ぶ『オンライン講座 映画スタッフ・監督の契約事情~フランス映画界の事例紹介~』が開催されました。
この講座には『ダゲレオタイプの女』(2016)、『蛇の道』(2024)の撮影をフランスで実施した映画監督の黒沢清、在仏メイクアップアーティストの岡悠美子、在仏映画ジャーナリストの林瑞絵が登壇。フランスの契約事情や労働環境がどのようなものなのか、具体的なエピソードとあわせて語られました。
本稿ではオンライン講座の内容をレポートしながら、映画業界における契約のあり方を考えます。
- テキスト・取材:ISO
- 編集:𠮷田薫
監督・黒沢清が「羨ましい」と感じたフランス映画制作現場の空気感
ISO:『蛇の道』『ダゲレオタイプの女』をフランスで撮影された黒沢さんに、日仏の撮影現場の違いをおうかがいします。まず、フランスで映画を製作して感じた日本との違いはありましたか?
黒沢:スタッフの細かい動きまでは把握していませんが、監督としては基本的に日本と変わらないと感じました。日仏ともに契約書はありますが、あくまで一番重要なのは人間的な信頼関係だと思います。
ISO:韓国の撮影現場では「必ず温かい食事が出て、食事時間は絶対に削らない」とよく聞きます。フランスの撮影現場における食事や休憩はいかがでしたか?
黒沢:食事はデザート込みの豪華で美味しいランチが提供されました。そこで感じたのは「自由」であること。20分でパッと食事を終わらせて仕事に取り掛かる撮影監督がいれば、その助手はゆっくり休憩していたり、出番の少ない俳優は2時間くらいかけて食事してワインまで飲んでいる人もいたり。温かい食事を皆で食べるのは良いことと考えてはいるけど、それをしなきゃいけないわけではないんです。皆がそれぞれの仕事の状況に応じ自由に休憩していて、上司に気を遣ったりという上下関係はない。文化的に日本に取り入れるのは難しいかもしれませんが、羨ましい環境でした。
ISO:監督は『蛇の道』『ダゲレオタイプの女』ともに、フランス人スタッフを起用されていますが、日仏で監督やスタッフにどういった動きの違いが感じられましたか?
黒沢:これも基本的に日本と変わらないと思います。フランスの撮影現場も、全スタッフ・全俳優が監督のビジョンを実現させるために全力を尽くしてくれる。皆仕事としてやっていると同時に、映画が好きで、監督のクリエイティブを尊重してくれるんです。それは日仏共通でした。
そしてやはり上下関係がないことは大きくて、皆が仕事をしている夕方ごろにセカンド助監督が「妻と演劇を観るので」と帰っていくんです。もちろん自身の仕事は終わらせ、撮影に支障が出ないようにしたうえですが。見ていてとても気持ちの良い現場でした。
ISO:フランスでの撮影を経て、日本の製作現場に導入してほしいと感じたことがあれば教えていただけますでしょうか?
黒沢:日本では撮影前に「衣装合わせ」が行われます。でもこれは衣装を合わせることが目的ではなく、ほぼ全スタッフと俳優が集結して打ち合わせまで行う一種の儀式のようなもの。それが悪いとは言いませんが、とても時間を要してしまいます。でもフランスにはそれがない。何を着るかは衣装スタッフと俳優が独自に選び、別の仕事をしている監督に写真が送られてくるんです。そしてどこかのタイミングで実物も見せてくれて正式に決定する。合理的で良い方法だと思いましたし、『蛇の道』主演の柴咲コウさんもやりやすいと言っていましたね。
また、田舎でロケをするときにはトイレカーを用意してもらえるんですが、それが驚くほど広くて綺麗で豪華。音楽も流れていて、とても落ち着いた空間なんです。すると、トイレに行くたびにホッ……とリラックスできる。日本ではトイレボックスが一般的ですが、多少お金がかかってもぜひそのトイレカーは導入してほしいですね。
ISO:適正な契約や就労環境が、どのように映画そのものへ影響を与えるか、ということについて。フランスと日本での映画製作のご経験からご意見があれば教えていただけますか?
黒沢:作品の質がどうこうの前に、労働なのだから適正な就労条件を守るのは社会人として当たり前のこと。でもこれが日本で守られていないのは、何十年も前にあった撮影所の影響が大きいと思っています。一般社会とは異なる組織の特異な環境や上下関係のなかで、カリスマ的な巨匠が特異な環境でしか到達できないような傑作をつくり、良いか悪いかは別として、それがヒットして世界的に評価された。それが「自分たちは特別だ」という感覚を根付かせ、未だいろんな問題を生んでいるのではないかなと。でもとっくにそんなものはないわけです。
社会人として、映画作りに皆が参加している訳ですから、真っ当な社会人が真っ当に映画を作っていくしか、映画が生き残っていく道はない。そんなものは何十年も前からないのだということを、やっと日本の映画業界も認識し始めたのかなと感じています。
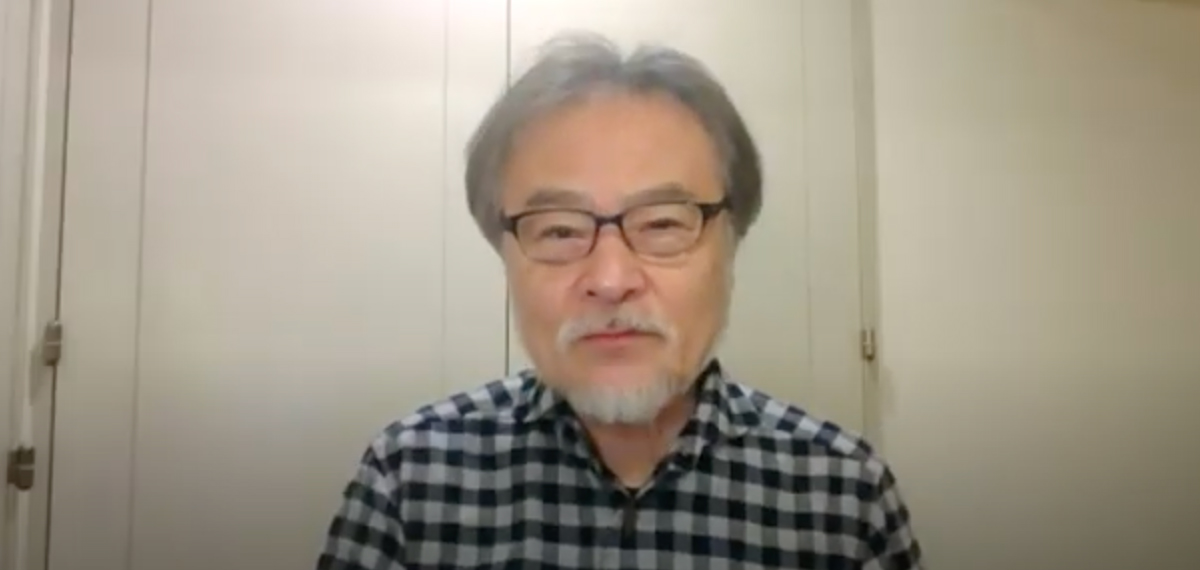
黒沢清:映画監督
1955年兵庫県神戸市生まれ。立教大学在学中より8ミリ映画を撮り始める。長谷川和彦、相米慎二に師事した後、商業映画に進出。97年の『CURE』で世界的に注目され、2001年の『回路』で『第54回カンヌ国際映画祭』国際批評家連盟賞を受賞。その後も08年の『トウキョウソナタ』で同映画祭の「ある視点」部門審査員賞、14年の『岸辺の旅』では同部門監督賞を受賞。20年に公開された『スパイの妻』は『第77回ヴェネチア国際映画祭』で銀獅子賞を受賞した。2024年には『蛇の道』『Chime』『Cloud クラウド』の3作品が公開された。
フランス映画界の法制度と契約の仕組みとは
林瑞絵(以下、林):フランスには労働の法律である「労働法典」があり、それを補完する「労働協約」が業界や職種ごとに存在します。実写映画の製作の仕事において適用される労働協約は「映画製作の全国労働協約」と呼ばれるもの。従属関係がある有期の労働には雇用契約書は必須なので、誰かの指示のもとで働く映画スタッフも労働協約に基づき雇用契約を結びます。標準的な契約書式がある韓国と異なり、フランスでは企業ごとに作成された契約書を使うのが一般的。実務家の視点で言えば映画界で結ばれる契約書は主に以下の2種類があります。
・労働法典・労働協約 に基づく契約:働く期間が決まった監督含むスタッフや俳優の契約
・「知的所有権法典」に基づく契約:脚本家、監督、および字幕翻訳者のための著作者の契約や権利譲渡の契約
林:労働協約は絶えず進化しており、賃上げ交渉のような定番の議題に加え、最近はハラスメントやAIに関する修正が追加されています。「映画製作の全国労働協約」には、具体的に以下のような内容が記載。
職種における業務内容の定義
監督を始め、全ての職業が定義される。2024年には16歳未満の俳優を守る「子どもの責任者」という職業が追加され、今後はインティマシーコーディネーターやカラリストも追加予定
労働時間、休憩、休日
撮影時期は週39時間(1日8時間の計算)を基準に設定される
週最大48時間で基本は週休二日(特定の技術者は別途)
翌日の撮影まで、最低11時間を空ける
7日連続の就労は禁止 日曜に撮影する場合は特別に許可申請が必要
賃金
仕事ごとに最低賃金が設定される。夜間・休日出勤は増額、日曜は賃金二倍
食事
食事の提供か、食費の支払いが規定されている
白テントの即席食堂のなかで暖かな食事をとれることが多い
それ以外にも、宗教、人種、性別、政治的意見、障がいなどによる差別の禁止/安全と衛生の配慮/健康や福祉について/ハラスメントについて…などが記載されている
林:#MeToo運動はフランス映画界にも大きな変化をもたらしました。2021年から、映画の雇用者が助成金を得るためには、性暴力予防の研修が必須に。現在は製作者、配給者、国際セールス、映画館の興行者などの雇用主が研修を受け、認定を受ける必要があります。単に倫理観や道徳観に訴えるだけではなく、研修を映画助成の仕組みに組み込んでいるんです。さらに2025年1月からは、職種に限らず撮影現場で研修に参加できるように。
それ以外にも、心理・法律の専門家に匿名かつ無料で相談できる窓口が設けられていたり、映画・映像関係者用のハラスメント予防キットを公表・配布する、といった取り組みが行われています。
またフランス芸術界特有の制度に、アンテルミタン制度というものがあります。「年間507時間以上の就労」という条件が認定されれば、収入のない日に失業保険として一定の補償収入(2020年:平均56€/日)を得ることが可能になるというもので、不安定な働き方に理解のある世界でも珍しい制度です。
<参考記事>
契約書が普及し、変化した韓国映画業界。韓国在住の監督・俳優に聞く生の声

林瑞絵:在仏映画ジャーナリスト
北海道札幌市出身。映画会社で宣伝担当を経て渡仏。パリを拠点に欧州の文化・社会について取材、執筆。海外映画祭取材、映画人インタビュー、映画パンフ執筆など。現在は朝日新聞、日経新聞の映画評メンバー。著書に仏映画製作事情を追った『フランス映画どこへ行く』(キネマ旬報映画本大賞7位)、日仏子育て比較エッセイ『パリの子育て・親育て』(ともに花伝社)がある。

ISO:フリーライター・司会
奈良県出身。映画を主軸に活動しており、主な寄稿先は劇場プログラムやCINRA、映画.com、月刊MOEなど。作品インタビューや批評記事をはじめ、映画業界の現場や課題など、社会的な視点からの記事も執筆する。J-WAVE「PEOPLE’S ROASTERY」で映画紹介を担当するほか、トークイベントの登壇など活動は多岐にわたる。
現場スタッフが感じた日仏の一番の違いは時間管理の厳格さ
ISO:在仏メイクアップアーティストの岡さんは、どのような経緯でフランス映画界で働き始めたのですか?
岡悠美子(以下、岡):もともとは大阪でメイクのアシスタントをしていました。そこから渡仏し、2000年代始めにテレビ局のプロデューサーから仕事を受けて以降、フランスで22年間メイクの仕事をしています。
ISO:日本とフランスで、撮影現場の労働時間の捉え方についてはどのような違いを感じますか?
岡:フランスは、勤務時間や休憩時間、超過した場合のオーバーチャージなどすべての時間が厳密に管理されています。たとえばメイクを含む制作スタッフは勝手に自分の入り時間を決められません。前日に各部署が演出部と話し合い、プロダクションと相談のうえで最終的な入り時間が決まるんです。そして残業をするにもプロダクションに掛け合って承諾をとらなければいけません。
ISO:フランスの制作スタッフは、皆ユニオンやギルドに入っているんですか?
岡:人によりますね。業界の人はそれぞれの関係する業界団体に所属することが多いですが、私はまだ入っていません。
ISO:岡さんも契約書を交わしているかと思いますが、契約書について岡さんはどこで学んだんでしょうか?
岡:文章が長く理解できない部分が多いので、私も当初はちんぷんかんぷんでした。でも現場には必ず契約内容に詳しい人たちがいるので、抑えておくべきところなどをその人たちに教えてもらいました。
ISO:撮影現場におけるハラスメント対策はどのように行われているんでしょうか?
岡:日々のスケジュールが書かれたコール・シート(進行予定表)に、ハラスメント対策の相談窓口が記載されています。対応も迅速で、そこに訴えられて即日クビになった人も見たことがあります。研修のようなものはまだ受けたことがありません。
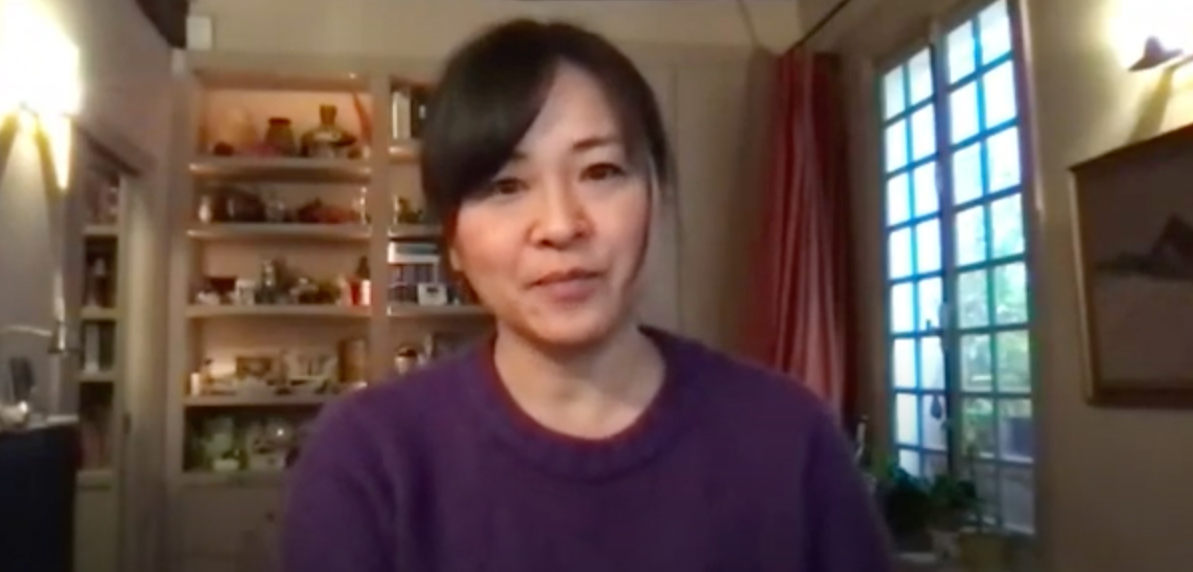
岡悠美子:在仏メイクアップアーティスト
大阪府出身。2002年渡仏し、2006年からフランスのテレビ局TF1のドラマで3年間チーフメイクを担当。以後、ドラマのメイクを継続しながら、映画のアシスタントメイクを経て、映画『メモリーズコーナー』『En pays cannibale』『 l’antiquaire』『バティモン5 望まれざる者』などのチーフメイクを担当している。
同講座では参加者からの質問に答えるQ&Aも実施された
Q.演出部では七五三(70万、50万、30万)といったように、日本の現場ではある程度報酬の相場がありますが、フランスの撮影現場のおおよその相場はあるのでしょうか?
岡:作品の予算にもよりますが、それぞれの職種や役職によって「最低でもこの賃金」という料金表が設定されています。それを基準に報酬が契約書に記載されますが、納得いかなければ交渉もできると思います。
黒沢:具体的な報酬はわかりませんが、私が知る限りフランスは助監督のシステムが違っていて、チーフ助監督が制作のほぼすべてに関わるんです。日本だとセカンド助監督は衣装担当、サード助監督は美術担当というように役割が分かれているんですが、フランスはすべてチーフの担当でセカンドやサードはあくまで助手。能力も労働時間も桁違いなので、そこは報酬も破格なのではないかなと思います。
Q.監督は企画段階で契約書を交わすことが可能なのでしょうか?
黒沢:まずこういう作品を撮りたいというプロットを書くのですが、私の経験上、日本ではそこまでは無償の場合が多い。その後、企画が成立しなければ報酬は発生しません。そこから脚本を書くとなっても、その段階で契約書が交わされることはあまりないと思いますが、プロデューサーが口約束で「第一稿ができたらこれくらい払います」といったような話をしてくるのが普通です。脚本を書いても企画が頓挫することもよくありますが、約束した額はなんとか払ってもらうという紳士協定が日本の現状かなと思います。
林:フランスの場合、基本的に雇用者は、雇用後の48時間以内に従業員に契約書を送付するという決まりがあります。ただしそれが必ずしも守られているわけではありません。
Q.フランスでは映画業界に関係する法律や労働法典、契約について大学などの関連学部で学ぶことはできるのでしょうか?
林:現状はそのような授業は行われておらず、あるとしても一部の大学で労働組合の人が年に6時間ほど出張授業をする程度。ですが法律や契約については皆知るべき内容なので、本来は必修科目として学ばせるべきだと思います。
日本のよりよい労働環境に向けて
黒沢:映画制作にあるのは単純な労働の喜びだけでないと私は信じています。スタッフや俳優が気持ちよく、楽しく、熱意を持って働けるかを左右するのは監督です。監督がどのように現場をうまくまわし、ビジョンをスタッフや俳優に伝え実現させていくか、映画制作の喜びはそこにかかっている。私個人としては、何よりそこを重視したうえで、契約もきちんとやっていくこと。それが映画にとって健全だと考えています。
林:フランスの「芸術を守ろう」という態度は理想主義的に見えますが、労働環境や契約のことを詳しく見ると現実的な面もあり非常にバランスが良い体制であると今回あらためて感じました。取り入れられるかは別として、日本の労働環境や契約の参考になればと思います。
岡:今回登壇を決めたのは、日本から来た撮影隊の方々に過酷な労働環境について聞いたから。今日明日でフランスのようになることは難しいと思いますが、ひとつずつでもきっとできることがあるのではないかなと思い、フランスの事例を挙げさせていただきました。今回のお話がヒントになれば幸いです。
ISO:本日はフランスの労働事情を知ることができてとても勉強になりました。日本の映画文化が発展していくためにも健全な労働環境は必須ですので、ライターという立場から、他国の就労状況などを発信していくことで映画界に貢献できればと考えています。
さいごに
フリーランス新法施行に伴う契約書の導入で、変化が訪れ始めた日本の映画業界。他国の働き方や契約事情を参考にしながら、正しく契約書について学んでいく必要があります。
JFPではオンライン講座以外に、2月からは対面研修会の実施中。映画スタッフ編、俳優・配給&エージェント編と、業種に応じて東京・大阪で開催。毎回専門の弁護士と多様な映画関係者が登壇し、契約書についてわかりやすく解説するとのこと。無料で参加可能なので、この機会にぜひチェックしてみましょう。
2月12日(水)「ゼロから始める、契約書の読み方講座〜俳優・配給&エージェント編〜」@梅田・立命館大学ROOT
2月15日(土)「ゼロから始める、契約書の読み方講座〜俳優・配給&エージェント編〜」@Space&Cafe ポレポレ坐
主催:文化庁(令和6年度「芸術家等実務研修会」)
事務局・企画・運営:一般社団法人Japanese Film Project
▼参考サイト
映画関係者のための契約レッスン – Japanese Film Project
