
複雑な社会課題に、デザインができることは? 社会×クリエイティブ領域で活躍するクリエイターたちと考える
- 2024.03.29
- REPORT
インパクト業界最大規模となる同イベントには、起業家や投資家、有識者など、業界をリードする人物たち約100名が参画。さまざまな角度から「インパクト」に関する議論が交わされるなかで行なわれたトークセッション「デザインは社会課題の複雑性を超えられるのか ―共感の波を起こすイシューデザイン―」の内容をレポートする。
- 取材・文:石塚振
- 写真:豊田和志
- 編集:生田綾
「複雑なものを複雑なまま伝える」ことの大切さ
セッションでは、社会と環境の観点から持続可能な範囲での利益創出や成長を目指す「ゼブラ企業」の支援を行なうZebras and Company代表の阿座上陽平氏がモデレーターとして登壇。
社会やビジネスといったさまざまな仕組みの図解を行う図解総研代表の近藤哲朗氏とソーシャルイノベーションスタジオである公共とデザイン共同代表の石塚理華氏、社会課題に映像制作でアプローチする、イグジットフィルム代表兼ブラックスターレーベル代表理事の田村祥宏氏の3名と話し合った。

モデレーターの阿座上陽平氏、公共とデザイン共同代表の石塚理華氏

図解総研代表の近藤哲朗氏、イグジットフィルム代表兼ブラックスターレーベル代表理事の田村祥宏氏
セッションは、「社会課題」という複雑性を持つものをどのようにクリエイティブとして表現するのかについての議論からスタートした。
スタートアップから大企業などのビジネスモデルを図解したシリーズで注目を集めた近藤氏は、複雑な事象を「図解」という形でシンプル化してきた。「最近は複雑なものをシンプルにするのではなく、複雑性を残したまま理解できるような形で表現することに取り組んでいます」と話す。
「女性のウェルネス課題デザインマップ」が公開されました!女性のウェルネスにまつわる社会課題の構造を因果関係とともに可視化したマップです。… pic.twitter.com/43uEJiE6P8
— チャーリー (@tetsurokondoh) December 11, 2023
「図解は情報に優先順位をつけ、取捨選択をし、構造化する作業のため、気をつけないと重要な情報が捨てられてしまう可能性もあります。図解にはある種の暴力性があり、捨てられた周辺情報に目を向けられないまま拡散されてしまう危険性もあります」
「もちろん、人は複雑なものを一目見てすぐには理解できないし、敬遠してしまうこともある。そのなかで、シンプルでわかりやすい、入口としての図解には意味があります。ただ、そこで終わるのではなく、徐々に理解を深めていき、複雑なものを理解したくなるといった好奇心の階段をどうつくっていくのかが重要だと考え、複雑性をどう表現すべきかに注目するようになりました」

複雑なものの複雑性をもたせたまま、情報の受け手が何かを感じ取れるようなクリエイティブにするにはどうしたら良いのか。
その課題に挑戦したのが、田村氏が手がけた映画『Dance with the Issue:電力とわたしたちのダイアローグ』だ。電力の課題に対して、経産省や東京電力、新エネルギーのプレイヤーやシンクタンクなどさまざまな立場の担当者たちの語りとコンテンポラリーダンスを組み合わせた本作品について「複雑なものに、複雑なメタファーを組み合わせるという手法を取りました」と田村氏は語る。
「ロジックでは解けないような難しい問題においては、一つの答えを示して『みんなでこっちに向かおう』と誘導するのは解決には至らないと考えていました。僕としては特定の道にみんなを連れていきたいわけではなく、解決をしたいだけ。そう考えたとき、複雑性をそのまま残すことの大切さを感じました」
「しかし、電力などの課題は、一個人にとっては遠すぎる問題で、情報も偏っているため、個人ではアクションを取りづらい側面もあります。自分の暮らしはどうするのかといったレベルにまで落とし込み、一人一人の観客の心の深い部分にアクセスできるチャンネルをつくることが重要です。
そのアクセス手法の一つとして、アートの領域は非常に役立つと思っていて。何が美しいと思うのか、何が楽しそうに見えるのか、何が幸せと感じるのかが鍵となり、そこから参加者が増えていくことで大きなアクションになり、意見が形成されていき解決に向かっていくのかなと考え、今回の作品をつくりました」
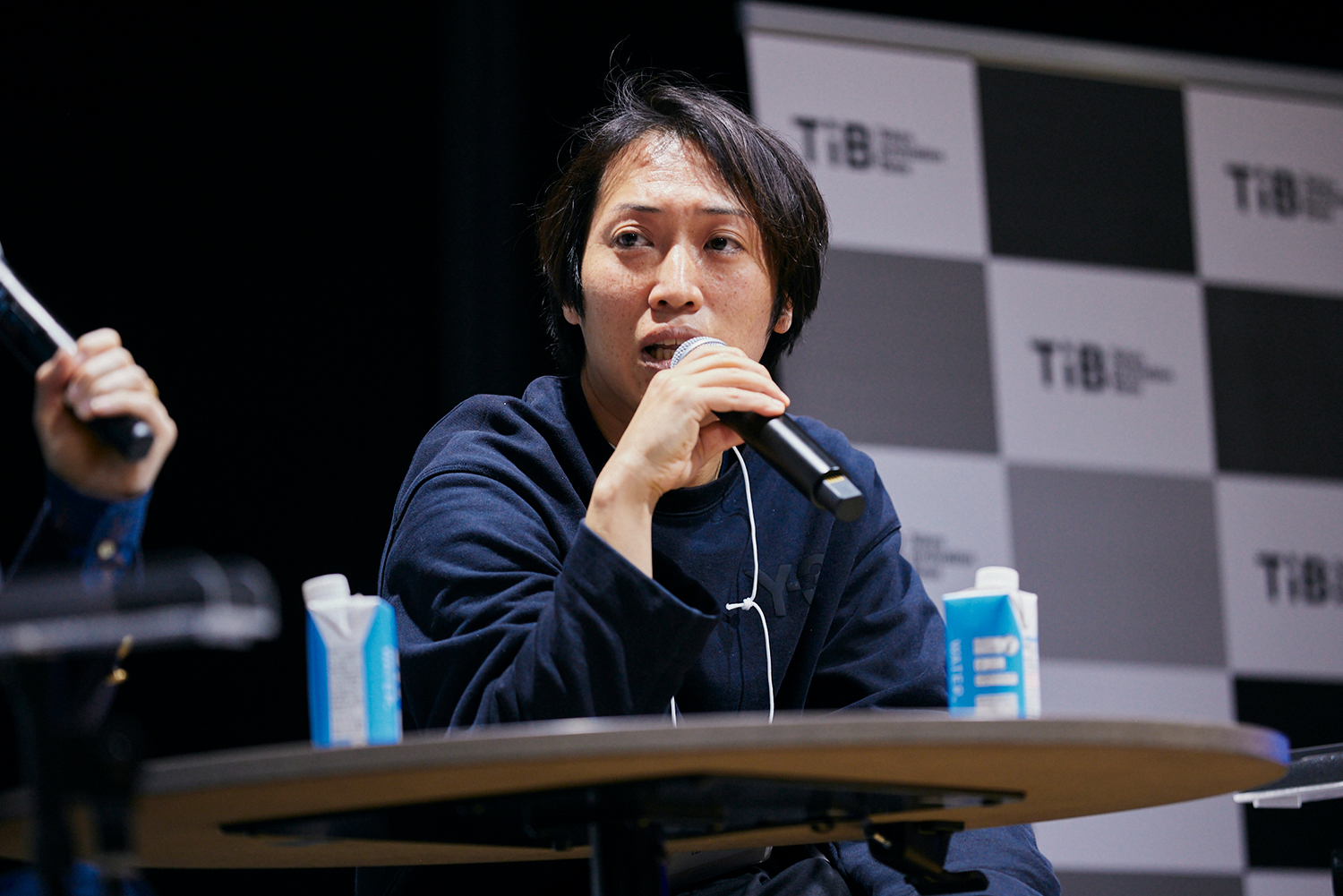
クリエイティブから仕組み、プロセスまで。拡張するデザインの対象
社会課題のクリエイティブへの落とし込みにおいては、関係者の選定やプロジェクトの進行方法など、プロセスの構築も重要になってくる。
企業のアイディエーションや組織文化形成の支援など、デザインの観点からさまざまな領域にアプローチする公共とデザインの石塚氏は、「産む」にまつわる価値観を問い直す展示『産まみ(む)めも』展を例に挙げ、プロセス構築の工程を説明した。
「まずはリサーチによるイシューの全体像の把握から始めることが多いです。『産まみ(む)めも』展では、不妊治療をされていて子どもを授かった方や授からなかった方、養子縁組を検討して実際に子どもを迎え入れた方、迎え入れなかった方、産まないことを選択した方といった当事者の方はもちろん、不妊治療の医師や看護師の方など、支援者側にもヒアリングをし、いろいろな視点から出産について全体像を考えていきました」


プレ当事者(=これから産む選択を控える人)の制作作品の一部
「全体像をある程度把握した後は、システムマップをつくっていきます。ここで言うシステムマップとは、リサーチでヒアリングした方々の言葉を起点としながら、社会を取り巻く複雑な問題がどのように関係し合っているかを視覚化したものです。つくったマップ全体を見ながら、『何歳までに結婚して子供を産む』といった空気感はどこから来ているんだっけ? といった問いと、それに対する仮説を立てていきます」

「誰の意見を入れるのか、選択がとても重要な時代になっている」
近藤氏と田村氏、石塚氏は、デザインの対象を可視化されたアウトプットだけでなく、仕組みやプロセスといった広い領域にまで拡張している点で共通している。しかし、デザインのアプローチ手法はそれぞれ異なるようだ。
近藤氏は「僕は伝えた先に何かしらの理解がある前提のもと、図解をつくっています。一方で、田村さんの『Dance with the Issue』は理解をさせるのではなく、電力に関するさまざまな人のインタビューの内容や、コンテンポラリーダンスがどういった意味を持っていたのかを観た人に考えさせる形で、僕とは異なる新しいアプローチだなと感じました」と分析する。
田村氏は『Dance with the Issue』の制作において、「共創型」のアプローチ手法を取ったと振り返る。
「今回の作品は、ステークホルダーに見せたい、といった意図がありました。そのなかでは、関係者の方と一緒につくっていくような手法が適切だと考え、制作をしていきました」と説明しつつ、「共創型はともすると内輪感も出てしまいます。一般的な映画として広めようとしたときに、どうすべきかはもう少し考えないといけないな、とも感じています」と思い返した。
石塚氏はデザインのアプローチ手法として、個人という単位への着目からスタートすることが多いという。「社会などの大きな単位で見ていくと、これが必要、こうしないといけないといった義務感が発生しがちですが、状況が変わったり、うまくいかなかったりしたときに挫折してしまうことも多い。自分がいま取り組んでいることや置かれている状況が、どう生活や社会に影響していくかという観点を意識すべきだとあらためて感じています」と語る。
個人にフォーカスしたデザインは、真実味が伝わりやすく、共感も生みやすいように見える一方で、誰に着目するかによってプロセスやアウトプットが大きく異なる可能性もある。
「何かを選んで形にすることはある意味とても不平等なことで、『可視化できるもの』にすると、良くも悪くも正しさが宿ります。誰のどのような意見を入れるのかという選択の方法がとても重要な時代になっていると感じています」と石塚氏は指摘する。

資金はリソースの1つでしかない。スポンサーとクリエイターの関係のあり方
誰の意見を取り入れるのかを考える際に、障壁の1つになりえるのがスポンサーの存在だ。
「スポンサーを入れることで、意見がスポンサー寄りになってしまうこともあります。一方で、作品のフラットさを担保しようとすると、経済性を維持するのが難しくなってしまう。バランスの取り方が非常に難しいなと感じています」と田村氏。
この課題に対して、ゼブラ企業への出資なども行っている阿座上氏は「資金を出す側が、どのような社会的変化の意図を持っていて、どうするために資金を用意するのかを考えないといけません」と出資側の意識の重要性を説いた。
「しっかりとお金を出す先のクリエイターたちと対話し、彼ら・彼女らのやりたいことと自分たちのやりたいことが合致しているかを確認すべきだと思います。もし意思が合致しているのであれば、クリエイターを最後まで信じるしかありません」
「資金も言ってしまえば一つのリソースでしかありません。ほかのリソースとどう公平に取り扱うのか、という点はプロジェクトリーダーの腕の見せ所ですし、最終的には共感を生み出すポイントになるのかもしれないと考えています」

第三者も巻き込んだ共感の波を生むには?キーワードは「ストーリー」「インセンティブ」「問い」
そして、社会にインパクトを与えるためには、課題の当事者だけでなく、第三者となる人々の共感を得る必要もある。当事者以外の共感を生むためには、どうすれば良いのだろうか。
この問いに対して、石塚氏は「当事者じゃない方にも何かしらの引っかかりはあると思っています。その引っかかりと社会で問題とされているものが関わりうるんじゃないかと思えるようなストーリーがあることが重要なのかもしれません」と回答。
近藤氏は「何かしらのインセンティブが必要なのではないか」と考察する。「政策や制度といったルールに切り込み、当事者以外の人たちも知らないと損をするという状況をつくり出すほどの大きな変化をもたらさないと、当事者以外の人たちを巻き込むのはなかなか難しいのではないかと考えています」と語る。

田村氏は『Dance with the Issue』の制作観点から、「誰もが共感できるところにアクセスするために問いをつくり、『これだったらみんなで話せませんか?』といった対話のスタートラインに立たせることを意識して今回の映画をつくりました」と説明した。

セッションの最後は、「デザインは社会とどう関われるのか」に対する3人の考えで締め括られた。
「デザインやクリエイティブの定義は、社会が複雑化することで広がっています。そのなかでは、ビジュアルのデザインといった表面的な部分ではなく、ルールなどの大きな仕組みにデザインがどう関わっていくのかが重要になっています。デザイン経営などの手法がすでに出てきていますが、デザイナー出身の官僚の方が出てくるなど、デザインと政策が関わるような事例が生まれていくと可能性が広がるなと考えています」と近藤氏。
田村氏は共創関係の重要性を強調した。「個々人の力は付いてきていますが、インパクトを生み出すためには、多くの人に関わってもらう必要があり、そのためには、作品を広く広げていかないといけません。受発注の関係ではなく、共創関係をいろいろな人たちと構築していくことが重要になってくると思います」
石塚氏は「踊り場」にたとえて語った。「最初は誰も踊らなくても、いいスピーカーや音楽があって、一人でも踊る人がいれば少しずつ踊る人の輪が広がるかもしれない。そうした場をつくることが重要になってきているなかで、場を仕立てたり、仕立てる方法を考えたりすることがデザインが手助けすることでできるのではないかな、と考えています」

