
[PR]新卒採用は地方美大がアツい。DeNAトップデザイナーがその可能性を語る
- 2019.03.11
- FEATURE
PR
しかし、DeNAデザイン本部の小原大貴さんは地方美大生の可能性を評価。優秀な人材を獲得するため積極的に地方へ訪れ、説明会やワークショップを開いている。実際、2017年、18年の『JAGDA学生グランプリ』で2年連続入賞を果たした勝森彩香さんも、沖縄県立芸術大学の4年生。「優秀な地方美大生」の一人だ。「地方だからこそ培える力がある」と熱を込めて話す。
今回は、そんな2人に「地方美大だから育つ可能性」「企業が地方を訪れる重要性」について語ってもらった。
- 取材・文:宇治田エリ
- 撮影:有坂政晴(STUH)
- 編集:服部桃子(CINRA)
Profile
小原大貴
株式会社ディー・エヌ・エー デザイン本部サービスデザイン部グループマネージャー。多摩美術大学情報デザイン学科を卒業後、大手代理店系Web制作会社でアートディレクター、UXデザイナーを経験した後、2016年DeNAへ入社。現在はサービス領域デザイングループのマネージャーと新規サービスのUXデザインに従事。地方美大での合同説明会の参加やワークショップの開催など、ポテンシャルがありそうな美大生と出会うべく、積極的に地方美大に向けたアプローチを行っている。
勝森彩香
大阪府出身。沖縄県立芸術大学にてデザインを専攻。グラフィックデザイン、イラストを中心に制作を手がける。『JAGDA学生グランプリ2017』優秀賞受賞。『JAGDA 学生グランプリ2018』入選。
グラフィックにとらわれない。幅広い技術を学べることが、沖縄県立芸術大学の魅力
—勝森さんは大阪出身とのことですが、なぜ沖縄県立芸術大学(以降、沖縄芸大)に入学したのですか?
勝森:私はもともと美術系の高校に通っていて、そこでグラフィックデザインを勉強していました。大学進学を考えたときに、4年間知らない土地で過ごしてみるのも面白いと思って、関西にとどまらず広い範囲で国公立の美大を探していたんです。
沖縄芸大では、デザイン専攻という広いくくりで、グラフィックデザイン以外にもさまざまな分野から授業を選択できることを知り、ここなら幅広い知識が身につきそうだと思って進学を決めました。

勝森彩香さん
—具体的には、何を学んでいたのでしょうか。
勝森:1年生のときは分野横断的に造形の基礎を学び、2年になってからはプロダクトデザイン系の授業を選択して革製品や木工家具などを制作しました。ほとんど初めての体験で大変でしたが、立体造形も「自分の考えを作品に落とし込む」という点においては、グラフィックデザインと同じだと学びました。
また、1年生のときは課題がそこまで多くなく、時間もたくさんあったので、空いた時間を使って自主制作を続けていました。
—勝森さんは2年連続『JAGDA学生グランプリ』で入賞されています。コンペティションに作品を出そうと思ったきっかけはなんですか?
勝森:私は何か制約があったほうが頑張れるタイプなので、コンペに出すという目的があれば作品づくりがより捗るかもしれないと思い、応募したんです。結果として賞をいただき、周りに認めてもらったことで自信を持てるようになりました。また、それまでは都市部の美大生に対するコンプレックスがありましたが、自分も彼らと同じフィールドに立っていると実感できたのも嬉しかったですね。
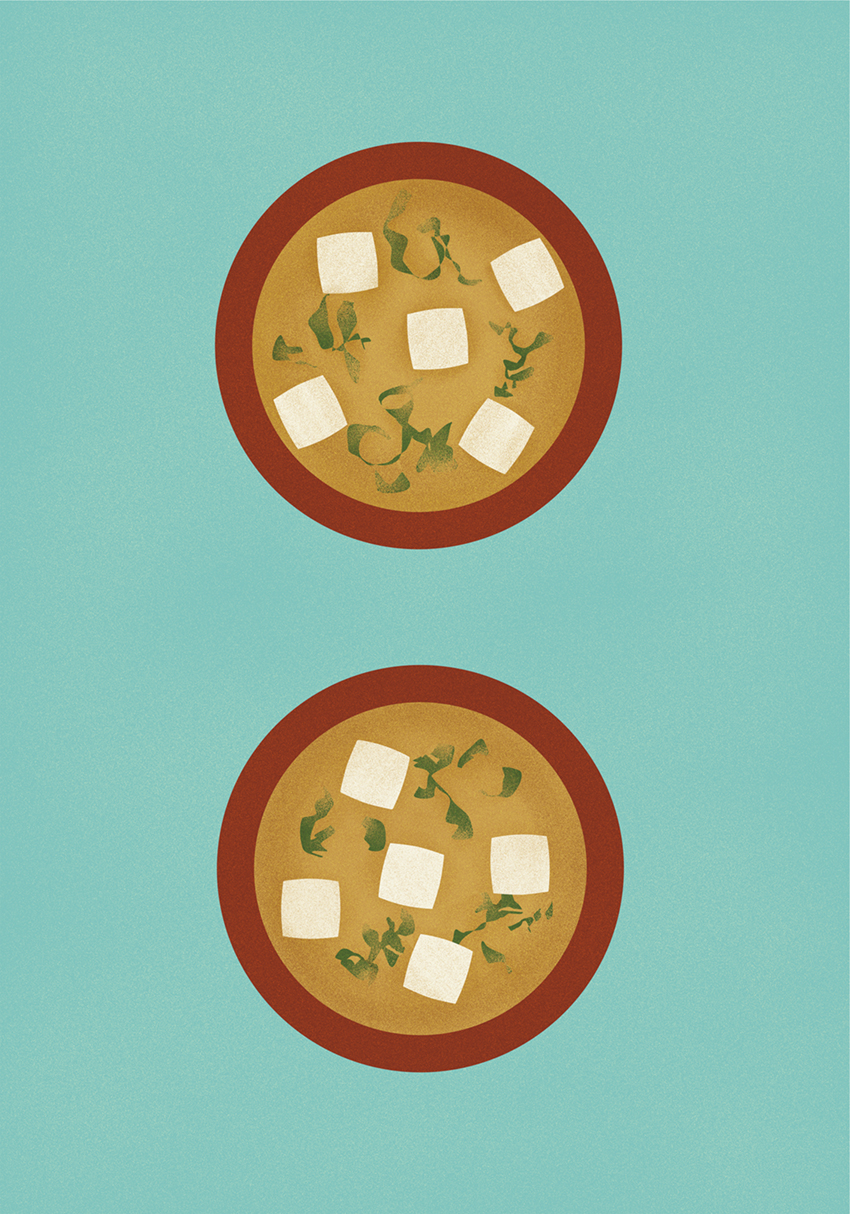
『JAGDA学生グランプリ2017』で優秀賞を受賞した勝森さんの作品(『みそしるコミュニケーション』)。「この年のテーマは『食』。食=コミュニケーションになると考え、親子の会話をイメージして制作しました。わかめが文字になっています」
―毎日の努力が実を結んだのですね。大学で学んだ経験も活かされましたか?
勝森:そうですね。高校からデザインを勉強していたものの、じつは「デザインが何より好き!」と言えるほどではありませんでした。でも、大学でめちゃくちゃデザインが好きな学生と知り合えて、彼らと「こんなすごい人がいるよ」「こんなすごい作品があるよ」と情報交換をするうちに、私自身もだんだんデザインが好きになっていったんです。
「自分ももっといいデザインができるようになりたい」「負けられない」という意識を持つようになったことも、受賞できた要因のひとつだと思います。
なぜ現地へ赴くのか? DeNAデザイナーが考える地方美大生の魅力
—地方美大にも勝森さんのように活躍している学生は多くいますが、企業が人材発掘のため積極的に足を運ぶことは少ないと聞きます。一方、小原さんはデザイナー採用のため、地方の美大へ行き説明会やワークショップなどを開催していますが、なぜそういった活動をしているのでしょうか?
小原:ぼくたちの会社では、インターネットやAIサービスを開発するUI / UXのデザイナーを新卒や中途で募集しています。しかし、現状ではUI / UXを学べる大学や学部が限られ、職種自体の認知度や歴史も浅いため、デザインを学んでいる学生がUI / UXデザイナーを目指したり、将来の選択肢にしたりすることが割合として少ない。弊社の場合も、思っていた以上に多くの学生に応募してもらうことが難しい状況でした。
特に地方の美大となると、企業や先輩からの情報も少ないため、学生は仕事内容の想像がしやすい広告業界に集中しがちです。「若手デザイナー不足」という課題は、弊社だけではなく業界全体が抱いていると思います。
そこでぼくたちは、UI / UXというデザイン領域があることや、その魅力を学生に伝え、ゆくゆくはインターネットサービスの業界にもっとデザイナーを増やすために全国各地の美大を回っているんです。現地では、UI / UXデザイナーがどんな仕事をしているかを説明したり、体験してもらったりするとともに、大学で学んできたことをどう活かせるのかを話しています。

DeNAデザイン本部 小原大貴さん
—地方と都市部とで、学生の考え方に異なる部分はありますか?
小原:身の回りの情報量の違いから、UI / UXの考え方に慣れている学生が都市部には多いという実感はあります。また、都市部には意識が高い学生が割合としては多く、ステレオタイプな意見かも知れませんが、地方には素直で素朴な学生が多い印象ですね(笑)。
ただ、根本のデザイン適性の部分は地方と都市部でそんなに違いはなく、どちらにしても優秀な学生はみんな初期のコンセプトづくりをすごく大事にしていると感じました。どちらにも有望な学生はいると思います。
勝森:私自身、UI / UXデザインという言葉は大学3年生のときに知って、最近やっとどういうものかわかってきました。沖縄芸大でもウェブの授業が最近始まったので、UI / UXも教えてくれたら、後輩たちの選択肢も広がるんじゃないかなと思います。
小原:ぜひぜひ、沖縄芸大からのワークショップのオファーお待ちしています!
- Next Page
- 企業が地方で説明会を開くことで、学生の選択肢が広がっていく
企業が地方で説明会を開くことで、学生の選択肢が広がっていく
—就職活動において、地方と都市部のあいだに情報格差はあると思いますか?
小原:最近は企業がウェブ上に求人情報を掲載することが多く、都市部の学生も地方の学生も自力で情報を探せるという点ではそれほど格差はないと思います。
勝森:でも、学生側としてはバリバリに感じていましたよ(笑)。CINRA.JOBが大学に来て合同説明会を開催するまでは、県外の就職先の情報はまったくと言っていいほど入ってこなかったんです。
沖縄芸大は1学年20人ほどなので、同級生だけでなく先輩ともよく話していましたが、東京の企業から内定をもらった先輩は少なくて。都市部の企業が気になっても、結局は自力で調べるしかない状態でした。

小原:たしかに先輩・後輩のネットワークって大切ですよね。「先輩があの会社行ったよ」というのは重要な情報源になりますが、そもそもいないとなるとかなりハードルが上がってしまう。
勝森:OB・OG訪問がなかなかできないので、大学3年の夏休みを使って、広告系の会社へ4社まとめてインターンに行けるプログラムに応募しました。そこで初めてデザイン業界について知ることができましたね。
—そう聞くと、地方の美大生は就活において不利なことが多いように思います。
小原:そうですね。インターンやOB・OG訪問のためにわざわざ東京に行かなきゃならないとなると、時間の面でも費用の面でもなかなかハードルが高い。逆OB訪問じゃないですけれど、企業側が地方に行き会社説明をして、「こういう道もあるよ」ということを伝える必要がありますね。
勝森:企業側が相談会やワークショップなどで地方に来てくれるのは、とてもありがたいです。実際に働いている人と話せるというのは大きいですよね。自分の技術が企業にどう活かせるのか、イメージもつきやすいと思います。
小原:じつは、初めて地方の大学に行ったとき、学生がぼくらの会社に興味を持ってくれるのか不安でいっぱいでした。でも、皆さん真面目に聞いてくれて、興味も持ってくれたようで嬉しかったです。もっと早く来ればよかったと思いましたね。
また、実際に話をしてみると、新しい領域だから敬遠するということはなく、「UIやUXはやったことないけれど、興味があったので説明を聞きに来た」という学生も多かった。興味があるのに、周りに専門的に教えてくれる人や先輩が少ないというのはすごくもったいないなと思います。

マイペースに学べる環境が、チャレンジ精神のある学生を生み出す
—地方にいたことで就活面での苦労があったとのことですが、沖縄芸大で4年間過ごしてみていかがでしたか?
勝森:あくまで想像ですが、もし都市部の美大に行っていたら、自分の積極性は生まれていなかったかもしれないなと思います。人が多い環境だと自分の個性が埋もれてしまいそうですし、自主制作に取り組む気力も湧かなかったかもしれません。その点、沖縄芸大では少人数で学べて自分の時間もつくれたので、いまの自分があるのかなと。
小原:同調圧力に負けてしまう可能性はあるかもしれませんね。地方美大はマイペースにデザインを学べるというメリットがありそうです。
—最後に、勝森さんが目指すデザイナー像を教えてください。
勝森:理想とするデザイナー像は、自分の技術の幅を広げるためにいろいろなことに挑戦しながら、一つひとつコンセプトをしっかり組み立てて、意思のあるものをつくっていける人。完成した作品に対して「ここにはこういうこだわりがあって」とちゃんと説明できる、心を持ったデザイナーになれたらなと思っています。
あとは、グラフィックデザインにとらわれず、テーマによってベストなかたちでアウトプットできるようになりたいです。なんでも屋さん的なデザイナーですね(笑)。

小原:ぼくの同世代を見ても、活躍しているデザイナーはみんなハートが強いんです。やると決めたことはやるタイプが多い。また、いろいろチャレンジしてみたいという姿勢は、特にデザインをやる人間にとっては重要です。いろんな視点に立てていろんなものの見方ができる人こそ、いま社会に求められるデザイナーだと思います。
こうしたポテンシャルを秘めた学生は、都市部も地方も関係なくいる。彼らを見つけるために、ぼくたちは地方に足を運び続けますよ。
