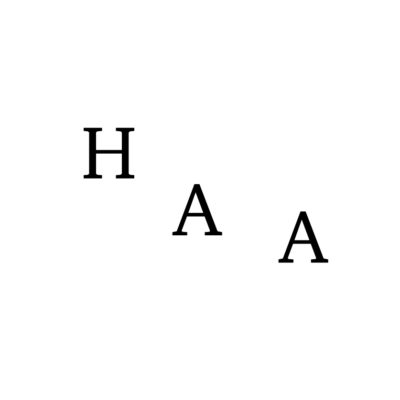リモートワークが定着した今、効率的に働きながらも温かいコミュニケーションをどう実現するか。
大分県別府市に本社を構える株式会社HAA(ハー)は、「深呼吸を届ける」をミッションとしたライフスタイルブランドを展開している。全員が基本的にリモートワークというHAAでは、月平均残業時間20分という驚異的な効率性と、お互いを思いやる企業文化を両立しているという。
そんなHAAが働き方に関するイベント『HAAの働き方〜深呼吸を届けるための、利他と効率〜』を開催した。今回は、イベントで感じたこと・考えたことを、編集者 / プロデューサーでありme and you, inc.代表取締役・竹中万季さんに綴っていただいた。
竹中さんの視点を通して、「優しさ」を持ちながら働くためのヒントが見えてきた。
- 取材・テキスト:竹中万季
- 編集:吉田薫
- 撮影:豊島望
ふと、リモートワークが当たり前ではなかった頃のことを思い出すことがある。朝、電車に揺られ、決まった時間に出社して、自分の席に着く。仕事で発生したちょっとしたトラブルを横にいる同僚に相談して、休憩がてら日々の悩みを立ち話していたら意外と長くなってしまったりして。提案していた案件がとれたときには「おめでとう!」と言い合ったりしていた、あの風景。
2020年、誰もが予想しなかったコロナ禍が訪れ、わたしたちの働き方は一変した。打ち合わせはZoomで行い、以前から使っていたチャットでのコミュニケーションはより浸透し、便利なツールがたくさん登場した。ここ数年で人と集うことが再び戻ってきたけれど、引き続きリモートの働き方は定着している。
私がCINRAで「She is」を共に運営していた野村と独立して「me and you」という会社をつくったのは、コロナ禍である2021年のことだ。ちょうど同じ年に生まれた「HAA」という会社がある。「日常に、深呼吸を届ける。」をミッションに、日々忙しく過ごす人たちに深呼吸を届けるためのプロダクトやサービスを提案している会社で、大分県の別府に本社を構え、東京、横浜、静岡などさまざまな場所で暮らしているスタッフと共にリモートで働いているという。

顔を合わせずに仕事ができるのは効率的だと感じることも多いけれど、どうしたら体温のあるコミュニケーションができるのか、誰もが未だ手探りをしている状態だと思う。そんななか、HAAではさまざまな工夫を凝らしながら、社員全員で「深呼吸を届ける」という思いをしっかりと共有しつつ、短い時間で効率的に働く取り組みを実践しているそうだ。
具体的に、どのような実践をしているのだろう? 期待と共に、HAAの働き方を伝えるイベント『HAAの働き方〜深呼吸を届けるための、利他と効率〜』に参加した。

5月15日に高円寺の『小杉湯となり』で開催されたイベント『HAAの働き方〜深呼吸を届けるための、利他と効率〜』。HAAとして社内文化を発信するイベントを開催するのは今回が初とのこと
忙しい日々で、心に余白をつくるために
HAAは、日本古来の養生法「湯治(とうじ)」に着想を得て立ち上がったライフスタイルブランドだ。日本各地の素材や伝統を大切にした製品やサービスづくりを心がけ、目まぐるしい日々だからこそ必要な「深呼吸のある暮らし」を届けている。
「お風呂に入ったときや、お茶を飲んだとき、素敵な景色を見たときに、『は〜』と言うことがありますよね。深呼吸をすると、心に余白ができるんです。余白ができると、自分を俯瞰できるし、まわりの人にも優しくできる。ぎすぎすしがちな社会のなかで、優しさが広がったらいいなと思っています」
代表の池田佳乃子さんは、もともとは映画会社や広告代理店で忙しく働いている会社員だった。コロナ禍前の2018年から東京と別府での二拠点生活を始め、地元である大分の鉄輪温泉でプランナーとして働き始めたことがきっかけで、それまで触れてこなかった湯治という文化、さらには湯治にとどまらない深呼吸を届けるライフスタイルをて広げていきたいという思いを抱き、HAAを立ち上げたそうだ。

代表・池田佳乃子さん
例えば、ギフトとしても人気だという『HAA for bath 日々』というプロダクトには、「ことばに包まれた入浴剤」というタグラインがつけられている。別府湯の花由来の天然成分を配合するなど、品質へのこだわりはもちろん、優しい色合いの包み紙には心が温まるような誰かの日常が綴られている。

『HAA forbath 日々』シリーズ。入浴剤の包み紙の裏には、さまざまな年代 / 職業 / ライフスタイルの「誰か」の日々を綴ったエッセイが掲載されている
忙しい日々で余白をつくるのは難しい。頭ではわかっていても、やらなくてはいけないことがたくさんある、と一息つくことさえ後回しにしてしまうときがある。こんなに忙しいのだからという気持ちは、自分を傷つけると同時に、誰かのことも大切にできなくする。そうした渦中にいると、自力で抜け出すことが難しく感じることも多い。そんなときに、ふと誰かがHAAのギフトを贈ってくれたとしたら、少しでも立ち止まることができるのではないだろうか。
深呼吸をどうしたら届けられるか。プロダクトはもちろん、ウェブサイトのデザインや写真、言葉選びの一つひとつに、一貫した思いが込められているのを感じる。HAAのブランドに関わる一人ひとりの真剣さが伝わってくるようだ。
深呼吸を多くの人に届けるために行っている、具体的な工夫とは?
イベントの司会を務める山本梨央さんは、以前はCINRA.JOBのディレクターを務め、現在はフリーランスとして活動しながらさまざまな会社の働き方に触れてきていた。HAAと仕事で関わるようになってからの印象として、「効率化がすごく得意」だと話す。
「深呼吸」をコンセプトにしているというと一見のんびりと働いていると思われることも多いそうだが、それとは反対に、仕事の間は効率的に全力で働いて成果を上げ、その分残業をしないなど、休むときは休む、働くときは働くというメリハリを大事にしているそうだ。「残業は一人あたり平均して、1か月で20分くらいです」という話を聞き、1日でなく、1か月で20分だということに驚く。
「というのも、業務時間が濃密すぎて、それ以上働けないんです(笑)。短距離走みたいな感じで。基本的にはみんなリモートワークなので、Slack、Notion、Google Meetを活用しています」
ツールを活用しながら行っている具体的な工夫について、たくさんのアイディアを共有してもらった。
Notionの情報共有から生まれる「自分が休んでも大丈夫な状況」
HAAでは情報がブラックボックスにならないように、社員全員が自分の仕事の棚卸しを行っている。フローやチェックリストが整理されることで属人的にならず、誰でも業務を行うことができるマニュアルが育っていく。新しいメンバーが入ってきたときにも共有がとてもスムーズだそうだ。一部の人が更新することになりがちなNotionも全員が更新していけるのは、「自分が休んでも大丈夫な状況を、自分でつくっていく」という社内文化が根付いていることも大きいのではないだろうか。
「Notionには、誰がどの時期にどのプロジェクトを行っているかまとめられているんです。相手の状況がわかれば、『休んで』といった声も掛けやすいですよね」
Google Meetでつくる声の掛けやすいオフィスのような空間
場所を共にするメリットの一つとして、声を掛ければすぐに相談ができるということがあると思う。HAAではその場にいる感じをオンラインで実現するために、少し話したいというときにGoogle Meetで5分だけつないで話すといったことも頻繁に行われているという。

イベントでは社内のSlackのやりとりの様子を少し見せていただけた。商談後の「お茶休憩」の様子を必ず投稿するメンバーがいるなど、気軽にコミュニケーションをとっている様子が伝わってきた
コミュニケーションを豊かにするために設けられた充実の制度
例えば、某テレビ番組から名前がつけられた「ごきげんよう」という毎朝開催されるミーティングの時間は、もともとはサイコロ形式でお題を決めて話すコミュニケーションの時間だったそうだが、現在はSlackで書くと長文になってしまいそうな日々の困りごとをシェアできる時間として設けられているそう。
また、金曜の14時以降を「HAA金」と名付け(こちらも華金から来ているそう、ユーモア!)、緊急でない限り打ち合わせを入れない日に設定。1週間の業務時間を超過しないようにするためのバッファの時間としても活用されているそうだ。
会うこともやっぱり大事。湯治で深まる「出社ウィーク」
HAAには2か月に1回、「出社ウィーク」という制度もある。普段はリモートで仕事をしているからこそ、顔を合わせるこのタイミングに、ブランドの方向性のディスカッションやレクリエーションの時間を設けている。
「一人でずっと家で仕事してると寂しいし、みんなで会いたいよねという話があって。いろいろやってみて、2か月に1回がちょうどいいねとなりました。会ったほうがお互いの状況もわかるし、その人のことをちゃんと理解できるから、リモートのときのコミュニケーションがスムーズになるんですよね。チームとしての心理的安全性も上がるので、相手のことを信じられるからか、仕事の効率がすごく上がるんです」
年6回行われる出社ウィークのうち3回は本社のある別府で行い、仕事の合間に温泉に入り、社員一人ひとりが湯治を実践しながら「深呼吸のあるライフスタイル」を経験しているという。「心と体を休めるという土台があってこそ、健やかに働けると思っています」と池田さんは話す。一人ひとりの生活リズムを尊重し、出社ウィーク中も解散時間は18:00。そのあとはそれぞれが自分のペースで過ごしているそうだ。

出社ウィークでの1枚
言語化して伝え合う、具体的な行動につなげる。思いやりを届けるSlackでのコミュニケーション
こうした制度が形骸化せずに機能しているのは、社内にお互いを思いやる心を持った人が多いことも影響しているという。話を聞きながら、ただ思いやる気持ちを持つだけでなく、思いやることを具体的な行動へと能動的につなげていく人が集っていることがHAAの特徴であるように感じた。そのなかでも、司会の山本さんがHAAと仕事をするなかで感じたSlackのやり取りの話が印象に残っている。
「例えば、仕事で誰かにサポートしてもらったとき、オフィスだったらささやかなコミュニケーションで補えるけど、フルリモートだと難しいシーンが多いですよね。HAAがうまくいっている秘訣は、Slackのやり取りの密度が濃いのに全然ぎすぎすしていなくて、すごく穏やかなところにあると思うんです。ちゃんと言語化して伝え合うことを大事にしていますよね」
Slackのコミュニケーションは難しい。私も常々感じている。いつでもどこでもスピーディなやり取りができて、話した内容がログとして残るところはいいものの、その場に居合わせれば伝わりそうなニュアンスが届かないせいで過剰にマイナスに受け取ってしまったり、余白が生まれづらいので「その仕事をする人」と「それをチェックする人」の一対一のやり取りになりがちだ。
HAAのSlackを覗いてみると、直接その仕事に関わっていない人も含め、7人くらいの人たちがメッセージや絵文字で反応をしている。「タグを付け忘れているみたいです」といった業務で抑えるべきところを抑えつつも、労いの声をかけたり、お客さんからうれしい感想が届いていることを伝えたり。そうした言葉のやり取りは、たとえデジタルでのコミュニケーションであっても温かいものとして心に届く。

HAA社員の内田ほのかさん。イベントではメインスピーカーの池田さん以外のメンバーも飛び入り参加した
「ブランドの思いをみんなで共有しているので、『自分の仕事はこれだから』と囲いを作らずに、サポートし合う、リスペクトし合うことを大切にしています」と池田さんは話す。未経験の領域のことをやらなくてはならないとき、お手本がないなかで手探りで行うからこそ、多くのことを吸収し、できることがどんどん増えていく。私自身も、大変だけど達成感があったそうした経験の一つひとつが、今の仕事を支えてくれているように感じている。とはいえ「そのほうが楽しいよ」「やりがいがあるよ」という言葉だけでは、未経験のことを進んで行いサポートしていく文化はきっと根付いていかない。
トークに飛び入り参加したHAA社員の内田ほのかさんは「HAAを取り扱ってくださっているお店の方が、『ご友人へのプレゼントに深呼吸を贈るのはどうですか?』と伝えてくれていることを知り、受発注の関係というより、HAAの世界を一緒につくる仲間が増えていく感じがしています」と実感をもって話していた。ブランドが叶えたい未来を社員全員でしっかりと共有していること。そして、お互いに思いやることができる環境の基盤があること。その二つが整っているからこそ、誰かに言われた仕事だけでなく、自発的な動きが生まれていくのだと感じた。

HAAでCCOを務める平岡季里子さん。池田さんとのPodcast番組『深呼吸できる女とできない女』でパーソナリティーも。
現在は入浴剤などのプロダクトを届けているHAA。入浴剤は、日本国内に留まらずオーストラリア・メルボルンでも発売が開始されているとか。みんなが深呼吸できるような社会に向けて、プロダクト、イベント、サービスなど形態は問わず、さらに広げていくことを考えているところだそうだ。そのなかで、ブランドを一緒に育てていく仲間を募集しているという。
「つくるものというより、時代や関わっている人たちと共に育っていくものがブランドだと思っていて。会社のメンバーや取引先の方、パートナー企業、お客さま、みんなと同じ船に乗っているような気持ちで育てていきたいですね。HAAという概念は世界共通で、例えば他の国の人からも『私の国のHAAはマテ茶だね』のように話してくれることもあって。これからは世界中に届けていけたらいいなと思っています」

『HAA for bath 小箱』。ギフトとしても愛されるHAA。プチギフト用として販売される小箱には『HAA for bath』を3袋が入っている
会社という小さな場所から社会へと、波紋のように広げていく
仕事は一人では行えない。今はAIも登場しているけれど、生身の人間である誰かとの関わりはケースバイケースで、決まり切った正解があるわけではないからこそ難しいし、一方でそうした関わり合いからしか得られない喜びもある。一日のなかで仕事をしている時間は長いからこそ、そこでの人との関わり合いは、生活、ひいては人生にも大きく影響していく。
「相手の仕事の進捗や業務量がわかるように仕組み化をしているから、思いやることができていると思うんです。何もない中では、なかなかできないですよね。情報が透明化されていたり、余白のある時間があったりすることで、自分の心にも余白ができて、だからこそ利他的になれるのだと思います」

HAAの取り組みを聞きながら、「人を愛するには技術が必要」だというエーリッヒ・フロムの言葉を思い出す。愛は自然と生じるのではなく、能動的な努力によって生じるもの。仕事環境において誰かを思いやることだって、きっとそうなのではないだろうか。すべて自然に用意されるものではなく、自分も含めて、みんなでああでもない、こうでもないと頭や手を動かしながらつくっていくものなのだということを実感した。
リモートワークをしていると、仕事に夢中になって時間があっという間に過ぎていく。まずは自分自身に余白をつくるために、心や身体を労ることが大切だ。例えば、ゆったりとお風呂に入ったりして、自分を愛するための土台をつくることで、初めて誰かのことを思いやることができる。そうした働き方、生き方を外に向けて提案するだけでなく、まずは自分たちがいる会社で実現する。深呼吸が循環する社会をめざして、まずは会社という小さな場所で実現していくHAA。この場から社会へと、波紋のように優しさが広がっていく未来を想像した。
Profile

私たちは創業以来、「日常に、深呼吸を届ける」というミッションを軸に、プロダクトやコンテンツの発信を行ってきました。「深呼吸して、心に余白ができる状態」をどのようにしたら生み出せるのか? 届けられるのか? ということを、日々考えながら事業を行っています。
私たちは、心に余白ができると、自分を俯瞰して見られるようになったり、他者のことに目を向けられるようになったりして、思いやりを持てるようになるのではないかという仮説を持っています。この仮説を、事業を通して世の中へ提案し、お客さまやパートナー企業、お取引先や応援してくださる皆さんと共創しながら、HAAのあるやさしい世界をつくり出していくことに、楽しさとやりがいを感じています。
これまでは別府の湯の花エキス由来の入浴剤「HAA for bath」や、入浴剤をエッセイで包んだ「HAA for bath 日々」シリーズを展開してきました。今年から、さらなる新しい商品のリリースや、深呼吸を届けるためのサービス開発も行っていく予定です。
本社は大分県別府にありますが、スタッフのほとんどが東京や神奈川、静岡、大分、熊本など在住のリモートワーク。2か月に1週間ほど「出社ウィーク」として別府や小田原、その他さまざまな場所で全員で集いながら、コミュニケーションを取るベストな距離感を探って働いています。
これから、私たちが目指す未来を一緒につくっていく仲間に出会えることを、楽しみにしています。
【Podcast「HAAの頭の中」】
HAAってどんな会社なの?どんな働き方なの?というリアルな様子を、Podcastでお届けしています。よろしければお聞きください!
https://open.spotify.com/show/1A8Ar7G5PkG7F9QakQxdxt?si=f1da88c2155749f6