
- 取材・文:宇治田エリ
- 撮影:豊島望
- 編集:川谷恭平(CINRA編集部)
ソーシャルイシューに対する姿勢を見せる。社会の変化を見据えた新たなフェーズへ
―2021年3月、CINRAは会社として初の「中期経営計画(2021〜2025年)」を制定したと聞きました。その軸には「ソーシャルxカルチャー」というワンブランド戦略があるそうですが、それを打ち立てた理由を教えてください。
加藤:これまでCINRAは、『CINRA』というカルチャーメディア事業と、メディアで培ってきたノウハウを活かした受託事業の2つを軸に、社会に貢献してきたという自負がありますが、一方 で、カルチャーに期待される内容にも変化が起こってきたと感じたからです。
ある時期から日本では、政治やソーシャルイシューに対して、著名人が積極的に言及することがめずらしくなってしまっていたという印象があります。しかし2018年ごろからでしょうか。アーティストやタレントなどのカルチャーにも関わってきた著名人が、SNSなどで声を上げるようになってきて。この傾向は、CINRAとしては大切にしたいものでした。

PDU(プロデュースユニット)のユニットリーダー / 取締役の加藤修吾。2012年東京大学大学院博士課程満期退学。同年、株式会社電通に入社。主にデジタルコミュニケーション設計やWebサイト制作・システム構築のプロデュースに従事。その後、営業として主に外資系食品メーカーのメディアプランニングを担当。2018年12月にCINRAに入社。事業部長としてストーリーブランディングをサービス化する一方で、社内組織改変の責任者を経て2022年1月に同社取締役に就任。
―社会に目を向け、発信することが「あたり前」になると感じたと。何か考えるきっかけにとなった出来事があったのでしょうか?
大石:たとえば「あいちトリエンナーレ 2019」で「慰安婦」をモチーフにした作品が設置されたことについては社内でも議論が起きましたよね。当時、CINRAでは発信に時間がかかってしまったという反省がありました。
著名人がソーシャルイシューに言及することがあたり前になってくるのだとすれば、当然企業側もソーシャルに対して何を考えているのか、そのポリシーを示すことがいままで以上に問われますし、自らの言葉で発信していく必要があります。

大石みづき。1987年生まれ。日本大学芸術学部演劇学科卒業後、大小の制作会社でWeb制作の開発・デザイン経験を積み2015年にCINRAに入社。Webエンジニア・テクニカルディレクターとして自社メディア・受託案件の開発を担当。中途入社した際の経験から、新しくチームに入ったメンバーに対する教育・育成の必要性を感じCINRAにオンボーディング制度を導入。エンジニアチームのマネージメントを経て、現在は多様な専門領域を持つメンバーが所属するXDU(体験デザインユニット)のユニットリーダーを務める。
―それはCINRAが行なう情報発信として、政治的な意見を持つことなのでしょうか?
加藤: 何かしらのイデオロギーに寄りかかるようなアプローチは考えていません。CINRAはあくまでもカルチャーをルーツに持ち、そのうえで取り巻くソーシャルを見つめ、つなぎ、考えていくメディアです。あまりにも差別的な内容や誰かの人権を脅かす案件だと判断したら、当然問題提起を示すべきだと考えていますが。
なにが正解かわからないなか、発信する内容を決定するのは、メディアの編集長に権限があります。現在の生田編集長に白羽の矢が立ったのも、ソーシャルイシューに対し、CINRAとしてなんらかの態度を示すことができると思ったからです。とにかく自分たちなりの見方でちゃんと見て、情報発信していくことが重要だと思っています。
「ソーシャル×カルチャー」を掲げる会社として、これからのCINRAが担うべきこと
―実際どのように中期経営計画をまとめていったのでしょうか?
加藤:3つの段階を踏んで考えていきました。まず、これからどういう世の中の変化が起こりうるのかを想定し、年表に書き込みました。次にそのなかでどういうチャンスやニーズが世の中で起こりうるのかを考えました。最後に、それらに対してCINRAが提供できる価値や強みを見つめ直しながらあてはめていきました。
そこで見えてきたのが、「ソーシャル×カルチャー」というキーワードだったんです。CINRAが「ソーシャルxカルチャー」という軸を打ち立てることで、企業の発信をともに行なうパートナーになれると考えました。
並行して、CINRAという会社が成長していくうえで、ブランドの認知と売上の双方を伸ばしていくためには、どのようなプロジェクトに力点を置くべきか、社員数はどのように増やしていくかといった、具体的な目標に落とし込んでいきました。

―具体的な目標を設定したことで、市場開拓のあり方も変わったのではないでしょうか。
加藤:「どの市場を狙うのか」という目的は、以前よりだいぶ明確になったと思います。先ほどお話ししたとおり、近年、企業にもソーシャルイシューへの態度表明が求められるようになってきた。それに伴い、企業がオウンドメディアを立ち上げる意味合いも、オウンドメディアが流行りだした10年ほど前とはまったく異なる重要性を持ち始めています。
オウンドメディア支援において、私たちは「CINRAメディアで培ったノウハウを活かし、企業のサポートができる」ことから引き合いをいただいていました。でも、いまは「オウンドメディアは、企業が自分たちの考えを直に発信できる場所として重要」と意義づけしたうえで、しっかりとアプローチできるようになったと思います。
もちろん、クライアントからは何かしらの社内会議を経て、目的を持ったうえでオーダーされるので、クライアントの希望をひっくり返すということはしません。しかしクライアントとチームとして足並みをそろえるという観点では、クライアントと共鳴できることが重要であり、そこでぼくらが「オウンドメディアが目指すべきこと」について理路整然と語ることができるようになるということは、非常に大きな前進だといえます。

―中期経営計画を策定する前と後で、ベンチマークの設定にも変化はありましたか?
加藤: 年商や従業員一人あたりの売上高を設定するために、ベンチマークとして具体的な会社名をあげることはありますが、会社のブランディングという観点では、ベンチマークを設定しなくなりましたね。
以前はクリエイティブエージェンシーやメディア関連の具体的な会社名をあげて設定していましたが、中期経営計画以降はCINRAらしいユニークネスを探求するようになりました。
ソーシャルイシューを発信することで見えてきた変化。クライアントから期待は?
―「ソーシャル×カルチャー」の軸を築いていくうえで、キーとなっている取り組みはありますか?
加藤:CINRAとビジネスデザインカンパニー「SIGNING」が共同で取り組んでいる「coe」というプロジェクトでしょうか。取りこぼされてしまいがちな、子どもたちや若者の小さな声と向き合い、変化の兆しをつくっていく企画で、CINRAの自社メディア内にページがあります。
SIGNINGが集めているさまざまなデータと掛け合わせながら、ステートメントと共に発信しています。また、そこから派生した企画として『ちいさなcoe』というPodcast番組も不定期で発信しています。

「coe 未来世代のちいさな声から兆しをつくる」のウェブサイト。モヤモヤと抱えている悩みや課題「マイ・マイノリティー」と、それを抱える人たち「サイレントマイノリティー」に焦点を当てることで、多様な時代の課題解決を進める取り組み(Podcast番組『ちいさなcoe』を聴く)
大石:文化庁、キヤノンマーケティングジャパンと協力して進めている、日本のまつり探検プロジェクト「まつりと」もそうですよね。現在、日本各地で地域の伝統行事がなくなりつつある危機があり、その背景には、コミュニティーがなくなっていくという大きな社会課題が隠れています。
「まつりと」では、祭りをとおして、地域とそこで暮らす人、地域にあるモノとのつながりや、それらを大切にする気持ちを再確認できるような取り組み、さらにお祭りが社会に存在する意義までプラスして魅力を発信しています。

日本のまつり探検プロジェクト「まつりと」のウェブサイト。文化庁の公開支援として、地域の伝統行事などの伝承事業を請け負うキヤノンマーケティングジャパンから受託
―「ソーシャル×カルチャー」を発信することで、クライアント側が変化してきているという実感はありますか?
加藤:CINRAらしい企画の出し方に信頼をいただいていることに加え、ソーシャルイシューに切り込む視点も期待されていると感じることが増えてきましたね。私たちも、中期経営計画に「こういう案件は積極的に受けましょう」という指標を設定しているので、カルチャー度の高いものや多くの人に変化を与えられる案件とマッチングできている実感があります。
今後はさらに、実績をつくっていくことで、自分たちがソーシャルイシューに対してどうリーチできているのかということも、積極的に外に出していきたいですね。とはいえ、まだまだこれからという段階なので、つくりながら考えて、外に出して反響を見て手応えを確認していくしかないのですが。
大石:計画をつくったからすぐにできるようになるというわけではないからこそ、いかに主体的に取り組んでいくかが大事なんです。これまでの強みであるメディア、イベント、動画制作の手法を取り入れつつ、クライアントが抱える課題の解決策を提案できる会社として信頼を獲得していきたいと考えています。

―求人の方では、CINRAのソーシャルイシューへの取り組みに共感して応募してくれる人が増えたそうですね。
加藤:とくに「coe」を見て応募してくれた方が増えましたね。また、CINRAの「JOB」の取り組みである「グリーンカンパニー認証制度」も注目されています。これは在籍する社員が自社を評価する制度で、会社の推しポイントが本当に基準を満たせているかというアンケートを取るものです。
「サステナビリティー配慮」「パーパスドリブン経営」など9つの項目があり、社員による評価が一定以上であれば認証バッジがつき、求職者から注目されるような仕組みです。こういった公平性のある取り組みにも、ソーシャルに対する意識が宿っていると思います。
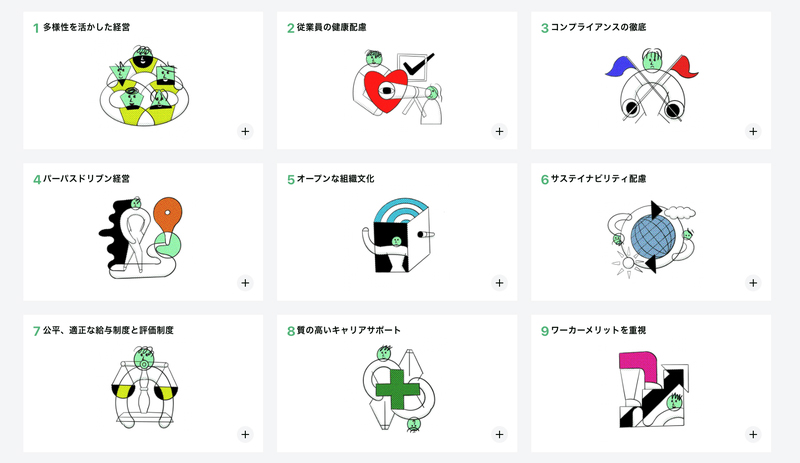
グリーンカンパニーの基準となる9つの項目。企業側が求職者に一方的によいメッセージを打ち出すだけでなく、そこで働いている従業員が会社を評価することで、各社のリアルな情報を届けることを目指す
たくさんの変化のなかで、社員たちはどう適応していく?
―ディレクターやエンジニア、デザイナーなどが所属するXDUのユニットリーダーとして働く大石さんは、最初に中期経営計画を聞いたとき、どのように感じましたか?
大石:私自身は大きく舵を取ったなと感じましたね。カルチャーシーンが好きでCINRAに入ってきた人も多かったので、ソーシャルへの方向転換は戸惑いが大きかったと思います。
また、社内には自社メディアのCINRAにまったく関わっていないメンバーも多く、そこでも反応は分かれたように思います。そのため、中期経営計画が発表された初期の段階では、私を含め多くの社員が理解の難しさを感じていたように思います。
―メンバーの意識を変えるために、チーム内ではどのような取り組みがされてきたのでしょうか?
大石:さまざまな制度をつくり、浸透を図ってきたので、細かくいうとキリがありませんが、たとえばCINRAが手がけた記事に対して、ほかの社員はどう感じたかを評価できる「VMI(ヴィジョン・ミッション・アイデンティティー)制度」を取り入れ、社内でも発信者と読者の関係性をつくり、全員がCINRAとつながりを持つことができるようにしました。
また、クライアントからの受託案件を中心に手掛けているメンバーと、自社メディアに関わっているメンバーとのあいだで相互にナレッジ共有できるような取り組みも最近始まりましたね。
そのほか、案件を振り返るレビュー会もしています。公開された案件について、クライアントの要望や納期などは考慮に入れず、担当者以外のメンバーやマネージャーが制作物に対して、どこがよくて、どこが悪いのか、感じたことを率直にフィードバックしています。

―やり方が変化していくなかで、軋轢は生まれなかったのでしょうか?
大石:多少はありましたね。レビュー会も、「もっと先に言ってほしかった」とか「なにも事情をわからないくせに」という感情は生まれたでしょうし。実際にメンバーからも、オブラートに包んだかたちでその思いを伝えられたこともありました。ただ、マネージャーの立場としては、次に活かすためにも、そこで「もっとこうしたかった」という悔しい気持ちを感じることも必要だとは感じていますね。
ほかにも、編集チームとプランナーチームは、お互いのカルチャーやソーシャルに対する関心を共有し、視野を広げるために、気になったニュースをピックアップして、ディスカッションする場を設けています。また、よりイノベーティブな考えができる社員を増やす目的で、抽象的なものや答えがないものに対して考える社内ワークショプの取り組みも始まってています。
―それらの取り組みの中で、見えてきた傾向はありますか?
大石:意外とみんな、ソーシャルイシューに興味があるんだなと感じていますし、昔のCINRAに比べてみんなの好きなものや関心も広がっていると思いました。人数が増えたことで、いろんな考えの人、いろんな好みの人がいることに気づけましたし、だからこそ、もっと意見を通わせていきたいと思うようになりましたね。
―いまのメンバーに足りないことはなんだと思いますか?
大石:批判も称賛も、率直にフィードバックしあえる関係でしょうか。お互いに気を使い合って意見を言えない関係になってしまっては、純粋にいいものをつくる集団でいつづけられないと思っていて。
加藤:批評的な視点はソーシャルイシューを考えるうえでとても重要ですよね。自分はどう考え、どういう社会であるべきか、本当にそれがいいことなのか。クオリティーを突き詰めていくために持つべき尖った視点は、ソーシャルに目を向けたときもちゃんと生かされるはずですし、大切な資質だと思います。

―変化のなかで感じる、CINRAメンバーのポテンシャルはどこにあると思いますか?
加藤:カルチャーだけに携わることに誰も疑問を持っていないなかで、経営メンバーは先手先手で「カルチャーだけじゃなくて、ソーシャルもやるんだ」と変えていっていますから、方針転換に戸惑うのは当然のことだと思います。そんななかでもCINRAのメンバーはみんなうまく対応していってくれて、とても感謝しています。
大石:現場は必死ですよ(笑)。実際にみんなすごく大変だと思います。これまで暗黙の了解でやっていたことをやめ、制度化した部分も多いので、とくに昔からいるメンバーにとっては「なんでわざわざ……」と大変に思うことも多かったと思います。でも、今後も新しいメンバーは随時入ってきますから、長期的にはルール化し、制度をつくった方がいいんですよね。そこは理解してくれていると思っています。
加藤:そこで一旦飲み込んで、対応してくれるところに、優しくて真面目な人が多いCINRAの特徴が現れているような気がしますよね。

社内イベント「ツキイチCINRA」の様子。2020年からCINRAは渋谷のオフィスを退去し、フルリモートに移行。フルリモートでも定期的に社員が交流するイベントを行なっている(写真提供:CINRA社員)
「世の中を本気で変えたい」。カルチャーをルーツに持つCINRAが描く社会のゴール
―大石さんご自身にも、変化の実感はありましたか?
大石:はい。いままでも一緒に仕事をする人たちのことを考えチームワークを意識してきましたが、人が増え、より多くの人と関わる必要がでてきたので、さまざまな考えの人たちがいろんな立場でいい仕事ができるようになるにはどうしたらいいかと考えるようになりましたね。その結果、チーム内だけでなく、CINRAとしてどういう方向に向かっていくべきかという視点も得られたように思います。
―今後、中期経営計画という一定のゴールの先に、どのようなCINRAを見出していきたいと考えていますか?
加藤:中期経営計画は、カルチャーや芸術を楽しみ、大切にする気持ちを根本に持つ集団が、「大人」になっていくための道のりだと思っています。業界のなかに目を向けていたところから、もっともっと外に向けてワクワクを共有し、いろいろな人が一緒に語らう光景が広がっていく。
そういう場をつくれるようになると、また違う目線になれると思いますし、個人個人が意見を言える社会をつくりたいと考えたときに、CINRAはそれをリードする集団になれるはず。今後もステージを上げていきながら、手をつなげる人を増やしていきたいですね。
―最後に、CINRAで働くことを考えている方へ向けて、メッセージがあればお願いします。
加藤:世の中も、自分自身も、本気で「変えていきたい」と思っている人に来てほしいですね。そういう方であれば、いま取り組んでいる仕事がどのように世の中のためになるのか、自分で見つけられるはずですから。また、チーム編成も流動的ではありますが、その変化のなかでもチームで試行錯誤し、課題に前向きに取り組める人は向いていると思います。
大石:チームのなかでも自分らしさが発揮できて、楽しめるって重要ですよね。逆に、誰かに言われたままに行動する方がいい人は多分やりづらくて、いろいろな人がいるなかでも「自分はこうしたい」って意見が言えて、チームをよくするために話し合える人は楽しく仕事できるんじゃないかなと。
CINRAは個人の意見にも向き合う会社だからこそ、みんなで話し合いながら、変えていくために一番いいかたちを探せるはずです。

Profile
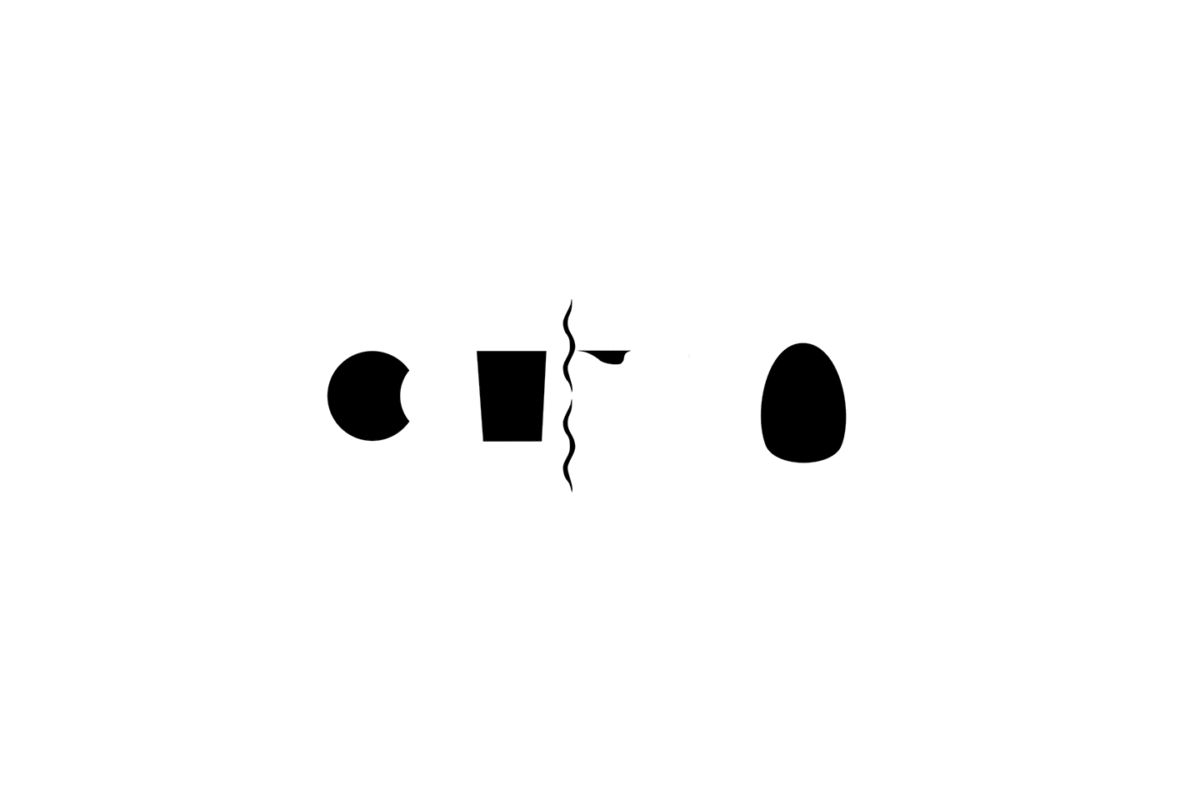
平素より弊社の採用活動にご関心をお寄せいただき、誠にありがとうございます。
恐れ入りますが、下記の期間中は冬季休暇に伴い、採用業務を一時休止させていただきます。
【採用業務休止期間】
2025年12月24日(水)~2026年1月4日(日)
休止期間中にいただいたご応募・お問い合わせにつきましては、1月5日(月)より順次対応させていただきます。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
ーーー
CINRA, Inc.(以下、CINRA)は「人に変化を、世界に想像力を」をミッションに掲げるメディアカンパニーです。私たちはこのミッションを実現するため、さまざまな仕事をしています。
たとえばメディア「CINRA」の運営、クライアント企業の声を伝えるオウンドメディアの制作・運営や、ブランディング、リアル / オンラインイベントの企画・プロデュース・運営などなど。そういった私たちの事業のすべてが、「人に変化を、世界に想像力を」というミッションとつながっているのです。
もちろん、自分たちのミッションだけが実現できればそれでいい、というわけではありません。2003年の開設以来、私たちはアーティストやクリエイターをはじめ、官公庁や教育機関、文化団体、ナショナルクライアントからベンチャーまで、国内外の多種多様な人々の思いや、問題意識に耳を傾けてきました。それらの声を丁寧に束ねて編み、ストーリーやデザイン、WEBサイトといったかたちにすることを通じて、人に変化を与え、世界に想像力をもたらす。私たちはそれを目指して仕事をしています。
そんなCINRAには、編集者やWEBディレクター、プランナー、デザイナー、エンジニアなど、さまざまな職種のメンバーが集まっています。プロジェクトは職種間でコミュニケーションを取り、連携しながら進めているので、1つの職種だけで閉じているわけではありません。2021年10月には自社のメディアブランドを統合し、全社で協力し合いながら、1つの新しいメディアをつくり上げる経験もしました。
CINRAでは、出社を基本としつつ、リモートワークも組み合わせたハイブリッドワークを取り入れています。コミュニケーション不足を解消するために、チーム間の垣根を越えたイベントを開催したり、気になることを話し合う時間を設けたりしています。メンバーの年代は幅広く、子育てをしながら働いている人も。副業も条件を満たせばOK。働き方はさまざまです。
私たち自身も変化し、想像力を養いながら、人々の声や思いを媒介し、社会に接続していきたいと考えています。共感してくださる方、ちょっとでも興味のある方、ぜひご応募ください。
【メディアブランドCINRA】
「クリエイティブな意思を、他者に届ける」
2003年開設の芸術文化をルーツとするメディアブランド。一人ひとりの情熱や違和感、問題意識に耳を澄ませ、社会や文化に好奇心を抱く人に向けて、思いを媒介するメディアとして2021年にフルリニューアル。
https://www.cinra.net
【実績】
コーポレートサイト上で、過去の実績(一部)を公開しています。どうぞご覧ください。
https://www.cinra.co.jp/work
【採用ピッチ資料】
沿革、事業内容から働き方、評価制度のことまで、さまざまな角度からCINRAを紹介する採用ピッチ資料「Greetings」を公開中です。
https://speakerdeck.com/cinra_hr/cinra-inc-greetings-ver-dot-1-2-cai-yong-pitutizi-liao
【記事コンテンツ】
コーポレートサイト上で、社員インタビューや社内の取り組みなどを紹介する記事を掲載しています。
https://www.cinra.co.jp/joinus


