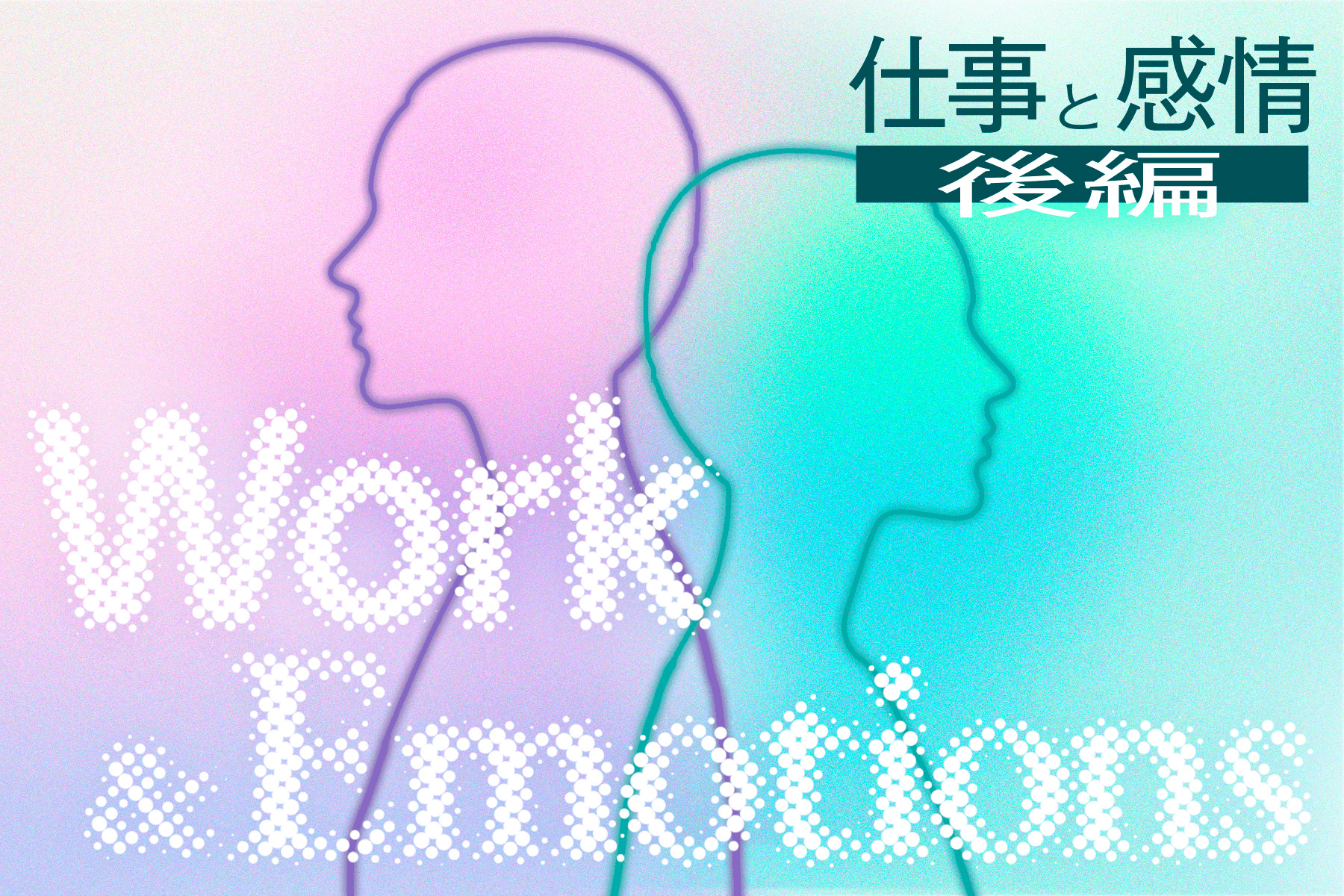
弱音を吐くことすら難しい、仕事でも「人間性」が求められる社会への違和感。社会学者・山田陽子インタビュー
- 2025.05.21
- COLUMN
感情労働、EQ、自己分析、MBTI……現代の働く環境では、性格や感情といった「人間性」までもが評価の対象となりつつある――そう感じている人が、少なからずいるのではないだろうか?
本記事では、「感情資本主義」や「感情労働」など、感情と社会の関係性を研究している社会学者・山田陽子先生にインタビューを実施。前編では消費社会のなかで「感情」がどのように扱われてきたのかをお話いただいた。
後編の本記事では、人間性が過剰に求められる現代の働き方や、感情が資本化されていく現代社会のあり方、さらには自分を守りながら働くヒントについてまでを聞いた。
※前編はこちらから
- インタビュー・テキスト・編集:妹尾ちあき
「ガクチカ」「MBTI」……仕事に人間性が求められるようになった
ー山田先生の著書『働く人のための感情資本論―パワハラ・メンタルヘルス・ライフハックの社会学』で、職場では感情の表出がネガティブに評価されるという指摘がありました。それはどうしてなのでしょうか?
山田:現代社会では、感情をコントロールできることが一人前の社会人であることの要件になっていると思います。そもそもわたしたちは日頃から、「感情規則」にならい演技をしています。感情規則とは、お葬式では悲しみや人を悼む気持ちを表現するとか、結婚式であれば喜びやお祝いする気持ちを表現するというように、ある社会的な場面で「どのような感情が必要とされているのか」を決めている目に見えないルールのことです。私たちは誰しも、この目には見えないけれども強い拘束力をもつルールの中で生きています。感情規則は、場面や状況によって変化するような微妙で繊細なものです。そのため、集団の中で悪目立ちを避けようとすれば、それを慎重に読み解くことが求められます。
このルールがある中で、社会的場面にフィットしない感情はノイズとして扱われ、無かったことにされたり、排除されたりします。労働の場面では、表面上はとりつくろっても、心のうちでは相反する感情を抱きながら仕事をして疲弊し、バーンアウトしてしまうこともあると思います。
一方で、感情というか全身全霊をつぎ込んだ結果としてとても良いアウトプットが生まれることもあるので、必ずしも悪いことばかりとは言えないのですが。

山田陽子(やまだ・ようこ)
社会学者。大阪大学大学院人間科学研究科准教授。博士(学術)。単著に『ポスト・ヒューマン時代の感情資本』(De-Silo Label Books, 2024年)、『働く人のための感情資本論―パワハラ・メンタルヘルス・ライフハックの社会学』(青土社,2019年)、『「心」をめぐる知のグローバル化と自律的個人像―「心」の聖化とマネジメント』(学文社,2007年)、編著に『社会学の基本-デュルケームの論点』(学文社,2021年)など。日本社会学史学会奨励賞受賞(2007年)。
山田:いずれにしても、いまの時代、仕事と人間性が強く結びつく傾向にあると思います。仕事をただの仕事として割り切れない状況ですよね。
キャリア教育を見ても、幼い頃から「やりたいことは何ですか」と問われて、子どもたちはなんとなく「お昼寝」「お散歩」と答えてはいけないような空気を感じ取ります。やりたいこと=職業を答えねばならないという見えない規範を肌身で感じ取りながら育ち、就活では自己分析をして、ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)やこれまでの生き方と自身の人間性がいかにその会社での仕事に役立つのかを面接で語りますよね。
就活から逆算して学生時代を組み立て、ガクチカのために留学やボランティアをするというような本末転倒も生じています。
また、MBTIのような性格診断も流行っていますが、自分や他者の性格を記号化してしまうことにみんな慣れ過ぎているのではないでしょうか。性格診断で自分の人間性を語ることや、血液型や星座も同じですが、自分がどういう人間かを深く考えているようでいて、実際は極度に単純化・記号化して思考停止しています。隣の人がどんな人なのか、自分がどんな人間なのか、記号による分類やキャラ設定をすることで安心し、それ以上深く考えずに予定調和を生きているのではないでしょうか。

Photo by Glenn Carstens-Peters
共感力がある人ほど営業成績が良い? 「いい人」が求められる背景
ー複雑な人間性を、わかりやすさのために安易に言語化してしまっているということですね。近年では、一定のコミュニケーション能力・共感力があるような人物像が求められているように思います。
山田:日本では1996年に出版された『EQ:こころの知能指数』(ダニエル・ゴールマン著)がベストセラーになりましたが、その頃から感情的なもの・人間的なものが社会的スキルや職務遂行能力に含まれることが顕著になったように思います。EQ(心の知能指数・感情知能)が高いセールスパーソンほど営業成績が良いという調査研究がなされたりもしました。
「科学的」な言説が規範と結びつくことがあります。「こういう性格のセールスマンは、営業成績が良い」ということが「客観的事実」として発表されると、現場は「生産性を上げるために、〇〇な性格の人を採用すべきだ」と考え行動しはじめます。仕事を遂行する能力の評価が、人間性や生き方を評価することに近づく昨今、私たちの社会がどのような感情や人間性を高く/低く評価し、何を排除しているのか、注意深く見ていく必要があるでしょう。
社会学者のエヴァ・イルーズは、20世紀を通じて尊敬されるリーダー像も変化したと指摘しています。リーダーシップを兼ね備えながら、共感的であるとか、部下に寄り添うEQがあるような管理職や経営者が求められるようになってきました。
ー性格診断やEQ診断などを通じて、特定の人物像が求められるようになることで、社員の個性が均一化されていき多様性が損なわれる危険性もはらんでいるように思いました。
山田:性格診断で同じタイプの人を集めたところで、よくよく見たらやはり人間は多様だと思うんですね。何パターンかで分類できるはずもない。ですから、そういう意味ではあまり心配することもないかと思います。ただ、そのレッテルがレッテルであることを認識し、何のために貼られるのか、社会の中でどのような意味を持っているのかを絶えず疑うことは必要だと思います。
感情も資本化されていく社会のなかで、どのように働くか
ー以前『De-silo』のインタビューで山田先生は感情が資本化されることへの危機感について言及されていました。労働現場、家庭以外でも日常的に感情が資本化されている事例について教えてください。
山田:そうですね、日々の暮らしにかかわることで言えば、「応援消費」があります。被災地や特定の農家や企業の生産物を応援するような消費行動です。応援消費は、社会課題の解決に向けた倫理的で持続可能な「エシカル消費」と、アイドルやアニメのキャラクターをファンとして応援する「推し消費」の二つの要素がありますが、いずれにしても、商品にまつわる理念や物語を生産者側とユーザーで共有し、共感やリスペクトや愛着にもとづいておこなわれる消費です。消費を介して、ある種のコミュニティが形成される点も特徴的です。
このような動きは、これまでの大量生産・大量消費・大量廃棄とは異なる消費の形態と言われていますが、倫理や共感や人と人との結びつきさえも、商取引の文脈に取り込まれたということでもあるでしょう。働くことに感情や人間性を投入することが求められる一方で、共感や尊敬や他者とのつながりがどんどん商業ベースになっているように思います。

『De-Silo』でのインタビュー。「「感情」すらも資本化されていく時代に、「働くこと」と「癒し」を問い直す──社会学者・山田陽子」
ーなるほど……感情やつながりまでもが資本に絡めとられてしまっているということですね。仕事をするうえで、良いものを生み出すだけでなく常に全方位から人格も問われるのは息苦しさを感じる人もいるのではないかと考えます。自分を守りながら働くためのアプローチがあれば教えていただきたいです。
山田:社会のありようを客観的に観察しつつ、同じような状況にある人たちと悩みや疑問を共有することが重要です。
現代は、仕事に人間性を問う社会になっている印象があります。ある一定の方向性の人間性――感情のまま泣いたり怒ったりしない、ポジティブで協調性があり、クリエイティブで快活だけれども気分の変動が少ない、穏やかさや共感力をもつ人―― が求められる傾向にあるのではないでしょうか。そういった社会では正当な怒りや悲しみでさえ認められず、和を乱す行為として退けられるかもしれません。働くことを通して社会とつながることが多い現代人にとって、こうした事態はなかなか辛いことでもあるでしょう。
でも、同じように感じたり、悩んでいたりする人はいるはずです。「感情や人間性にかかわることだから、自分一人の個人的な問題だ」と考え、自分を責める人もいると思います。ですが、いまの社会のしんどさは、決して一人だけのものではありません。皆が多かれ少なかれ感情資本主義のうねりに巻き込まれており、共通の問題を抱えています。同様の悩みや疑問を抱えている人とつながり、発信や共有を通して共に考え、この社会の問題として可視化することが大切だと思います。
