
私たちは「感情」を売買している――感情労働はいかにして生まれたのか?社会学者・山田陽子に聞く
- 2025.03.31
- COLUMN
「感情をコントロールできるようになれ」
働くようになってから、この類の言葉を言われたことがある人は、少なからずいるのではないだろうか? 最近では、組織のリーダーにはメンバーの「感情管理能力」が求められたり、社員向けにアンガーマネジメントやレジリエンスの研修が実施されたりすることもあるなど、労働環境において「感情」がフォーカスされる機会が増えている。なぜ「感情」が、いま労働分野においてホットなトピックなのだろうか?
近年、「感情労働」という概念が注目を集めている。感情労働とは、適切な態度や言葉遣い、そして喜びや楽しさといった適切な感情で顧客と接することが求められる労働を指す社会学の用語である。
この記事では、社会における感情の有様に注目する「感情社会学」の領域で活躍する、大阪大学大学院人間科学研究科准教授の山田陽子先生にインタビューを実施。社会における感情の歴史、また人間性が過剰に求められる現代の働き方について、前後編に分けてお届けする。
前編では感情労働を詳しく知る前段階として、社会学で「感情」がどのように扱われてきたのかをお話いただいた。本題である後編の内容をより深く理解するためにも、ぜひご一読いただきたい。
- インタビュー・テキスト・編集:妹尾ちあき
社会学から紐解く、「社会」と「感情」の関係性
社会学の概念である「感情労働」。山田先生に感情労働という概念が誕生した背景についてお話していただいた。もともと社会学は、社会と個人の関係について考えてきた学問だが、感情はメインテーマではなかったという。
山田:社会学は、社会と個人の関係や結びつき方について考えてきた学問です。さまざまな理論がありますが、たとえば、フランスの社会学者エミール・デュルケームは、社会は個人の単なる総和ではなく、「一種独特の実在」だと言っています。
私たちは生まれてくる社会を選べないですよね。時代も親も選べない。個人一人一人が死んでしまっても、社会は続いていきます。身近な人が亡くなって自分は喪失感に打ちひしがれているのに、テレビをつければバラエティ番組がやっていたりして、まるで何事もなかったかのように日常が続いている……個人の気持ちがどうであろうとも、それとは別に「社会」というものが存在している、つまり、個人と社会は別個のものというのが社会学の基本的な考え方です。
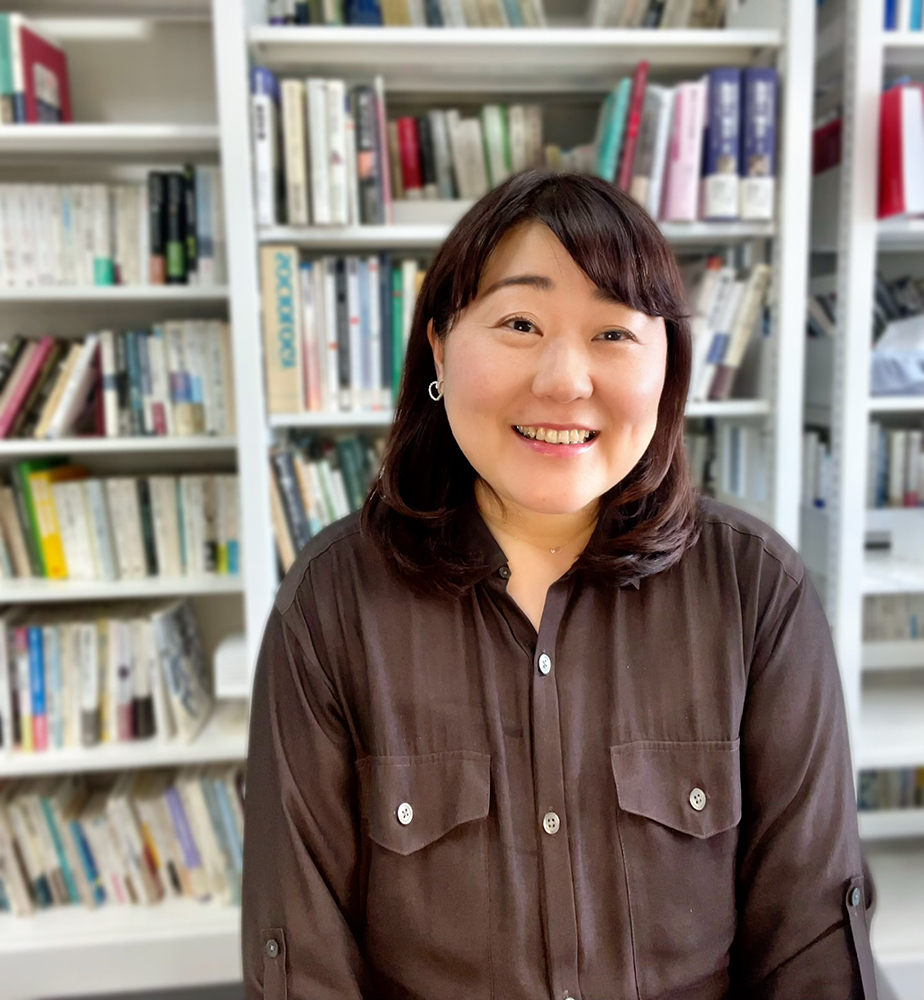
山田陽子(やまだ・ようこ)
社会学者。大阪大学大学院人間科学研究科准教授。博士(学術)。単著に『ポスト・ヒューマン時代の感情資本』(De-Silo Label Books, 2024年)、『働く人のための感情資本論―パワハラ・メンタルヘルス・ライフハックの社会学』(青土社,2019年)、『「心」をめぐる知のグローバル化と自律的個人像―「心」の聖化とマネジメント』(学文社,2007年)、編著に『社会学の基本-デュルケームの論点』(学文社,2021年)など。日本社会学史学会奨励賞受賞(2007年)。
山田:デュルケームが社会学を確立したのは19世紀後半です。近代化や都市化が進み、個人主義的な考えが浸透する一方、宗教や地域や家庭など、それまでに人々を結び付けていた絆がゆるんでいく激動の時代。共通の価値や道徳が見えにくくなる中で、社会と個人はどのような関係にあるのかをデュルケームは問いました。たとえば、『自殺論』では、孤立し孤独を深めた個人の自殺(自己本位的自殺)や、道徳による規制が緩み、個人の欲望が肥大化することによる自殺(アノミー自殺)について論じています。自殺という最も個人的なものに見える行為についても、宗教や道徳、政治、家族といった社会的要因や背景から考えてきたんですね。
消費社会へ変化するなかで生まれた感情労働
山田:このように社会学の歴史のなかでは、感情はメインストリームにあったわけではありません。そうした中で、A.R.ホックシールドという社会学者が、1970年代の終わりに「感情規則」や「感情労働」について論じはじめました。感情規則とは、状況や場面に応じて、どのような感情をどの程度の強さで感じ、表出すべききかを規定するルールですが、みなさんも思い当たることがあるのではないでしょうか。よく、「空気を読む」と言いますよね。空気は目に見えませんが、暗黙裡のうちに、みんなそれがあることを理解して、それに沿うふるまいをしています。今自分が実際に感じていることとは異なるものだと自覚しつつ、感情規則にあわせて、その時その場で求められている感情を装う、もしくは本当に感情を書き換える。こうした感情規則にもとづく感情マネジメントというのは、日常生活において誰しもがおこなっていることです。
70年代以降、消費社会化が進む中で、人々の働き方や消費のありかたも変化していきました。それにともない、感情規則と感情マネジメントが賃労働の中に組み込まれていきます。それが「感情労働」です。
消費社会へと変化するなかで、ものを「作る」仕事だけでなく「売る」仕事、いわゆる営業職のような職種の割合が増えていき、「感情労働」は生まれた。当然、消費活動にも変化があった。

Photo by Alexander Faé on Unsplash
山田:消費の場面では、従業員が顧客のライフスタイルや好みを探りながら、その人に最適なものを提案して自社の商品をすすめることも増えていきます。
1900年代初めにT型フォードが爆発的に売れましたが、それまで車を持っていない人たちにとって、車が自分にも買えるということが喜びでした。そのため、「自分もみんなと同じ車が欲しい」という横並びの購買意欲が顕著でした。一方で、消費社会化が進むと、「人と違うものが欲しい」という個性やオリジナリティを求めることが増え、「この商品を手にすることで、素敵なライフスタイルを実現できる」というように、多様な選択肢の中から自分にフィットする商品イメージや物語、ライフスタイルの型を選び取ることで自分を創る時代になっていきます。
ライフスタイルや価値観を深掘りして商品を売るためには、「コミュ力」が求められ、それは感情労働につながっていったという。
山田:従業員には、顧客とコミュニケーションを取りながら、一人一人の価値観やライフスタイルにあった商品を提案することが求められるようになります。その際に仏頂面をしているわけにもいきませんよね。「今日は本当は疲れているけど…」という時も自分を奮い立たせて、ポジティブな感情をつくりだし、笑顔で親切にふるまうこともあるでしょう。
このように、労働者が自分の感情を操作して、場面にフィットする感情を作り出し、それを商品として提供することで顧客に満足感を与える労働を「感情労働」といいます。顧客が買っているのは、商品そのものだけでなく、それが提供される際の笑顔や親切さといったサービスを含めた「商品」です。
2000年代には、イスラエルの社会学者エヴァ・イルーズ(ヘブライ大学社会学部教授。資本主義と感情、感情社会学を専門領域とする)が「感情資本主義」や「感情商品(エモディティ)」という概念を提唱し、労働者だけでなく消費者の心のありよう、現代人の感情のありよう自体が現代資本主義に絡み取られていくプロセスを分析するようになりました。

Photo by Tristan Colangelo on Unsplash
山田先生は付け加えて、現代において感情は労働だけでなく消費の対象にもなっていると話す。
山田:現代では、街を歩けば感情を揺さぶってくるもの、感情に働きかけてくるものにあふれていますね。「ホッとしたい」と思ってカフェに入るとか、「怒りっぽい自分を変えたい」と思ってアンガーマネジメントの研修に行ってみるとか、感動したいから映画を観ようとか……さまざまな形で、今の自分やメンタルの状態にどのような変化が起こるかを予測して商品やサービスを購入し、実際に商品やサービスを使用・体験する過程で感情変容や自己変容が起こって満足する、といったことがしばしば見られます。モノ消費やコト消費、応援消費など、さまざまな消費の形態がありますが、モノやコトの購入や消費を通して、予測した感情を得たり、自己変容(の約束手形)を買ったりすることが日常の風景になっています。このように、消費者の感情や自己変容が商品の一部として組み込まれている商品群について、イルーズは「感情商品」と呼んでいます。リアルな気持ちや自分らしさが消費を通して立ち現れる。この視点は、現代人の感情や自己について考える際にとても重要なものです。
職場だけではない。家庭内の感情労働
山田:感情労働や感情商品は、家庭内でも見つけることができます。私的な領域では、無償の愛、自己犠牲、自己献身などが美徳とされてきました。愛はお金には変えられない、と信じられてきたと思います。
性別役割分業が当たり前だった時代、女性は家庭内で家事育児を丁寧にすること、男性は外へ出て働いて稼ぐことが家族に対する愛情の証とされてきました。「男は黙って◯◯◯」というフレーズが象徴的ですが、愛情表現をしなくても黙々と働いてお給料をきちんと家族に渡すことが愛情の証と見なされていたのです。
しかし、男性が一家の大黒柱だった時代は過去のものとなったいま、結婚や家庭の在り方が大きく変化しつつあるという。
山田:1980年代ぐらいから、親密な関係のありかたにも少しずつ変化が生じます。お互いの本音を伝え合えることや、安心して素の自分を出せることなど、コミュニケーション自体に価値を置く文化になっていきます。最近では、もし相手と行き違いが生じた場合も、「私は、ここがおかしいと思っていて、このように改善してほしいと思っています。あなたはどう思いますか」といった、相手を立てつつ自分の考えもきちんと伝えられるアサーティブなコミュニケーションが大切だと言われていますね。生々しい怒りや苛立ちをそのまま相手にぶつけるのではなく、自分の内面をよく観察して分析し、きちんと言語化して相手に伝える。そのような感情マネジメントやコミュニケーションをお互いにし続けることで関係性を維持することがよいと考えられているようです。一方で、MBTIなどの性格診断やキャラ設定によって自分や相手を記号化し、本当にその人がどういう人であるのかをあまり深く考えないような、時間と労力を節約する傾向も顕著になっています。感情の観察や分析と言語化、あるいは記号的な他者理解とタイパ・コスパ優位、これらは正反対のベクトルに見えますが、いずれにしても、コミュニケーションのあり方が合理化されてきていることは確かでしょう。理性的に感情に向き合い、無駄なく効率的に生きようとする傾向が目立ちます。
また、家庭においても、家事を愛情の証とはとらえずに「タスク」として割り切ってアウトソースしたり、パートナー間で担う量をイーブンにすることを試みるのが今の時代です。家事代行業者の広告では、アウトソースが家族の時間を確保するための有効手段だと宣伝されることもありますよね。家庭内の時間の使い方も効率性が重視されるようになっており、その意味での合理化も進んでいると思います。

Photo by Scott Umstattd on Unsplash
合理化されイーブンであることを重視するようになった一方で、女性のおかれる状況は改善されていないとも山田先生は語る。
山田:昼間は仕事、夜は家事・育児というように、1日の間にあたかも2つの勤務シフトで働いているような共働き家庭の忙しさを指して、A.R.ホックシールドは「セカンド・シフト」と名づけています。ファースト・シフトとセカンド・シフト双方の負担が特に共働き家庭の女性にかかりやすいこと、また、夫婦間での調整がうまく行かないことがアメリカの離婚率の高さにつながっていることを、1980年代にすでに指摘しています。2020年代の今、この本を読んでも日本の現状と重なるところが多くあると思います。
昼間はビジネスパーソンとして感情やふるまいをマネジメントし、終業後、疲れていても買い物に行って料理をし、子どもを定刻通り寝かしつけるために逆算して夜のスケジュールを組み、子どもの話を聞きながら家事も同時並行で進める……1日のうちに質の異なる労働とそれにともなう感情マネジメントをやり遂げること、その大変さを実感している共働き世帯は多いと思います。時短レシピや時短家電の人気には、時間の節約やコスパ意識だけではなく、こうした背景もあるのではないでしょうか。
仕事、家庭、政治――あらゆる場面で感情が前面にでる時代と社会学
山田:経済と労働の領域で感情が前に出てくるようになっていることに加えて、家庭内での合理化についてもお話ししてきたところで、エヴァ・イルーズが提唱した「感情資本主義」についても少し見ていきましょう。
感情資本主義とは「経済的行為のエモーショナリゼーション」と「感情生活の経済化・合理化」が同時に進行する動的プロセスのことを指します。従来の公私二元論では、「公」は合理的・理性的な領域であるとされ、「私」は情緒や計算不可能な愛が中心となる非合理的な領域だと見なされてきました。しかし現代社会はそうした図式だけでは語れないのではないか、とイルーズは指摘しています。
ビジネス界や家庭における感情規則や感情労働だけでなく、近年のアメリカ大統領選挙で見られたように、政治の場面でも共感による分断や怒りによる連帯が生まれるなど、感情が現代社会について考える際に重要になってきました。
このような社会の変化の中で、社会学においても感情が改めて注目されるようになったのです。
