
編集者・ライターとして働きながら2021年に岡山で本屋「aru」をオープンさせた、あかしゆかさん。本連載では、あかしさんにこれまでの働き方について振り返っていただきます。最終回は、働いた道程を振り返ることで感じた「キャリア」そのものについて、そして未来について綴ります。
- テキスト:あかしゆか
- 編集:吉田薫
- 撮影:kazuo yoshida
Profile
あかしゆか
1992年生まれ。2015年に新卒でサイボウズ株式会社へ入社、5年間ブランディング部での企画・編集を経て独立。現在はWEB・紙問わず、フリーランスの編集者・ライターとして活動をしている。2020年から東京と岡山の2拠点生活をスタート。2021年4月、岡山で本屋「aru」を開業。2025年4月、同じく岡山にて2店目となる「aru鷲羽山店」をオープン。
2025年。
2015年に大学を卒業して社会に出た私にとって、今年は社会人になってからちょうど10年が経過した節目の年である。私は東京のIT企業の会社員としてキャリアをスタートし、今では東京と岡山の二拠点生活をしながら、東京ではフリーランスの編集者・ライターとして、岡山では「aru」という小さな本屋の店主として仕事をしている。2025年4月には、2店目となる「aru 鷲羽山店」をオープンした。
思い返してみるとこの10年間は、自分自身と、そして共に生きていきたい他者との対話を重ね、働き方や生き方を模索しながら変化を続けてきた10年間だった。
自身の働き方を振り返る連載「働き方ルックバック」も、今回で最終回となる。最終回では、これまで書いてきたことを振り返りながら、私の「キャリア」という言葉に対しての思いや考えを総括してみたいと思う。
違和感や疑問に向き合い続ける
この10年を振り返ってみると、私のキャリアには「違和感」や「疑問」、「不満」や「不安」がいつだってつきものだった。就職したら、自分の希望する職種に就けていないことに対する不安を感じ、編集者になれたらなれたで携われるジャンルの偏りに不満を感じ、複業を始めたら正社員でい続けることへの疑問が生じて、フリーランスになって2拠点生活をしながら本屋をはじめたら、その属人的なあり方に対する違和感が生まれた。
一度に違和感や疑問、不満や不安がすべて消えるなんてことは決してなくて、ひとつの違和感と向き合って前に進んだら、その場所にはその場所なりの新しい違和感があった。それはまるでRPGで課せられるステージごとのミッションのようで、ひとつずつ、それらと向き合うことで自分の立ち位置を変化させてきた。悩みながら、戸惑いながら、でも心は前向きに(もちろん後ろ向きな瞬間もあったけれど)その疑問や違和感に向きあい、行動することで、自ずとキャリアが変わっていき、仲間も増えていったのだ。

今振り返ってみればに過ぎないのだが、そういった疑問や違和感に向き合う時、私は「急ぎすぎない」ことを大事にしていたように思う。心の中に湧き出てくる疑問や違和感は、本当に今のその生活を変えてまで向き合うべきものなのか。行動に移すタイミングはいつが良いのだろうか。まだしばらくこの場所で頑張ったほうが、後々のためになるのではないか──? 違和感があるからすぐ辞める、変化するのではなく、しばしその場所でもがいてみる。これは私の臆病な性格も起因していて、行動する勇気と確信をある程度貯めてからではないと、なかなか先には進めなかった(そのかわり、確信が生まれてから行動するまでの思い切りのよさはかなりあるほうだと思っている)。
そんな自分にじれったさを感じることはあったけれど、結果として、この石橋を叩いてから渡ろうとする自分の性質はあってよかったなと思う。会社員を5年続けた経験がいまのフリーランスの仕事を助けてくれているし、4年間ひとつの店舗で本屋の営業を続けてから2店舗目を開店できたことも大きかった。臆病に、されども時には大胆に。この矛盾したふたつの性質を合わせもって、私のダンジョンは進んでいったように思う。

見据えるべき未来と、見据えなくてもいい未来
このように、私のキャリアはその時々に自分の中に生まれる違和感や疑問をもとに変化を続けている。だから、あらかじめ「10年先の未来を考える」といったことはあまりしてこなかった。
就職活動の面接で聞かれる「10年後のキャリアプランをどう考えていますか?」といった問いには、どうしてそんなことを聞かれるのだろうとけっこう真剣に首を傾げていた。若いうちから具体的なキャリアプランを打ち立ててみても、自分の性格上、絶対にその通りにはいかないだろうと思っていたのだ。人生は、出会いや予期せぬ環境の変化で180度考えも方向性も変わっていく。特に私は人との出会いが自分に及ぼす影響が大きいタイプだと自覚していたからこそ、具体的にキャリアプランを(しかも新卒という若すぎる段階で)考えることにあまり意味を見いだせなかったのである。
でも、「どういう人たちと、どんなふうに笑い合っていたいか」という風景に対する未来は、いつだって思い描いていたような気がする。
仕事に思いを持っている人。仕事だけじゃなくて、一緒においしいご飯を食べたいと思える人。会社員にせよフリーランスにせよ搾取構造にならず、与えあうことができる人。そんな人たちと、笑いあい、刺激しあえる未来はどうやったら作っていけるのだろうか。漠然とした理想の景色が、いつも頭の中にあった。私の場合、具体的なプランよりも、そういった漠然とした景色が、キャリアの行く末を照らす光になってくれていたように思う。

けれども今は、そういった漠然と描く未来に加えて、「本屋を10年続けたい」という明確で具体的な目標を持つようにもなっている。これは、これまでの違和感を乗り越えてきた結果、はじめて私が「具体的に」見据えた未来でもある。自分自身の今の仕事、周囲の環境、大事にしたいと思える人々への確固たる信頼が生まれたからこそ、「大事なものを守り続ける」という意志を、キャリアプランとして描いてみてもいいなと思ったのだ。
見据えるべき未来と、見据えなくてもいい未来。そのふたつは時によって変わるのかもしれない──そんなことをふと思う。

魅力的な誘いに乗れる自分でいるために
何度も書いているけれど、少しずつ、自分の人生における違和感は減っていっている(もちろん今もあるけれど、昔に比べると減っている)。そうなってきた時に、じゃあ今私はキャリアにおいて何を一番大事にしているのだろうかと考えてみると、「好きな人たちの魅力的な誘いに、いつでも乗れる自分でいたい」ということだった。
魅力的な誘いを受けるためには、誘いたいと思われるような自分であり続けなくてはいけない。そして、誘いを受けたあとに「また一緒にやろう」と言いあえるような結果も残さなくてはいけない。
たとえば私に2店舗目の本屋を作ろうという話をくれたのは、岡山で私が本屋を続けているのを見て「ゆかちゃんだったらきっとこの土地を大切にしながら新しい店舗も作れるはず」と信じてくれた友人がいたからだし、今関わっている魅力的なプロジェクトたちも、私のことを信じて誘ってくれる人びとがいるからだった。
そのためには、自分自身の核となる「スキル」や「テーマ」が必要になってくる。私の場合は、それが文章であり企画や編集であり、そして場作りであった。「場作り」というのは本屋をはじめてからするようになったことだけれど、文章や編集に携わり出してからは8年以上が経っている。こういった、「自分はこれができる」という明確なスキルは、当たり前だけれど新しい仕事を掴んでいくうえでとても大切だ。まだまだ研鑽を積んでいる途中ではあるけれど、ひとつのことを突き詰めることの大切さも、この歳になってみるとあらためて痛感する次第である。
誰と共に、笑って生きていきたいか。私にとって仕事は、人と関わるための言い訳でもあるのだと思う。周囲の人々の成長を見て「私も頑張らなくては」と思うのは、比較や焦りや嫉妬などではなく、好きな人たちと、「本気で遊びながら一緒におもしろい仕事がしたいから」に尽きるのだ。
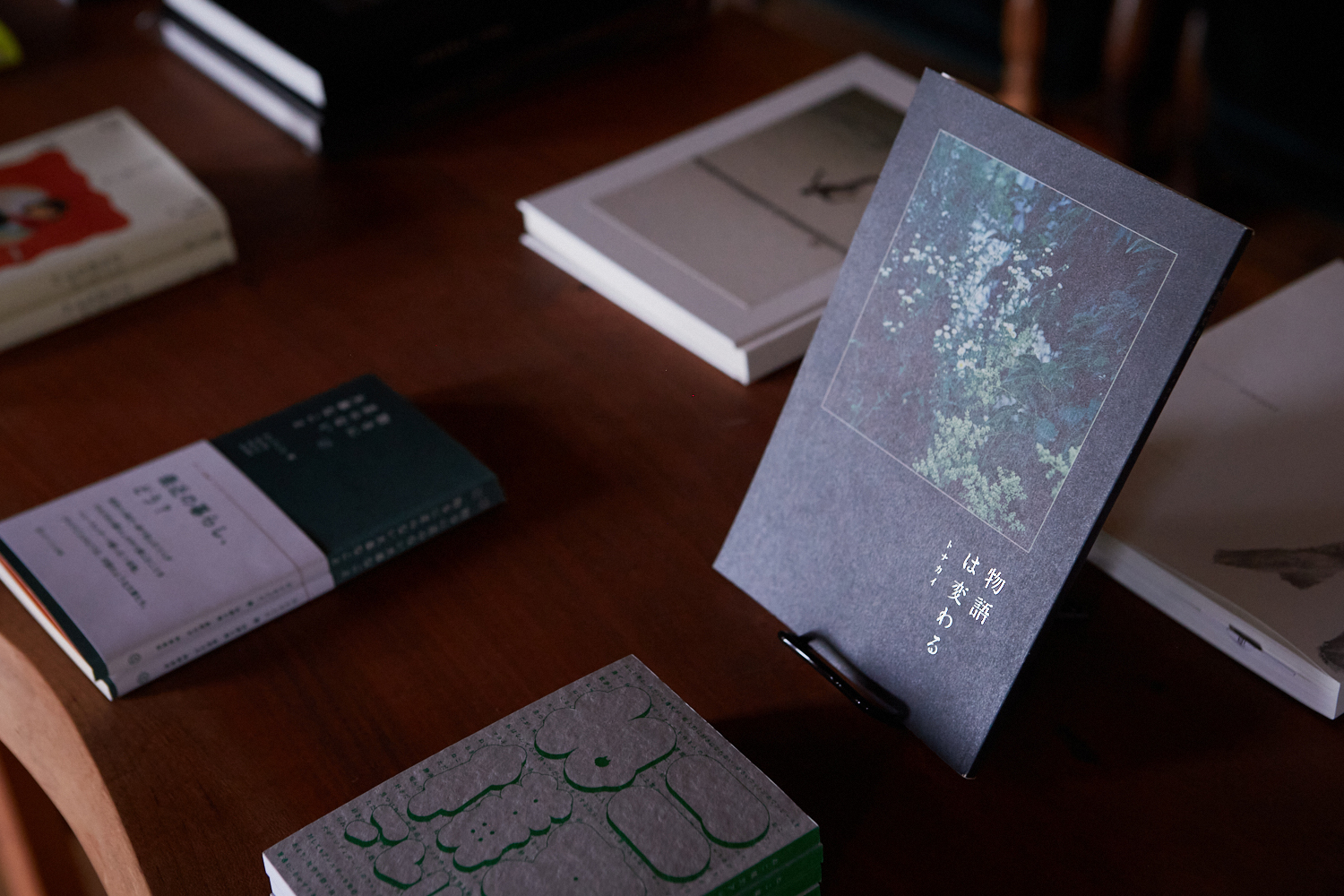
キャリアは人生の軌跡である
違和感や疑問と向き合い、前に進むこと。ゆるやかに未来を描くこと。そして、魅力的な仲間と共に人生を歩めるような自分であり続けること──。
こう考えてみると、何もこれは仕事に関してだけのことではないなと思った。パートナーシップにおいてもそうだし、ありとあらゆる人間関係にも当てはめることができる。
つまりはキャリアに対して大事にしていることは、私が人生で大事にしたいこととほとんど同じなのだ。
「キャリア」という語源を調べてみると、ラテン語の carrus(荷馬車) に由来しているのだという。そこからフランス語の carrière(道・競走路)へと繋がり、さらに英語の career(道筋、経歴、職業)へと発展していった。
つまり、キャリアとは人生の歩む道そのものなのである。
そりゃあ「設計」など不可能だよな、と思う。人生に予期せぬ出来事が多々起きるように、キャリアにだって予測不可能なことが起きる。山あり谷ありで、決してままならない。
「キャリアを積む」という言葉があるけれど、私はキャリアは積むものではなく、歩んでいく道そのものなのだと思った。自分自身の心と体をめいっぱいに使いながら、前へ、前へ。時に立ち止まり、時に後悔をしながらも、昨日よりも今日、今日よりも明日、「よい人生だった」と言える自分に近づくために。そういった生きている実感を持ちながら仕事をしてきた自負はあるし、これからもそうやって仕事をしていきたい。
そうして、人生の最後に「いいキャリアだったな」と言えるようなキャリアを、これからも歩んでいきたいなと思っている。




