
人生に合わせて働き方や場所を柔軟に変化させてきた、あかしゆかさん。本連載では、あかしさんにこれまでの働き方について振り返っていただきます。第3回は岡山で本屋を始めた時のお話です。
- テキスト:あかしゆか
- 編集:吉田薫
- 撮影:タケシタトモヒロ
Profile
あかしゆか
1992年生まれ。2015年に新卒でサイボウズ株式会社へ入社、5年間ブランディング部での企画・編集を経て独立。現在はウェブ・紙問わず、フリーランスの編集者・ライターとして活動をしている。2020年から東京と岡山の2拠点生活をスタート。2021年4月、岡山で本屋「aru」を開業。2025年4月、同じく岡山にて2店目となる「aru鷲羽山店」をオープン。
2025年。
2015年に大学を卒業して社会に出た私にとって、今年は社会人になってからちょうど10年が経過した節目の年である。私は東京のIT企業の会社員としてキャリアをスタートし、今では東京と岡山の二拠点生活をしながら、東京ではフリーランスの編集者・ライターとして、岡山では「aru」という小さな本屋の店主として仕事をしている。
思い返してみるとこの10年間は、自分自身と、そして共に生きていきたい他者との対話を重ね、働き方や生き方を模索しながら変化を続けてきた10年間だった。
自身の働き方を振り返る連載「働き方ルックバック」。第3回目の今回は、個人事業主になってしばらくが経ち、自身の本屋をはじめることになった話をしたいと思う。
芽生え始めた「仕事を自ら作りたい」という気持ち
これまでの2回のコラムでは、5年間勤めた会社での出来事、そしてフリーランスの編集者・ライターとして仕事をするようになって感じ、考えてきたことを書いてきた。
仕事はどんどん楽しくなっていった。少しずつ、信頼と実績を積み重ね、時にはもちろん自分自身の未熟さに悩むこともあった(し、今もある)けれど、周囲の人に恵まれ、成長できている感覚はあった。いただくお仕事も、自分の興味のど真ん中であることが増えていき、「やりたいこと」「できること」「求められること」の円が重なりはじめ、それが仕事のやりがいにもつながっていったのだ。
けれども私はひとつだけ、ずっと自分の中で引っかかっていたことがあった。それは、「自分自身の力で、ゼロから何かを生み出したことがない」ということだ。

編集者やライターという仕事は、多くの場合「誰かのやりたいことを形にする」という性質を内包する。もちろん、本の編集や、エッセイを書いたりする仕事は、自分がやりたいこと・書きたいことが仕事になるので表現としての側面もあったけれど、そこにもクライアントの存在はあって、「誰かが求めていること」がまずあり、それを叶えていくという矢印の方向であることが私の場合は多かった。
私は、自分で何かを生み出すよりも、誰かがやりたいことを形にするほうが向いている。そして、それこそが自分のやりたいことなのだ──。長らくのあいだそう思って生きていたけれど、それはただ単に、やったことがないのに「ゼロから生み出すのは私にはできない」という、臆病が故の自分自身への決めつけでもあったかもしれない。歳を重ねるにつれ、覚悟を持って場所やブランド、会社を持つ知人友人が増えていき、そういった人たちへの尊敬と憧れもあった。さらにはクライアントワークに生計を依存しすぎることの怖さも感じていた。
「自分で何かを作り出してみたい。」
明確に言葉にしていたわけではないけれど、少しずつ私はそう思うようになっていたのである。
コロナ禍がもたらした、またとない機会
新型コロナウイルス感染症の流行が日本にやってきたのは、そんなことをぼんやりと考えはじめたタイミングと重なっていたと思う。
プライベートで離婚を経験し、仕事も一度コロナ禍で小休止がかかり、人生に空白が生まれた時に、岡山とのご縁があった。以前から仲良くしていた友人が岡山の海沿いでホテルを開業し、落ち込んでいた私を2週間のワーケーションに誘ってくれたことがきっかけである。
その滞在で瀬戸内海の美しさに心身を救われている時に、「空いている物件があるから、この土地で何かを始めてみたらどうか」というお誘いをいただいた。
「何か、やりたいこととかないの?」
そう友だちから問いかけられた時、私は自然と、「本屋をやってみたい」と口に出していたのだ。
これまで、本屋を始めることになったきっかけを多くのメディアで「衝動だ」と書いてきたけれど、こうやって今までのことを体系立てて振り返っていると、「ゼロから何かを生み出してみたい」「誰に頼まれるでもなく自分自身がやりたいことをやってみたい」という思いが私の中にはすでにあって、そのことが、本屋をはじめたいという決断に大きく影響を与えていたのだと思う。
大学時代に本屋で働いた経験から、本という媒体に人生を動かされてきたこと。そして文章を仕事にしたいと思うようになり、実際に編集・ライターという職業に就いたこと。人間関係が広がり、信じられる、尊敬できる人たちが周りにいてくれるようになったこと。
これまでの経験や、考えてきたこと、出会ってきた人びと。そういった人生のいろんなことが帰結して、私ははじめて、「何かを自分自身ではじめてみたい」と思った。今ならできるかもしれないと、そう思ったのだ。

それまでの経験を集結させる
そうして私ははじめて、まったく誰にも頼まれていないのに、自ら仕事をつくることに挑戦することになった。
本屋のはじめ方もわからない。できるかもわからない。けれども、その時の私は失うものがほとんどなかった。むしろ、何かを作ることで自分が救われるだろうと思っていた。
これまでの知識と経験、そして培ってきた人間関係を総動員させて、場所づくりに取り組んでいった。会社員時代にプロジェクトマネジメントはしたことがあったし、編集者はそもそも、必要な人たちを巻き込んで、作りたいものを形にしていくという仕事でもある。
お金のこと、仕入れのこと、古物商などの資格のこと、空間づくりのこと。ひとつひとつ、必要なタスクを分解して、目の前の課題に取り組んでいく。その時々で生まれる困難には、幸運なことに都度助けてくれる人が現れた。この時に助けてくれた人の恩を私はずっと忘れないし、これから先、次の世代の人が何かを作ろうと思った時、純粋に応援の手を差し伸べられる大人でありたいなと思っている。
そうして1年弱の準備を通して、2021年の4月にオープンしたのが、「aru」という本屋だった。
「本屋」と「編集・執筆」の二足の草鞋で
本屋という商売の厳しさは、大学時代に本屋で働いていたり、本屋の知人から話を聞いたり、好きが故にさまざまな本屋に関する本を読んだりしていたことで、少なからず知っていた。だからこそ、私は自分とお店の健全さを守るためにも、編集者・ライターとしての仕事と本屋の仕事を両立させようと当初から決めていた。
編集者やライターの仕事は、原価がほとんどかからない。一方、本屋は本を仕入れるだけで原価が約7割かかり、さらに家賃や光熱費、備品代や2拠点生活を続けるための費用も追加でかかってくると考えると、生きるための十分な利益を本屋だけで作ることは現実的ではないと考えていた。だからこそ、自分が地方で本屋をはじめることで生まれる新しい仕事や、もともとしていた編集やライターの仕事をまるっと込みで考えて、トータルとしての事業で考えるのがよいと思っていたのだ。
そして何より、私はクライアントワークが好きなことに変わりはないのだった。文章や企画を通して、自分が素敵だと思う企業や人の力になれること。その喜びは、昔も今も変わらずある。だからこそ、前回のコラムでも書いたように、お金や人間関係、自身の成長、社会的な意義など、仕事で得られるものを全体のバランスとして考える。さらには今のパートナーとの関係性や、求めるライフスタイルなども考慮したうえで、仕事のポートフォリオを作っていくことが大事だと思うようになっていた。
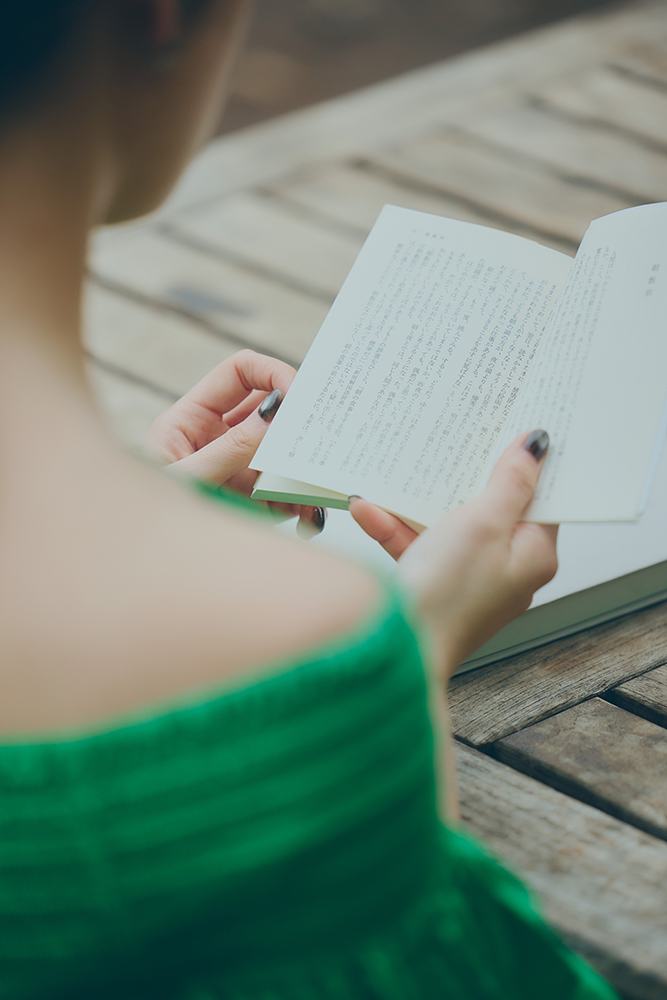
肩書きは、人との関わり方を示すものなのかもしれない
本屋をはじめてよかったことはたくさんあるのだけれど、今回のコラムの「キャリア」というテーマに合わせると、「仕事における、人との関わり方の種類が増えた」ということが大きくあるなと思う。
編集者・ライターとして、主に文章に関する仕事をしていると、仕事で誰かと関わるのは必然的に「ことばが必要になった時」となる。
もちろん文章はコミュニケーションの礎なので、さまざまな関わり方ができる。けれども職能としては一定の形であるため、もう少し仕事で人といろんな関わり方ができれば……と思うことは少なくなかった。「本屋」という新しい仕事をはじめたことで、これまでになかった形での人との関わり方を見つけられるようになったのだ。

ブックマーケットに出店者として呼んでもらったり、本のある空間をつくる相談をしてもらえたり、イベント登壇の仕事が増えたり、地方での仕事をいただけたり、友人と一緒にポップアップイベントを開催したり。「本屋」という商いをはじめたことで「やろう」と思えたり、声をかけてもらえることが増えていった。
本屋を始めたことで、さまざまな商いをしている人たちと対等な目線で話せるようになったことも大きい。店をやる上での葛藤や苦労、原価率、仕入れルート、成り立ち、特徴など。「商売」という共通点は業界を超え、さまざまな業界で働く人との共通言語を生み出してくれた。
あたらしい肩書を手にすることは、世界と関わるあたらしい切符を手にすることなんだな、と今では思う。もちろん、むやみやたらに肩書きを増やすつもりは毛頭ないし、それ自体が目的となって何かを始めることはないのだけれど。
でも、結果として「人との関わり方が増えたこと」は、私が本屋をはじめてよかったな、と思うことのひとつなのである。
本屋をはじめて4年。2店目をつくることに
そんな生活をはじめてから、はや4年が経った。もちろん「本屋として利益を出すことは難しい」と思いつつも、その道を諦めているわけでは決してない。イベントの企画や、自費出版の本づくり、オンラインストアの開設、グッズ制作、本屋の存在を知っていただくための試行錯誤を重ね、本屋の売り上げも、開店当初に比べて倍以上になった。赤字にはなっていないし、ゆっくりな歩幅ではあるけれど、着実に歩んでこれた自分を少しは褒めてあげたいな、と思う。
そして私は次なるステップとして、なんと2店目の本屋を開くことになったのである。
今年の4月、aruの2店目となる鷲羽山店を同じ岡山県でオープンした。しかも今度の本屋は、不定期営業ではなく、週に5日間空いている、定期営業の本屋である。
──さて、次回のコラムでは、なぜ2店目の本屋をはじめることになったのか、そこで目指していることは何なのかを書きたいと思う。





