
会社員やフリーランス、本屋経営まで、自分の人生に合わせて働き方や場所を変化させてきたあかしゆかさん。本連載では、働き始めて10年という節目をむかえたあかしさんに、これまでの働き方について振り返っていただきます。第2回はフリーランス時代のお話です。
※第1回「いち会社員が、複業を経て独立するまでの話」はこちらから
- テキスト:あかしゆか
- 編集:吉田薫
- 撮影:西田香織
Profile
あかしゆか
1992年生まれ。2015年に新卒でサイボウズ株式会社へ入社、5年間ブランディング部での企画・編集を経て独立。現在はウェブ・紙問わず、フリーランスの編集者・ライターとして活動をしている。2020年から東京と岡山の2拠点生活をスタート。2021年、岡山で本屋「aru」をオープン。
2025年。
2015年に大学を卒業して社会に出た私にとって、今年は社会人になってからちょうど10年が経過した節目の年である。私は東京のIT企業の会社員としてキャリアをスタートし、今では東京と岡山の二拠点生活をしながら、東京ではフリーランスの編集者・ライターとして、岡山では「aru」という小さな本屋の店主として仕事をしている。
思い返してみるとこの10年間は、自分自身と、そして共に生きていきたい他者との対話を重ね、働き方や生き方を模索しながら変化を続けてきた10年間だった。
自身の働き方を振り返る連載「働き方ルックバック」。第2回目の今回は、フリーランスとして仕事をするようになった初期の頃の話をしたいと思う。
はじめて「個人」として仕事をいただいた時のこと
前回のコラムでも書いたように、私がサイボウズを辞めて完全にフリーランスになったのは2020年のこと。ただ、それまでも複業で編集や執筆の仕事を受けていたので、「個人事業主」として開業届を出したのはもっとはやく、2017年のことになる。
そう人に伝えるとよく聞かれるのが、「どうやって社外からお仕事をもらえるようになったのですか?」ということだ。たしかに、フリーランスになろうと決意できたのは、会社員をしながら個人事業主としてある程度の仕事を受けられるようになったから、という理由が大きくある。なのでまずは、私がはじめて複業をした時のことから話をしてみたい。
個人で最初に仕事をもらった時のことは、今でもはっきりと覚えている。会社員として働いていた頃、Twitterで何度かやりとりをしたことがあった編集者の方から、「会社が複業OKなのであれば、一緒にお仕事をしてみませんか?」と声をかけていただいたのだ。
当時、私はサイボウズのブランディングの部署でオウンドメディアの編集や執筆の仕事をしていた。社内の先輩が編集者としての基礎をしっかり教えてくれていたけれど、より体系立てて編集や執筆のことが知りたいと思った私は、社外で開催されていた、宣伝会議の「編集・ライター養成講座」や「ほぼ日の塾」といった編集を学べる講座にもいくつか通っていた。
同じ時期に、Twitterやnoteのアカウントも開設して、少しずつ自分自身の言葉での発信もはじめていった。それまでTwitterは超プライベートな鍵つきのアカウントしかなかったのだけれど、実際に編集者として記事をつくるようになって、「自分でつくったものを、自分の力で読者の方に届けられるようになりたい」と思ったのだ。
そのほかにも、自分の言葉を紡ぎ出したのには、今感じているこの気持ちが記憶からこぼれ落ちてしまわないよう、どこかに残しておきたいという理由もあった。Twitterは仕事や生活における思考や感情をアーカイブするものとしてとてもいいツールだなと思ったし、自分の思いを140字にまとめるという行為も、きちんとやってみると編集的な要素があっておもしろさがあった(いまではXになったことで使い方が変わってしまっているけれど)。
サイボウズでの働き方のこと、読んだ本や見た映画のこと、日々の生活のなかで自分の琴線に触れた出来事、社会で気になったニュースのシェア……。そうやって、いわば「雑誌的に」自分自身について発信していたものを、その編集者の方は見てくれていたのだという。「何も実績がないのですが」と伝えたとき、「きっとあかしさんなら大丈夫だと思います」と言ってくださったのだ。
後日、「どうしてあの時、信頼してくださったんですか?」とその人に聞いたことがある。すると、発信していた内容と実際に話したことである程度の人柄はわかったこと、何が好きそうかが発信から見えたこと、そしてやってみたい仕事に対して意欲と実際の行動がともなっていたこと、などを挙げていただいた。
はじめは誰しも実績がない。けれどもたしかに、「何がしたいのか」「そのために何をしているのか」「その結果、今どこまでできるのか」は伝えることができる(それがインターネットでもそうじゃなくても、文章であってもそうでなくても、だ)。言葉に関わる仕事がしたい、という希望だけではなくて、実際に行動をしていたこと。そのことが、フリーランスとして一歩踏み出すきっかけにつながったのかもしれない。
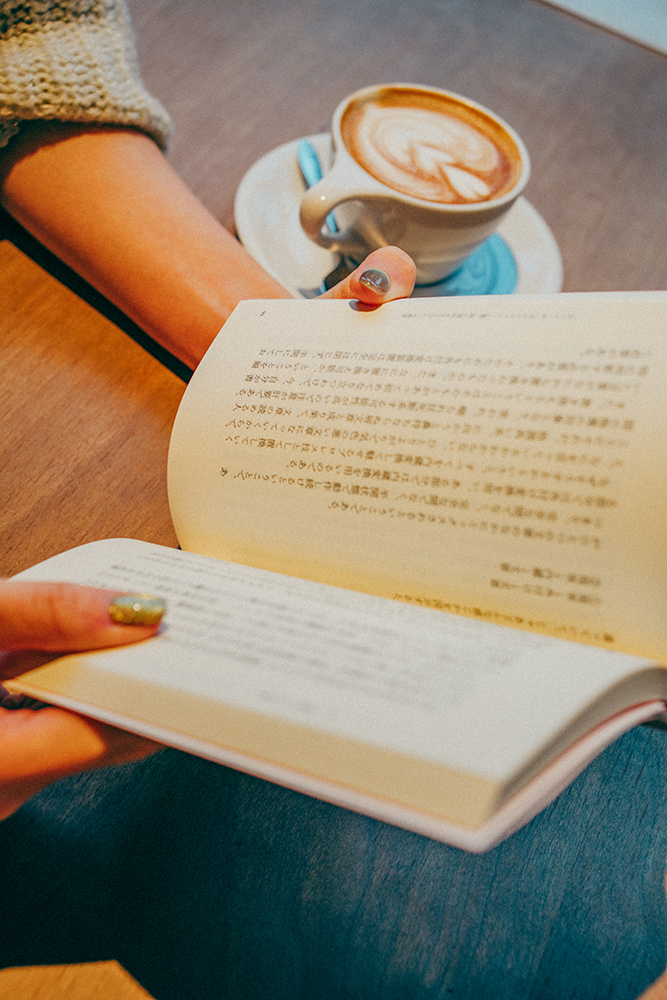
フリーランスは、利点と欠点が紙一重
そうして会社員での複業時代を経てフリーランスになったわけだけれど(それまでにもいろんな出来事があったけれど、その話は前回のコラムと重複するので割愛する)、フリーランスになってみて、その働き方の特徴は、時と場合によって利点にも欠点にもなりうるということを感じるようになった。「自由」とは、甘美な響きと同時に、残酷さも介在するのである。
たとえばフリーランスは、
①時間や場所を選んで働けること
②自分の体調や意欲が、収入と直結すること
③仕事量の全体像を把握できるのは自分自身だけであること
④クライアントワークや創作活動など、仕事の種類を自分で組み立てられること
などが特徴として挙げられると思う。
「①時間や場所にとらわれずに働けること」は、好きな時間に休んだり旅行したりできるという利点にもなれば、オンオフがつけづらくいつまでも働いてしまうという欠点にもなるし、「②自分の体調や意欲が、収入と直結すること」は、言わずもがな調子がいい時と悪い時の収入の差につながっている。
「③仕事量の全体像を把握できるのは自分自身だけであること」は、他者からマネジメントをされることが苦手な人からすれば利点だけれど、自分自身のがんばりや成長を認めるのが自分しかいなくなるということでもあり、そこに一抹の寂しさや、モチベーション維持の難しさを感じるという欠点を感じる人もいるだろう。「仕事の種類を自分で組み立てられること」は、軌道に乗っている時は自分主体でいられるけれど、余裕がなくなってくるとその主体性は一気に失われる。
フリーランスになりたての頃は、これらのバランスをうまくつかむことが難しかった。というよりも、私は2020年3月──つまりは、本格的にコロナ禍に入った頃にちょうどフリーランスになったので、上記のようなフリーランスならではの要素を感じたのは、もう少しあとのことではあったのだけれど。コロナ禍の初期は、とにかく毎日を生きるのに必死だったと記憶している。

仕事を、単体ではなく全体のポートフォリオで考える
コロナ禍が次第に落ち着き、フリーランスとして仕事を順調にいただけるようになると、前述したような楽しさ・難しさを感じると同時に、「編集・執筆の仕事」には本当にさまざまな種類があることを実感するようになった。
たとえば、「クライアントワークで執筆の仕事をする」という事実ひとつとっても、その実態は多岐にわたる。オウンドメディアでの執筆、事業として存在するメディアでの執筆、広告代理店が企業から受けているプロモーションのなかでの執筆、コーポレートサイト内での執筆、などなど。
自分が受ける執筆や編集のお仕事が、どんな会社の、どんな事業の、どんな役割としてあるものなのか。そのビジネスの構造はどうなっているか。社会的な意義は? 予算は? 関わる人は? 期間は? プロジェクト内での自分の立ち位置は──?
執筆や編集という仕事を俯瞰して見つめ直してみると、そこにはさまざまな種類が存在することに気づくのである。
たとえば、社会的に意義があって、憧れの人と仕事ができるけれど、その事業の立ち位置的に、どうしても単価が極端に低くなってしまうものがあったとする。その仕事を受けることで自分自身が成長もできそうだし意義も感じるしぜひやりたいけれど、そういった仕事「だけ」を受けていると、自分の生活がままならなくなってしまう。
逆に、単価は高いけれど、コミュニケーションなどにおいて少し違和感を感じるような依頼があったりもするし、バランスよく、すべてにおいてハッピーな仕事もある。
その仕事を通して、社会や人のためにできることは何なのか。
その仕事を通して、クライアントのためにできることは何なのか。
その仕事を通して、自分自身のためになること(成長や金銭面、人間関係の喜びなど)は何なのか──。
ひとつの仕事だけで、すべてのバランスを保つのは難しい。逆に言えば、ひとつの仕事だけを見ると少しバランスが悪かったとしても、全体でバランスが取れていれば自分自身の幸福度は高くなるとも言える。私のフリーランスとしての働き方は、複数のプロジェクトを受けながら成り立たせるものだったからこそ、健全に生きていくためには、自分のキャパシティの中で、これらのバランスを全体として取っていくことが大切なのだと思うようになっていった。
わたしは常に、今受けている仕事を一覧で見られるようにしている。そして自分が何かしんどいな、と思ったら、じっとその一覧を見つめ、何がそうさせているのかを分析し、少しずつ仕事内容を調整するように働きかけている(それを相談させていただけるクライアントさんばかりで日々感謝である)。
そういった調整がうまくできた時にはじめて、フリーランスの働き方の特徴がすべて「利点」として捉えられるようになるのだ、と思ったのだ。
──そして、ある時にその「バランス」を考えてみて気づいたことが、「クライアントワークではない、自分自身でつくりだす仕事をしてみたい」という気持ちだったのである。
さて、次回は二拠点生活をはじめて、自分自身の事業「本屋」をはじめるようになってからの話をしたいと思う。





